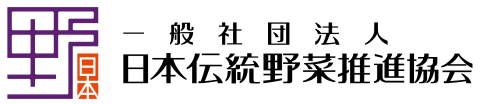この秋は祭に参加してみよう! ~自然や神々、人々に感謝を伝え、ねぎらい、癒す「収穫祭」の魅力~
目次
令和の米騒動が続いた2025年ですが、米価も高止まりで落ち着くのでしょうか?
資材やエネルギーコストも上昇する中、米農家さんが経営を持続するためには、値上がりも致し方ない面もあります。猛暑が続いた今年の米の出来は、どうなのでしょうか?私は農家の関係人口として、すでに早出し米の新米を頂きました!春に自分が田植をした田んぼのお米を頂くのは、なんとも感慨深いものです。
日本の年中行事や祭りの多くは、稲の豊作を祈る・感謝するなど農耕の祭事に由来しており、米をはじめとする五穀や冬を越すための農作物が収穫される秋は全国的に多くの祭が開催されます。そこで、今回は農耕にまつわる秋祭りをご紹介しつつ、あらためて、農作物の収穫に感謝する機会にしたいと思います。

自然への感謝を表す秋の収穫祭
秋の訪れとともに、黄金色に染まる田んぼや、たわわに実る果樹園。この豊かな風景は、私たちの食卓に欠かせない恵みをもたらしてくれます。日本人が古くから大切にしてきたのが、この自然の恵みに感謝する「お祭り」です。
昔から稲作を中心とした生活を送ってきた私たちは、自然の力に生かされ、その恵みなしでは生きていけませんでした。だからこそ、豊作を祈り、そして実りを得たことへの感謝を神様に捧げるための行事を大切にしてきました。
秋の収穫祭は、単に豊作を祝うお祭りではなく、私たちが日々の暮らしの中で忘れがちな、食べ物への、そして自然への「感謝の心」を形にしたものです。
神嘗祭(かんなめさい)
収穫に感謝する代表的な祭としては、宮中行事として、毎年10月17日に伊勢神宮で行われる神嘗祭があります。
神嘗祭は、伊勢神宮で行われ、その年に収穫された初穂を天照大神に奉納する最も重要な祭儀です。天皇が皇居から伊勢神宮を遥拝し、奉献の儀式が行われるほか、伊勢神宮では由貴大御饌(ゆきのおおみけ)や奉幣(ほうべい)などの重要な儀式が執り行われます。
新嘗祭(にいなめさい)
新嘗祭は、毎年11月23日に行われ、その年に収穫された新米や新酒を天照大御神をはじめとする天地八百万の神々に捧げ、天皇陛下自らもこれを食し、国民と共に収穫を祝う宮中祭祀です。毎年11月23日に行われ、現在の「勤労感謝の日」のルーツとされています。
神嘗祭が伊勢神宮に限定されるのに対し、新嘗祭は宮中と全国の神社で同時に行われることも大きな違いです。
収穫祭から見える日本の文化
宮中行事のような国家的収穫祭のほかにも、全国各地で、その土地の風土や信仰に合わせて異なるかたちの収穫祭が行われます。その祭の形態は、地域によってさまざなに個性的な祭が催されています。
ずいき祭
京都市北区の北野天満宮で10月1日から5日まで開催される五穀豊穣を祈願する神事です。ずいき祭の最大の特徴は、食用の里芋の茎である「ずいき」や様々な野菜で飾られた「ずいき神輿」が特徴的です。初日には御旅所へ渡御し、最終日には本社へ還幸する神幸祭・還幸祭が行われ、伝統芸能の奉納も行われます。
https://souda-kyoto.jp/event/detail/zuikimatsuri.html
くんち
九州地方では、収穫に感謝して行われる秋祭り「くんち」が行われます。「くんち」の語源は、旧暦9月9日の重陽の節句にあるとされ、神社の「例大祭」を意味することもあります。特に「長崎くんち」、「唐津くんち」、「博多おくんち」が有名です。
長崎くんち
毎年10月7日から3日間、長崎市の諏訪神社で行われます。巨大な曳山が街を練り歩くことで知られており、「奉納踊り」や、船を模した「曳物」の巡行が特徴です。中国やオランダなど異文化の影響を受けた独特の演し物が見どころで、演し物をもう一度呼び戻す際に観客が「モッテコーイ!」と掛け声をかけるのは必見です。
博多おくんち
毎年10月23日から25日頃にかけて福岡市博多区にある櫛田神社で行われる秋季大祭です。最大の見どころは、絢爛豪華な「神輿行列(みこしぎょうれつ)」です。10月24日の本祭では、ご神体を乗せた神輿が氏子地区を巡行します。また、「神幸祭(おくだり)」と呼ばれる行事では、神輿が氏子町を練り歩き、五穀豊穣と地域の安全を願います。
唐津くんち
毎年11月2日から4日の3日間、佐賀県唐津市にある唐津神社で行われる秋季例大祭で、ユネスコ無形文化遺産にも登録されており、日本を代表する祭りの一つとして知られています。豪華絢爛な漆と金箔で造られた巨大な「曳山(ひきやま)」14台を、曳き子がお囃子(はやし)に合わせ「エンヤー」「ヨイサー」の掛け声をかけ街中を曳き回します。

十日夜(とおかんや)
旧暦10月10日(2025年は11月29日)に東日本を中心に広く行われる伝統的な祭事です。「とおかんや」という言葉は、漫画「夏目友人帳 漆 第3話」で、奇妙な案山子が出てくる話があり、若い人が知っていたりするので驚きますが、実際は、稲作の収穫を感謝し、餅をついて神様に感謝を捧げたり、田の神を送り出す行事です。「わら鉄砲(わらづと)」という藁(わら)で作った束を作り、子供たちがこれを手に、家々を回って地面を叩き、大きな音を立て田の神様を送り出す儀式とされています。地域によってさまざまな形で受け継がれており、現代では新暦の11月上旬頃に行われることが多くみられます。
ところで、最近は「わら不足」に陥っているのをご存じでしょうか。稲刈り機の進化で、わらが細かく裁断されてしまうようになったため、しめ縄などの伝統工芸品や農業資材に使う十分な長さのわらを手に入れることが難しくなっています。そのため、知人は一部を手で稲刈りをして、わらを神社に供給していました。しめ縄がケイントップ(とうもろこしの茎)やカカオハスクで作られるようになったら、さすがに寂しい…。
亥の子祭(いのこまつり)
旧暦10月の亥の日に行われる行事で、主に西日本に伝わる収穫感謝のお祭りです。秋の収穫を祝い、田の神様に感謝を捧げる大切な行事です。餅を搗いて収穫を祝い、その餅で、イノシシの子の「うり坊」を模した亥の子餅(いのこもち)を作ります。イノシシは、子沢山なので、これにあやかり、子孫繁栄や無病息災を祈ったりします。

その形式は、京都の護王神社で行われる平安時代に宮中で行われていた年中行事「御玄猪(おげんちょ)」にちなんだ厳かに行われるものから、広島で行われる子ども達が中心となって「いのこ、いのこ、いのこもちついて、 繁盛せい、繁盛せい……」と言いながら、亥の子石をついて廻り巡るお祭りまで多様です。
祭りや風習は中国から伝わったとされ、平安時代には宮中行事となり、鎌倉時代以降庶民にも広まりました。
霜月祭(しもつきまつり/そうげつさい)
旧暦11月を指す霜月に行われる収穫祭で、「しもつきまつり」や「そうげつさい」と呼ばれます。九州などでは、田に残した稲を神に供える習慣があるそうです。
長野県飯田市で行われる霜月祭り(しもつきまつり)は、国の重要無形民俗文化財になっています。湯立神楽が主体で、昼間が最も短く生命力の弱まった冬至の頃に全国の神々を招き、お湯でもてなし、太陽と生命の復活を祈る儀式とされています。
「ん?お風呂で神々をもてなす?どこかで聞いたような…」
と思う方もいるかもしれません。そう!あの映画「千と千尋の神隠し」のアイデアは、この湯立神楽からきたものなのだそうです。
(湯立神楽の行事は各地で行われており、神社によってその方法はさまざまです)
遠山の霜月祭 – 飯田市ホームページ
信州遠山郷観光協会公式サイト
奈良県御所市の鴨都波神社では、10月スポーツの日の前々日の土曜日に催される秋祭り宵宮に「ススキ提灯献灯行事」が行われ、五穀豊穣・家内安全・無病息災を祈願します。この行事は、奈良県無形民俗文化財に指定されており、「御所まち霜月祭(そうげつさい)」で提灯演舞が再現されます。
奈良県御所市「御所まち霜月祭(そうげつさい)」
大和鴨大明神 鴨都波神社
宮崎県高千穂町で行われる高千穂夜神楽まつりは、11月から翌年2月に行われる祭で、地域住民が氏神様を神楽宿に招き、五穀豊穣への感謝と願いを込めて、夜を徹して行われる伝統的な神事です。神楽宿では、一部の演目が舞われ、観光客も参加して地域の交流を深めることができます。

これらの他にも、各地の神社で秋祭りが催されたり、地域の農産物直売所などで「感謝祭」が開催されたりします。このように、日本の文化の根底には、収穫の喜びを分かち合い、自然や神様を労う気持ちが祭りに現わされています。
感謝を示す祭の表現
収穫の感謝を示す祭の表現には、さまざまな形式があり、例えば、火を使った祭り(豊作を願う火祭り)、神輿や山車を出す祭り(神様への感謝を表現)、五穀を使った祭り(お団子や餅を捧げる)などがあります。
神輿や山車を担いで地域を練り歩くお祭りでは、神様を迎え、収穫の喜びを分かち合います。また、収穫されたばかりの五穀でお団子や餅を作り、神様に捧げたり、地域の人々で分け合ったりする風習も、日本各地に根付いています。
受け継がれる「伝統」
これらの収穫祭は、単なる一年ごとの行事ではありません。それは、親から子へ、そして次の世代へと受け継がれる「伝統」そのものです。お祭りを通じて、地域の人々は力を合わせ、準備から片付けまでを共に行います。そうした中で、地域の絆はより一層強くなり、未来へと続く大切なコミュニティが育まれていきます。収穫祭は、日本の文化や人々の温かさを知る、貴重な機会と言えるでしょう。
現代の私たちと収穫祭
身近な場所でも体験できる
スマートフォンひとつで何でも手に入る現代の暮らし。スーパーに行けば、野菜や果物が一年中並び、旬を問わず、いつでも好きなものを食べられるようになりました。しかし、あまりにも便利になったからこそ、私たちは普段食べているものがどこから来て、誰が作ってくれたのかを考える機会が減ってしまっているのではないでしょうか。
収穫祭は、そんな現代の私たちに「食」を見つめ直す大切なきっかけを与えてくれます。 実際に田んぼや畑の恵みに触れ、作り手の顔を見て感謝を伝えることで、食べ物に対する気持ちがより一層深まります。
収穫祭と聞くと、遠方まで足を運ぶ大規模な祭りを想像するかもしれません。でも、そんなことはありません。多くの収穫祭は、意外と私たちの身近な場所でも行われています。地元の神社やお寺で開かれる小さな秋祭り、農産物直売所での感謝祭など、探してみると、きっとあなたにぴったりの「収穫祭」が見つかるはずです。まずは身近な場所から、日本の豊かな恵みに感謝する心に触れてみませんか。

自然や人々とつながる機会
収穫祭は、単なる季節のイベントではありません。それは、私たちが自然と共生し、日々の食に感謝してきた、日本の長い歴史そのものです。そして、地域の人々が力を合わせ、過去から未来へと大切な伝統をつないでいく、人と人との絆を育む大切な行事でもあります。この秋、もしお祭りを訪れる機会があれば、その土地の恵みや人々の温かさに触れてみてください。
そして、もし、それが難しかったら、いつもの食卓に並ぶご飯や野菜に、少しだけ心を込めて「ありがとう」と伝えてみませんか?その小さな一歩が、きっとあなたの毎日を、もっと豊かにしてくれるはずです。