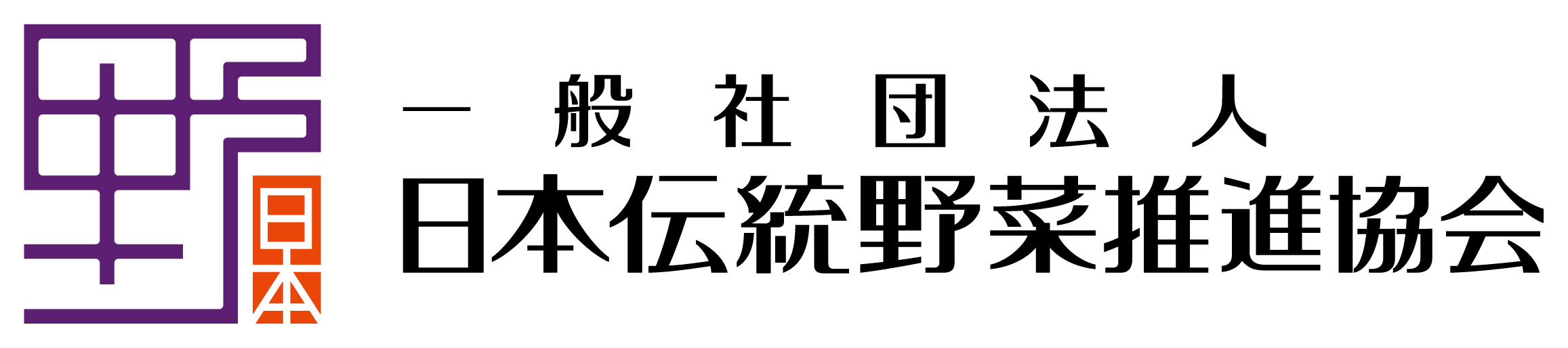目次
どの時代にどんな野菜が渡来したのか?
日本の野菜のほとんどは、かつて中国やヨーロッパをはじめとする世界各地から渡来したものです。どのような野菜がいつ頃に日本にやってきたのでしょうか?歴史的資料で確認できる代表的な品種をみていきたいと思います。
縄文時代~弥生時代
最も古いのは、縄文時代に渡来していた蓮根(れんこん)です。今でもよく食べられている蓮根は、仏教伝来とともに栽培されるようになったといわれています。蓮の花の根なので、なるほどという気がしますね。里芋も弥生時代には在ったとされ、稲作以前の主食であったと考えられています。

古墳時代~飛鳥時代
大根(だいこん)や生姜(しょうが)も古く、日本への渡来は古墳時代とされています。大根は「すずしろ」と称されており、「だいこん」と呼ばれるようになったのは室町時代以降とされています。生姜も別名「はじかみ」と言い、中国の歴史書「史記」に記録が残っています。葱(ねぎ)はその少し後の飛鳥時代に渡来したとされており、奈良時代に成立した「日本書紀」に登場しています。
奈良時代
蕪(かぶ)も「日本書紀」に栽培を奨励する記述が残されています。大蒜(にんにく)は「日本書紀」や平安時代の「源氏物語」に記されています。当時は主に薬用として用いられており、一般に普及するようになったのは世界大戦後のことです。驚くことにレタスも奈良時代にあったそうです。チシャと称されていました。結球する玉レタス(玉チシャ)は16世紀頃室町時代からあったそうですが、本格的に広く普及するのは、500年も後の1960年以降でした。
平安時代
牛蒡(ごぼう)や辣韮(らっきょう)は、平安時代に中国から渡ってきたとされていますが、どちらも中国では薬用に使われています。牛蒡を食用するのは世界中でも日本だけだといわれています。じゃがいも、人参、さつまいもは、戦国時代から江戸時代の間に渡来したそうです。
室町時代~江戸時代
法蓮草(ほうれんそう)、唐辛子、緑豆(りょくとう)、いんげん・えんどう・そら豆といった豆類なども室町時代から江戸時代の初期にかけて渡来しています。江戸時代の中後期になると苺(いちご)、トマト、アスパラガスなどが入ってきます。
明治時代
明治時代になると、ピーマンやアーチチョーク・セージ・タイムなどの西洋ハーブ類も入ってきます。玉ねぎも渡来したのは、この時期です。紀元前から中央アジアで栽培されていましたが、日本に入ってきたのは明治時代以降で、比較的新しい野菜と言えます。
日本への定着
海外から渡来した野菜は時の流れにともない日本各地に広がり、それぞれの土地の気候・風土に適応した品種や系統に分化していきました。各地に根を下ろし、長年にわたって栽培されてきた品種は在来種と呼ばれます。在来種の中でも、何世代もかけて選抜淘汰を行い、その地域の気候風土に合った種として、形質が固定化したものは固定種と呼ばれます。
伝統野菜や地野菜(地方野菜・地域野菜)は、この固定種を指すことがほとんどです。

時代ごとに変化する種子の有り様
在来種、固定種の時代
在来種や固定種は、自然淘汰によって生まれた品種、または昔から普通に行われてきた母本選抜による育種交配による品種です。その中でも長い時間をかけて形質が固定化した固定種の場合、次世代の野菜も親と同じ形質を持っています。
そして、その野菜からは種が採れ、その種を翌年に撒けば、また親と同じ形質を持つ野菜が育ちます。近代になるまでの長い間、農産者は採種用の野菜も栽培し、その種を翌年に撒い、野菜をつくるということをしてきました。
F1種の出現
その後、時代とともに、形や大きさが揃っていて、育てやすい野菜が求められるようになっていきました。そこで、人為的にかけ合わせ、良いとこ取りをした種子が数多くの品種でつくられるようになりました。その種子はF1種(一代雑種)と呼ばれています。F1種は、簡単に言えば、いわゆる「かけ合わせ」であり、遺伝子組み換え処理とは異なります。食味や環境適応などの改善がしやすく収穫量も見込めるため、農作物の種子として広く普及しています。
F1種の普及
F1種は、その形質や安定的に収穫量が得られるというメリットから、あっという間に普及していきました。種苗会社も、より食味の良いものや環境に強い品種の開発に力を入れています。F1種は、経済的な合理性においても効率が良く、消費者のニーズにも適合しているため、普及が拡大するのも当然です。また、そのおかげで豊かな食生活がおくれている面もたぶんにあります。
F2世代目は不安定
ただし、F1種の野菜の場合、その種子から翌年同じような野菜ができるとは限りません。
その理由は(小学校で習ったメンデルの法則思い出していただきたいのですが)、かけ合わせ同士の種子では、何世代も前の遺伝形質が出てくる可能性があり、安定した品質の野菜の定量の収穫が期待できないためです。F1種は一世代に限り、安定した形質と収穫量が得られるのです。そのため農産者は毎年、種苗会社からF1種の種子を購入し野菜を栽培することになります。
種子自給率の低下
F1種を利用することについては合理性があるのですが、問題は国内の種子自給率が低下し、現在は10%程しかないことです。農林水産省が2017年10月31日に発行した「国際的な食料需給の動向と我が国の食料供給への影響(P43)」の記述によると、F1種の生産は海外が主で、日本国内で流通している野菜の種の90%は種苗会社の海外圃場で生産されているそうです。その理由としては異常気象などの自然災害へのリスクヘッジや原産地と似た気候で育てるためだとしています。確かに、これまで見てきたように日本の野菜はそのほとんどが渡来したものであり、原産国は海外です。また、異常気象が続く昨今、自然災害におけるリスクヘッジも必要でしょう。だからといって野菜の種子自給率10%は低すぎるのではないでしょうか。
生物多様性保全の課題
さらに問題なのは、F1種の普及によって在来種や固定種の数が激減してしまい多様性が低下していることです。長い歴史を経て日本に定着し、毎年、採種されて長い間守り継がれてきた在来種、固定種は、今では国内で流通する野菜の1%にも満たない流通量と言われています。近頃、伝統野菜という位置づけで地域活性化の資源として見直されてきている在来種、固定種には、育種素材としての価値、遺伝資源としての価値があります。種を保全しておくことの重要性を考慮し、種を守っていくためににはどうすれば良いか、何をすれば良いかを消費者である私たちが積極的に考えていかなければならない時に来ています。
監修 高木幹夫