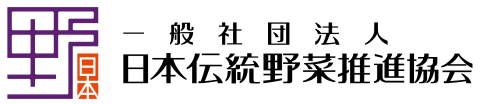世界の種子自給率の現状と戦略的展望 2026
第1章 種子自給率をめぐる世界的潮流
世界の食料情勢は大きな転換点を迎えています。ウクライナ情勢の長期化、異常気象の常態化、そして地政学的な貿易摩擦。こうした中、いま世界が最も注視しているのは「食料」そのものではなく、その源である「種子(たね)」です。
今回の記事では、世界各国の種子自給戦略と、私たちが知っておくべき日本の現状について解説します。
1.なぜいま「種子自給」が叫ばれるのか?
かつて種子は、農家が自分で採り、地域で分かち合うものでした。
しかし、現在、世界の種子市場の約6割は、わずか4社(バイエル、コルテバ、シンジェンタ、BASF)の多国籍企業が占めています。この寡占状態が、種子価格の高騰や多様性の喪失を招いているという懸念があり、多くの国が自国の安全保障を守るために動き出しています。
種子の自給率は、多くの国で「食料安全保障(フードセキュリティ)」の核心として位置づけられています。特に近年は、気候変動や地政学的なリスク(紛争、物流網の分断)の高まりを受け、多くの国が、種子の囲い込みや自国内での生産強化に動いています。
「種子自給率」は、今や単なる農業の指標ではなく、「国家の生存戦略」に直結する課題となっています。世界的には、食料自給率が高い国でも種子の生産を特定の地域に委託しているケースが多く、「種子自給率」という統計は、農業全体の自給率とは別に議論されます。
日本のような資源の乏しい国にとっては、種子の生産において、コストパフォーマンスを求めた「海外生産」とリスク回避のための「国内生産」のバランスをどう取り直すかが2026年以降の大きな焦点となるでしょう。
また、世界的なトレンドとして「種子主権(Seed Sovereignty)」という考え方が広がっています。これは、単に自給率を上げるだけでなく、「誰が種子を所有し、管理するか」という問題です。
例えば、気候変動に対応するため、その土地の環境に強い「在来種」を守り、農家が自由に種を採り、交換できる権利を保障する動きが、アフリカやアジアの途上国を中心に強まっています。
各国は自国の強みを活かし、異なるアプローチで自給率向上を目指しています。
本稿では、種子に対する世界的な潮流と、主要な国・地域における種子の国家戦略をまとめました。
(1) 食料自給率と種子自給率の相関関係
一般的に語られる「食料自給率」は、国内で消費される食品が、国内でどの程度生産されたかを示す指標です。しかし、その農作物を育てるための「種子」が海外依存であれば、その自給率は「砂上の楼閣(さじょうのろうかく)」に等しいと言えます。
➀「真の自給率」の考え方
農林水産省が公表する指標でも、種子を海外に依存している場合、その種子から作られた農作物の自給率は本来差し引いて考えるべきという議論があります。例えば、日本における野菜の食料自給率は約75%(生産額ベース)ですが、その種子の約9割を海外生産に依存しているため、種子まで遡った「真の自給率」は極めて低くなるのが実態です。
② 輸入途絶のリスク
パンデミック、紛争、あるいは気候変動による採種地の不作などにより種子の供給が止まれば、国内にどれだけ広大な農地や高度な技術があっても、生産そのものがスタートできません。
(2) 農業生産における「上流工程」としての種子の価値
製造業における半導体や設計図と同様に、農業における種子はすべての付加価値の源泉となる「最上流工程」に位置付けられるべきものです。
そのため、種子自給率は、単に「種を国内で作る」という物理的な問題だけにとどまるものではありません。農業生産の根っこの部分である種を保有するということは、「生存の権利(種子主権)」と「経済的優位性」を得ることにつながります。
➀生存の権利(種子主権): 自国の食料生産の生殺与奪の権を他国や多国籍企業に委ねないこと。
②経済的優位性: 優れた遺伝資源(種)を保有することで、国際市場での農業競争力を維持すること。
現代の農業分野における種子の価値は、「遺伝資源の独占」、「技術のパッケージ化」、「付加価値の源泉」という農産物の生産における強固な基盤を構築し、市場における主導権を握るキーエレメントになりつつあります。
| 価値の側面 | 内容 |
| 遺伝資源の独占 | 特定の気候や病害虫に強い「品種」そのものが知的財産(IP)であり、種子を握ることは、その後の生産流通プロセスの主導権を握ることを意味します。 |
| 技術のパッケージ化 | 現代の種子は、農薬や肥料、精密農業技術とセットで開発される「システム」となっています。種子を供給する企業が、農業のやり方そのものを決定する影響力を持ちます。 |
| 付加価値の源泉 | 高糖度のトマトや機能性野菜など、消費者のニーズに応える差別化の源泉は、栽培技術以上に「種子のDNA」に依存する割合が高まっています。 |
その「生存の権利(種子主権)」と「経済的優位性」を得ることが、各国が巨額の予算を投じて種子の自給・管理を強化している本質的な理由です。
2.グローバルな種子市場の構造
(1) 市場の独占化:種子メジャーの支配
世界の商業用種子市場は、数回の巨大な合併・買収(M&A)を経て、現在は「ビッグ4」と呼ばれる多国籍企業が市場の約6割近くを支配しています。これにより、種子の価格決定権や開発の方向性が少数の企業に集中しています。
| 企業名(本社) | 主要な特徴と動向(2024-2025年) |
| バイエル (独) | 旧モンサントを買収し、世界シェア1位(約20-23%)。遺伝子組み換え(GM)作物に強く、デジタル農業プラットフォームとの連携を加速。 |
| コルテバ (米) | ダウとデュポンの農業部門が統合。トウモロコシや大豆の種子に強みを持ち、微生物資材などのバイオソリューションを強化。 |
| シンジェンタ (中/瑞) | 中国化工(ケムチャイナ)傘下。アジア市場への支配力を強めており、インドや東南アジアに最新の種子研究所を相次いで設立。 |
| BASF (独) | 農薬大手から種子事業へ本格参入。気候変動に対応した耐性品種(乾燥・病害耐性)のポートフォリオを拡大中。 |
注記: 日本のサカタのタネやタキイ種苗は、野菜種子の特定分野(ブロッコリーやトマト等)で世界トップクラスのシェアを誇りますが、穀物を含む市場全体では「中堅(ニッチトップ)」という立ち位置になります。
(2)技術のパッケージ化と知財戦略
現代の種子ビジネスは、単に「種」を売るだけでなく、以下の要素をセットにした「プラットフォーム販売」へと移行しています。
➀ 農薬・肥料とのセット販売
特定の除草剤に耐性を持つ種子を販売することで、農薬と種子の両方で収益を上げるモデル。
② 知的財産権(PVP・特許)の強化
20年間の育成者権保護に加え、近年は「自家採種(農家が収穫物から翌年用の種を確保すること)」を制限する契約や法的枠組みが 国際的に強まっています。
③ 精密農業(デジタル)との融合
土壌データや気象予測に基づき、最適な種子の種類や播種(種まき)密度をAIが指示するシステムを提供し、農家を自社システムへ囲い込んでいます。
(3) 近年のトレンド:気候変動とデジタル革新
2025年現在の市場では、以下の3点が大きな原動力となっています。
➀ 環境ストレス耐性
異常気象(干ばつ、塩害、高温)に耐える品種の需要が激増。
② ゲノム編集(CRISPRなど)
従来の品種改良(10年以上)に比べ、数年で新品種を開発できる技術への投資が集中。
③ 植物ベース食品への対応
高タンパクな大豆や、加工適性の高い穀物など、代替肉市場をターゲットにした種子開発が進行。
(4)なぜ種子自給率が問題になるのか
この構造下では、大手種子企業の経営判断一つで、特定の種子の供給停止や価格高騰が起こり得ます。「種子の知的財産」と「デジタル技術」を他国に握られることは、その国の農業のコストと手法を他国に決定されることと同義です。そうならないよう各国は種子自給率の維持・向上に躍起になっているのです。
3.近年の世界的トレンド
2025年現在、種子をめぐる状況は、単なる「農業資材」の枠を超え、テクノロジーと国家安全保障が交差する最前線となっています。
(1) 気候変動に対応する「耐性品種」の開発競争
異常気象の常態化(極端な乾燥、高温、洪水、塩害)により、従来の品種では収穫が安定しなくなっています。現在、種子市場で最も成長しているのは、過酷な環境下でも一定の収穫を約束する「気候適応型種子(Climate-Resilient Seeds)」の分野です。
➀ 乾燥耐性・高温耐性
水不足でも枯れにくいトウモロコシや、酷暑でも品質が落ちない米の開発。
② 遺伝的保険
農家にとって、耐性品種の導入は「気候リスクに対する保険」としての意味合いが強まっており、多少高価でもこれらの種子を選ぶ傾向が加速しています。
③ 市場規模
乾燥耐性種子の市場は2034年までに約90億ドル規模に達すると予測されており、主要企業のR&D投資の最優先事項となっています。
(2) デジタル農業とゲノム編集技術による種子革新
「種子」そのものの設計図を書き換えるスピードが劇的に向上しています。
➀ ゲノム編集(CRISPR等)の普及
従来の品種改良(交配)には10〜15年を要していましたが、ゲノム編集技術により、わずか数年での開発が可能になりました。特に、外部から遺伝子を入れる「遺伝子組み換え(GMO)」とは異なり、その植物自身の遺伝子を微調整する手法(ゲノム編集、ターゲット育種、プロモーター編集など)は、一部の国(米国・日本等)で規制が緩和され、市場投入のハードルが下がっています。
② スマート育種(AI×デジタルツイン)
「デジタルツイン(仮想農場)」を用いて、数十万通りの遺伝子組み合わせをシミュレーションし、最適な個体をAIが特定します。これにより、研究室で「成功が約束された種」を作ってから圃場試験を行う、超効率的な育種が実現しています。
(3) パンデミックや地政学的リスクを受けた「種子安全保障」への回帰
コロナ禍やロシア・ウクライナ紛争などにより、グローバルなサプライチェーンの脆弱性が露呈したことで、多くの国が「種子の国内確保」を国家戦略に格上げしています。
➀ 「食料の武器化」への警戒
ロシア・ウクライナ紛争や米中貿易摩擦などの地政学的緊張により、種子や肥料の供給が政治的交渉のカードとして使われるリスクが顕在化しました。
② 戦略的備蓄と国内回帰
中国のように、海外依存を脱却するために「種子振興計画」を掲げ、自国企業による海外企業の買収や国内生産拠点(シードシリコンバレー)の整備を強硬に進める動きが目立ちます。
③ コミュニティ・シードバンクの再評価
大規模な商業用種子だけでなく、地域固有の在来種を保存し、不測の事態に備える「草の根の種子保存」も、多様性維持の観点から国際的に支援されています。
現在のトレンドを一言で言えば、「テクノロジーによる開発スピードの極大化」と「物理的な確保(自給)へのこだわり」の同時進行です。種子はもはや単なる農産物の一部ではなく、国家が管理すべき「戦略的IP(知的財産)」としての性格を強めています。
第2章 種子知財と技術革新による「種子安全保障」の再構築
気候変動による栽培適地の激変に直面する現代、環境に適応した品種をいかに迅速に開発するかが国家の死活問題となっています。しかし、ここには大きなジレンマが存在します。最先端技術を用いた育種には巨額の投資が必要であり、その権利を保護する制度(知的財産権)は不可欠ですが、保護を強めるほど、農家が種子に自由にアクセスできる権利が制限されてしまうのです。その仕組みとジレンマについてみていきます。
1.知的財産権(PVP/特許)と種子アクセスの対立
国や企業が種子を囲い込み、最先端の技術で気候変動などに適応する品種を開発する中、その育種権を保護する制度は重要です。現在、種子の知財保護には、大きく分けてPVP(植物新品種保護)と特許の2つの仕組みがあります。しかし、これらが強化されるほど、農家が自由に種を使える範囲(種子アクセス)が制限されるというジレンマが生じています。
(1)2つの保護制度とその違い
現代において、気候変動に適応する品種開発には多額の投資が必要であり、その権利を保護する制度は不可欠です。現在、主に2つの仕組みが国際標準となっています。
➀ PVP(Plant Variety Protection/植物新品種保護)
UPOV条約に基づき、新品種の「品種そのもの」を保護する制度です。通常、「育種家特例(他者がその品種を親に使って新種を作ってよい)」が認められていますが、最新のUPOV1991年条約では、育成者の権利が強化され、販売・輸出入の独占に加え、農家が収穫物から翌年の種を採る「自家採種」も原則として育成者の許諾が必要となり、制限が強まっています。
② 特許(Patents)
特許は、主に米国などで強い制度です。遺伝子配列や特定の技術、形質そのものに与えられます。PVPよりも保護が強力で、他者がその遺伝子を研究に使うことさえ制限される場合があります。
(2)種子アクセス対立の主な論点
知財権の強化は投資を促す一方で、農家や利用側の「シードアクセス(種子の入手可能性)」と対立する局面を生んでいます。
対立するポイントは、以下の3つにまとめることができます。
➀自家採種の制限
企業の「投資回収の正当性」に対し、農家側は「数千年の伝統と経済的自立の侵害」を主張しています。
②育種家特例の縮小
微細な修正による「ただ乗り」を防ぎたい企業に対し、農家側は「地域の気候に合わせた改良の自由(研究の自由)」が失われると危惧しています。
③バイオパイラシー
先端技術による特許化を、在来種の知恵を無断で奪う「生物海賊行為」と捉える対立です。
知財権が強すぎれば、農家は特定の企業に依存せざるを得ず、種子の「アクセス価格」が高騰します。一方で、知財保護が弱すぎれば、新しい耐性品種の開発投資が止まってしまいます。
| 論点 | 知財権の主張(企業側) | シードアクセスの主張(農家・NGO側) |
| 自家採種の制限 | 研究開発には巨額の投資(1品種10億円以上)が必要。毎年購入してもらわないと次なる革新に投資できない。 | 数千年にわたり農家は種を採り続けてきた。種子を毎年買わされることは、農家の経済的自立を奪う「隷属」である。 |
| 育種家特例の縮小 | 既存の品種に微細な修正を加えただけの「実質的に派生した品種(EDV)」による利益のただ乗りを防ぐ必要がある。 | 誰かの開発した品種をベースに、地域の気候に合わせて改良する自由(研究の自由)が奪われ、多様性が失われる。 |
| バイオパイラシー | 先端技術を用いて有用な性質を特定し、特許化することは正当な経済活動である。 | 途上国の先住民が古くから守ってきた在来種の性質を、企業が無断で特許化するのは「生物海賊行為」である。 |
2.2025年現在の国際的な調整と新モデル
この対立を解消・調整するため、2025年現在、新たな国際ルールやモデルが機能し始めています。
(1) 「農民の権利」の国際条約(ITPGRFA)
食料農業植物遺伝資源条約(通称:種子条約)では、農家が種子を保存・交換する権利を認めつつ、企業が遺伝資源を利用して得た利益を基金に還元し、途上国の農業支援に充てる「利益配分」の仕組みを運用しています。
(2) オープンソース・シード
ITのオープンソースになぞらえ、「この種子から作られた品種もまた、自由に利用可能でなければならない」ことを条件としたライセンス(OSSI等)を付与した種子が登場し、独占に抗う新しいモデルとなっています。
(3) ゲノム情報のデジタル化(DSI)
実物の種子ではなく、デジタル化された「遺伝子情報(DSI)」がネットでやり取りされるようになり、これをどう規制・課金するかが、2025年の生物多様性条約(COP16以降)での最大の争点となっています。
3.育種技術の進化(スピード勝負の時代へ)
知財を巡る議論が進む一方で、技術はこれまでの育種の常識を覆す進化を遂げています。この育種技術の効率が向上することによって、米国や日本に加え、EUやインド、中国でもゲノム編集作物に対する規制緩和が進み、商業栽培に向けたハードルが大きく下がっています。気候変動によって栽培適地が激変する中、種子自給の鍵は「いかに早く、環境に適応した品種を作るか」というスピード勝負になっています。
-
ゲノム編集(CRISPR/Cas9等)⇒ 従来の交配育種(10〜15年)を3〜5年にまで短縮。
従来の交配による育種が10〜15年かかっていたのに対し、特定の遺伝子をピンポイントで編集するこの技術は、開発期間を3〜5年程度にまで短縮することを可能にしました。 -
スマート育種とデジタルツイン⇒ AIが膨大なデータから最適な遺伝子の組み合わせを予測し、仮想空間の農場(デジタルツイン)で性能をシミュレートすることで、実際に育てる前の段階でプロセスの効率化を実現。
数千から数万通りの遺伝子配列データと、ドローンやセンサーで得られた生育データをAIが解析し、最適な組み合わせを予測する「ハイスループット・フェノタイピング」が普及しています。また、実際に育ててみる前に、コンピューター上の「デジタルツイン(仮想農場)」で品種の性能を予測できるため、育種プロセスの効率が劇的に向上しています。
4.「持続可能な種子システム」の構築と自給率への影響
真の自給率向上のためには、大手企業による「フォーマルな供給」と、地域に根ざした「インフォーマルな供給」の共生ができるようなシステムの構築が必要です。
➀ デジタル・トレーサビリティ⇒ブロックチェーンを活用し、種子の流通や権利関係を透明化することで、偽造排除と権利保護を両立。
ブロックチェーン技術を用いて、種子の生産地から流通経路、遺伝子情報を一貫して管理する動きです。偽造種子の排除や、ブランド品種の権利保護をデジタルで完結させることで、国内種子市場の健全性を高めています。
② コミュニティ・シードバンクの法的位置づけ⇒気候変動に対する「多様性の保険」
気候変動に対する「多様性の保険」として地域の在来種を保存する小規模なシードバンクを国家の種子戦略の中に公式に組み込む動き(エチオピアやインド等)が見られます。在来種は知財に縛られない持続可能な種子ですが、「栽培の難しさ」「不揃いによる機械・物流への不適合」「収益性の低さ」といった現代農業における弱点も抱えています。これらをコミュニティ・シードバンク等で公式に保護し、多様性の「保険」として維持することが重要です。
5.真の種子自給率とは
「真の自給」とは、単に種子が国内にあることではありません。「持続可能なコストで、かつ法的リスクなく、将来にわたって種子を使い続けられる権利」を確保することであると言えます。この点からみれば、在来種は全ての条件を満たした持続可能な種子であると言えますが、栽培に技術が必要なことと、生産された農作物の揃いが悪いことで機械への適応がしにくかったり、物流コストが上昇したり、消費者の請け入れが悪いなどが問題となります。
2025年現在の世界的なトレンドは、「法的に守られた権利(UPOV)」を、「圧倒的なスピード(ゲノム編集・AI)」で実現し、「デジタル(トレーサビリティ)」で管理するという、高度に情報化された種子システムへの移行が進んでいます。このシステムを自国でコントロールできるかどうかが、真の種子自給率を決定づけています。
-
法的基盤:UPOV等に基づき、開発者の権利を守りつつ、在来種やシードバンクを「多様性の保険」として公式に保護する。
-
技術基盤:ゲノム編集やAIを駆使し、圧倒的なスピードで適応種を生み出す。
-
デジタル基盤:ブロックチェーン等のトレーサビリティで、偽造排除と権利保護を完結させる。
持続可能なコストで、かつ法的リスクなく将来にわたって種子を使い続けられる権利の確保こそが、国家の安全保障としての「真の自給」に繋がります。
第3章 主要国の種子自給状況と政策方針
ここからは、主要各国の種子の自給状況と政策方針を見ていきます。
注目ポイント
1.日本:野菜種子の「実質自給」への転換
日本は、品種開発(育種)能力は高いものの、実際の「採種」を海外に頼っています。2025年現在は、有事の際に国内で即座に増殖できるよう「遺伝資源の国内バックアップ」と「スマート採種(完全密閉型施設)」への投資を強化しています。
2.中国:驚異的なスピードでの「国産化」
中国は、2020年時点ではブロッコリーやトマトの種子を日本や欧州に依存していましたが、2025年11月の発表では、国産品種の市場シェアが野菜全体で91%にまで上昇しました。ゲノム編集技術の緩和と国家予算の集中投下が功を奏しています。
3.ロシア:制裁を逆手に取った「自立」
ロシアは、2025年に「非友好的な国」からの種子輸入枠(クォータ)をさらに削減しました。ジャガイモやテンサイなど、これまで欧米に頼り切っていた品目でも、国産種子を使わない農家には補助金を出さないなど、極めて強硬な手段で自給率を底上げしています。
4.チリ:世界を支える採種基地
チリは、自国の種子自給率というよりも世界の種子生産を担っており、「チリが止まると世界の野菜種子流通が止まる」と言われるほどの影響力を持っています。日本にとっても、チリは最大の野菜種子供給源であり、このサプライチェーンの維持が安全保障上の生命線となっています。
5.主要各国の穀物と野菜の種子自給率
以下は、主要各国の穀物と野菜の種子自給率です。
| 国・地域 | 種子自給率 | 特徴・戦略の方向性 | |
| 穀物 | 野菜 | ||
| 日本 | ほぼ100% | 約8〜10% | 主要穀物は盤石だが、野菜種子の9割をチリやイタリア等に依存。国内採種プラントの整備を急いでいる。 |
| アメリカ | 100% | 100% | 世界最大の種子輸出国。知財(特許)とハイテク育種で世界の農業のオペレーションシステムを支配する戦略。 |
| フランス | 100% | 100% | EU最大の農業国。種子輸出も世界トップクラス。伝統品種の保護と先端技術を両立。 |
| オランダ | 100% | 100% | 野菜育種の世界拠点。面積は狭いが、施設園芸向け種子の世界シェアが極めて高い。 |
| チリ | 高い | 輸出拠点 | 自国の消費用というより、世界中の野菜種子を生産する「世界の農場」。南半球の気候を活かした受託生産。 |
| 中国 | 95%以上 | 91% | 種を「農業のチップ(半導体)」として国産化を猛推。2025年に野菜種子自給率が9割を超え、輸入から輸出へ転換中。 |
| インド | 100% | 高い | 米・小麦は完全自給。豆類・油糧種子の自給が2025年の最優先課題(自立したインド戦略)。 |
| アフリカ | 上昇中 | 低い | ジンバブエ等は穀物自給を達成。野菜は外資依存が強いが、農民による「在来種管理」で主権回復を狙う。 |
| ロシア | ほぼ100% | 約40〜60% | 2030年までに全種子自給率75%が目標。欧米からの輸入制限を強行し、国産化を強制。 |
1.日本:高い海外依存度と法的転換
(1) 野菜種子の海外生産依存(約9割)の実態と理由
日本は水稲の採種自給率は、ほぼ100%ですが、野菜種子の自給率は、数量ベースでわずか10%程度に留まっています。残りの9割は海外で生産されていますが、これには日本の地理的・経済的な構造上の理由があります。
➀ 採種適地の不在
種子を採る(採種)には、受粉時期に雨が少なく乾燥していることや、交雑を防ぐための広大な隔離圃場が必要です。多湿で農地が狭小な日本では、高品質な種子を大量に安定生産することが困難です。
② コスト競争力
種子の生産には多くの手作業(除草や授粉など)を要するため、労働コストの低い国や、機械化が進んだ広大な土地を持つ国(イタリア、チリ、中国など)に生産拠点を移転させてきました。
③ 「海外生産、国内供給」モデル
日本の種子メーカーは「研究・品種開発(R&D)」を国内で行い、その設計図をもとに海外の農場に生産を委託し、完成した種子を日本に逆輸入する形態をとっています。そのため、「日本で開発された品種か(品種自給率)」と「日本でタネを採っているか(採種自給率)」の使い分けが重要になってきます。
(2) 種子法廃止と種苗法改正(2020年〜)の狙い
2018年の「主要農作物種子法」の廃止、および2020年の「種苗法改正(2022年4月全面施行)」は、日本の種子政策の大きな転換点となりました。
➀ 民間参入の促進
種子法の廃止により、それまで都道府県が主導していたコメ・麦・大豆の種子開発に民間の創意工夫を促し、多様なニーズ(業務用、多収量など)に応える品種を増やすことが狙いとされました。
② 知財保護の強化(種苗法改正)
日本で開発された「シャインマスカット」が海外に流出し、第三国で無断増殖される事態が発生しました。また、「あまおう」のように品種登録(育成者権)が切れた品種は、苗の流出や無断栽培のリスクが高まります。これを防ぐため、「登録品種」の海外持ち出し制限や、農家による自家増殖の許諾制が導入されました。
③ 2025年現在の状況
改正法の施行を受け、各産地では「栽培地域指定」を活用してブランドを守る動きが加速しています。その一方で、育成者(開発者)の権利と、生産現場のコスト負担のバランスが継続的な課題となっています。
(3) 「みどりの食料システム戦略」と種子安全保障
2025年現在、政府は「環境」と「安全保障」の両面から種子確保の方針を強化しています。
➀ 気候変動・環境負荷への対応
2050年までに有機農業の割合を25%に拡大する目標に向け、化学農薬や肥料を減らしても育つ「抵抗性品種」や「有機農業適応品種」の開発が急務となっています。
② 種子安全保障の強化
2025年4月施行の「食料供給困難事態対策法」などの文脈において、有事の際に海外からの種子供給が途絶するリスクが再認識されています。これに基づき、気候の影響を受けにくい北海道や、隔離栽培が可能な離島などで、野菜種子の国内採種を復活させる事業を推進しています。
③ 国内生産体制の再整備
完全に国内に戻すことは難しくとも、特定の国に依存しすぎない「サプライチェーンの多角化」や、国内での戦略的な採種拠点の維持・支援を進めつつあります。
(4)日本の課題
日本の強みは「高度な品種改良能力(R&D)」にありますが、弱みは「生産の海外依存」と「知財の流出リスク」にあります。2025年以降の日本は、「優れた種を作る力(技術)」と「作った種を管理する力(法・知財)」の両輪で、種子安全保障を再構築する段階にあります。
2.アメリカ:民間主導の技術革新と強力な知財保護
アメリカは世界最大の種子輸出国であり、その戦略は「自給」という概念を超え、テクノロジーによる「グローバル・スタンダードの支配」と「徹底した知的財産(IP)の保護」に集約されています。
(1) バイオテクノロジーの社会実装と規制緩和
アメリカは、ゲノム編集(CRISPR等)を気候変動に対策する農作物生産の切り札に位置づけています。
➀ 規制の最適化
USDA(米国農務省)は、従来の遺伝子組み換え(GMO)とは異なり、自然界での変異の範囲内とされるゲノム編集作物について、審査プロセスを大幅に簡略化しました。これにより、スタートアップ企業でも短期間・低コストで新種を市場投入できる環境を整えています。
② 気候適応型品種の開発
極端な乾燥や熱波に耐える「気候回復力(Climate Resilience)」を備えたトウモロコシや大豆の開発を、民間企業が競い合っています。
(2) 強力な知的財産権(IP)戦略
「種子は発明品である」という考え方が徹底されており、法制度によって開発者の権利が強く守られています。
➀ 特許による独占
植物特許(Plant Patent)や実用特許(Utility Patent)を活用し、他者による無断の増殖や研究利用を厳しく制限しています。これにより、莫大な研究開発費を回収し、さらなる投資につなげるサイクルを確立しています。
② 「種子+デジタル」のパッケージ販売
巨大アグリビジネス(バイエル、コルテバ等)は、種子、農薬、そしてAIによる栽培指示データをセットで提供するプラットフォームを展開。農家をプラットフォーム内に囲い込むことで、種子の市場シェアを確固たるものにしています。
(3) 輸出拠点としての「種子安全保障」
アメリカにとっての種子安全保障とは、自国の供給能力を維持し、世界の食料システムの上流を握り続けることです。
世界への影響力
中南米やアジア、アフリカ諸国に対して、自国の知的財産基準やバイオ技術を受け入れさせることで、米国の種子が世界中で「標準」として使われる構造を維持しています。
3.フランス・オランダ:EU最大の種子生産拠点としての輸出戦略と基準化
欧州における種子戦略は、フランスとオランダという2つの「種子大国」が牽引しています。両国は単なる「自給」を超え、EU全体の農法や品質基準を策定・主導することで、世界市場での覇権を維持する「基準(スタンダード)輸出戦略」をとっています。
(1) フランス:世界最大の種子輸出国としての「競争力と多様性」
フランスは世界最大の種子輸出国であり、その戦略は「高付加価値化」と「官民一体の推進体制」に支えられています。
➀ SEMAE(フランス種子種苗産業連合会)の役割
2027年に向けた戦略「Horizon 2027」を掲げ、種子産業の国際競争力強化、気候変動対策、生物多様性の保護を一体化させています。
② 植物タンパク質の自給強化
ロシア・ウクライナ紛争以降、家畜飼料の海外依存(大豆等)を減らすため、マメ科植物(豆類)の種子開発・増産に多額の予算を投じ、国内自給率を劇的に引き上げています。
③ オーガニック種子の拡大
「Farm to Fork(農場から食卓まで)」戦略に基づき、2027年までに有機農業面積を18%まで拡大する目標を掲げ、それに適した無農薬・耐病性品種の開発をリードしています。その戦略の中で、生物多様性の維持を掲げる。伝統的な農家による種子交換を認める法改正を検討するなど、多様性確保と産業競争力の両立を目指しています。
(2) オランダ:世界の「種子のシリコンバレー」とハイテク輸出
オランダは、狭い国土ながら野菜種子と花の種苗で世界圧倒的トップのシェアを誇ります。
➀ 「シード・バレー(Seed Valley)」
北ホラント州に集積する高度な育種企業群が、AI、ドローン、衛星データを駆使した「精密育種」を展開。2025年現在、ブロックチェーンを用いた種子のトレーサビリティ(生産履歴管理)を導入し、ブランド価値を高めています。
② 環境制御農業への特化
グリーンハウス(温室)や垂直農業に最適化された種子の開発に強みを持ち、施設の設計・システムとセットで世界に輸出する「トータルソリューション」を展開しています。
(3) EU共通の動向:新ゲノム技術(NGT)と基準化
➀ 新ゲノム技術(NGT)への転換
2024〜2025年にかけて、EUはゲノム編集(NGT)作物を従来の厳格なGMO(遺伝子組み換え)規制から分離し、緩和する方向で法整備を進めています。これにより、フランスやオランダの先進技術が商業化しやすくなる見通しです。
② NAL(Naktuinbouw Authorized Laboratories)基準
オランダの検査機関「Naktuinbouw」が策定した品質基準(NAL)は、事実上の世界標準となっており、これに準拠することが国際取引のパスポートとなっています。
| 国名 | 得意分野 | 戦略の核心 |
| フランス | 穀物(トウモロコシ、小麦)、豆類 | 官民連携による輸出促進とタンパク質自給 |
| オランダ | 野菜、花卉、ハイテク温室用種子 | 育種テックの集積と品質基準の国際化 |
4. チリ:世界の「種子増殖基地」としての役割
チリは、自国で品種を開発して売るというよりも、世界中の種子企業から依頼を受けて種を増やす「世界の種子工場(増殖拠点)」として、極めて特殊かつ重要な地位を築いています。北半球のオフシーズン生産を支える受託生産モデルと自給率の考え方を見ていきます。
(1)北半球のオフシーズン生産を支える「逆サイクル」モデル
チリの最大の強みは、南半球に位置し、かつ安定した地中海性気候を持つことです。
➀ 開発スピードの倍速化
北半球(欧米、日本等)が冬の間、チリは夏になります。北半球で開発された新品種をチリに持ち込んで冬の間に増殖させることで、通常なら1年かかる育種サイクルを半年(1年に2回収穫)に短縮できます。
② リスク分散
北半球での不作や気候災害に備え、種子メジャーは「バックアップ」としてチリで種子を生産・備蓄します。
(2)高度な受託生産(アウトソーシング)体制
チリは、世界で栽培されているトウモロコシ、大豆、キャノーラのほぼすべての品種が、研究開発や増殖の過程で一度はチリの地を踏んでいると言われるほどの集積地です。
➀ バイオ技術のハブ
2025年現在、チリは遺伝子組み換え(GM)作物やゲノム編集作物の研究・増殖・輸出専用の特区のような役割を担っています。国内での商業栽培(食糧用)は制限しつつ、輸出用としての生産は高度な管理体制のもとで認められており、世界のバイオ種子供給の生命線となっています。
② 専門性と品質
熟練した労働力による手作業の授粉(ハイブリッド種子の作成)や、AI・画像認識技術を用いた品質管理デバイスの開発など、増殖プロセスの高度化が進んでいます。
(3)チリから見る「自給率」の特異な考え方
チリの事例は、種子自給率を考える上で一つの重要な視点を与えてくれます。
➀ 「生産額」と「供給権」
チリの種子自給率(生産ベース)は極めて高いですが、その知的財産権の多くは外資企業にあります。つまり、「自国で種を生産できる能力(技術・土地・気候)」はあっても、「何を植えるかを決める権利(知財)」はグローバル市場に依存しているという構造です。
② 経済的安全保障
チリにとって種子は主要な輸出農産物(約4億ドル規模)であり、自国の食料自給よりも「世界の種子供給網に不可欠な存在になること」で経済的安全保障を確保する戦略をとっています。
(4)種子供給のプラットフォーム
チリは「自国の種を守る」という文脈ではなく、「世界の種子供給のプラットフォーム」となることで、農業大国としての地位を維持しています。これは、種子を自給できない国(日本など)が、いかにして冬場や緊急時の種子供給を確保しているかを理解する上で見逃せない点です。
5. 中国:国家主導による「種子の独立自強」戦略
中国は種子を、食料安全保障のみならず「国家の競争力を左右する核心的技術(農業のチップ/半導体)」と位置づけ、国家種子振興計画による「種子の自立自強」と海外企業の買収で、世界で最も野心的な種子自給戦略を展開しています。2025年現在、その成果は「国産化の加速」という形で明確に現れています。
(1)「種業振興計画」と種子の独立自強
習近平政権は「中国人の飯碗(茶碗)には中国の種を盛る」というスローガンのもと、海外依存からの脱却を強力に推進しています。
➀ 国産品種のシェア拡大
2025年の最新データ(中国農業農村部)によると、中国の主要作物の国産品種シェアは95%以上に達しています。特にトウモロコシは94%、野菜は91%を国産品種が占めるまでになりました。
② 中央1号文書(2025年)
毎年発表される最優先政策指針において、ゲノム編集や合成生物学を活用した「新たな質の生産力」の発展を強調。特定の気候や土壌(塩類集積地など)に強い品種の自給を加速させています。
| 分類 | 主要品目 | 自給率(2025年推計) | 状況 |
| 主食(完全自給) | 米、小麦 | ほぼ100% | 独自の品種育成が極めて進んでおり、中国国内の種子で完全に賄われています。 |
| 飼料・加工用(中程度) | トウモロコシ、大豆 | 約85〜95% | 自給率は高いものの、単収(面積あたりの収穫量)の高い海外品種に一部依存。近年、国産のゲノム編集・遺伝子組み換え種子での置き換えが加速しています。 |
| 野菜・果物(海外依存あり) | トマト、パプリカ、ブロッコリー等 | 約10〜50%(品目による) | 高付加価値な野菜の種子は、依然として日本、欧州、米国からの輸入に頼る部分が多いのが現状です。 |
(2)「南繁硅谷(種子シリコンバレー)」と研究開発体制
中国海南省にある「南繁硅谷(なんふぁんけいこく)」は、中国全土から12万人以上の研究者が集まる巨大な育種拠点で、「種子のシリコンバレー」と言われています。
➀ 通年育種
亜熱帯気候を利用し、1年に複数回の栽培・選別を行うことで、新品種の開発期間を大幅に短縮しています。
② AIとデジタル育種
スマート監視システム「慧眼(けいがん)」などを導入し、病害虫の早期発見や遺伝子情報の解析をAIで行う「精密育種」を国家レベルで標準化しています。
(3)バイオ技術の商業化と戦略的備蓄
長年、慎重だった遺伝子組み換え(GM)技術についても、2024〜2025年にかけて大きな転換を迎えました。
➀ GM作物の本格導入
トウモロコシや大豆のGM品種の商業栽培を本格化。これにより、これまで輸入に頼っていた飼料用穀物の自給率を底上げし、米中貿易摩擦などの地政学的リスクに備えています。
② 種子輸出の黒字化
2024年に種子の輸出額が輸入額を上回り、初めて貿易黒字を達成しました。ハイブリッド米や綿花の種子をアフリカやアジア諸国へ輸出することで、国際的な影響力も強めています。
(4)国家安全保障戦略としての種子戦略
中国の種子戦略は、単なる農業政策の枠を超え、「食料主権の確立」と「ハイテク覇権」を同時に追求する国家安全保障戦略そのものです。
6.インド:農民の権利と民間企業の投資促進のバランス政策
インドは世界第5位の種子市場(約38億ドル規模)を誇り、急増する人口を支えるための「生産性向上」と、小規模農家を保護する「社会正義」の間で、極めてユニークなバランス政策をとっています。
2025年現在、インドは半世紀前の古い法律を刷新する「2025年種子法(The Seeds Bill, 2025)」の導入期にあり、現代化と伝統維持のせめぎ合いの最前線にいます。
(1) 農民の権利:世界でも珍しい「自家採種」の強力な保護
インドの政策の根幹には、2001年に制定された「植物品種保護および農民の権利法(PPV&FR法)」があります。伝統的に「農家が種を保存する権利」が強く、「種子主権」の意識が高い国です。
➀ 伝統的な権利の成文化
農家が収穫物から種を保存し、再播種、交換、さらには近隣農家に販売すること(未ブランドに限る)を法律で明示的に認めています。これは、企業の知財権を優先する欧米のモデルとは一線を画す「インド・モデル」として知られています。
② 補償制度の導入
2025年種子法案では、種子会社が主張した性能(収穫量や耐性)が発揮されなかった場合、企業側が農家に補償を支払う仕組みが強化されています。
(2)民間企業の投資促進:ハイブリッド化とデジタル化
一方で、政府は農業の近代化には民間企業のR&D投資が不可欠であると認識しています。
➀ 「One Nation, One License」の推進
従来、州ごとに必要だった煩雑なライセンス登録を簡素化し、全インドで統一したデジタル登録システム(SATHIポータル)への移行を進めています。これにより、企業の事務コストを削減し、新品種の市場投入までのスピードを早めています。
② ハイブリッド種子の普及
穀物や野菜において、民間企業が得意とするハイブリッド種子の市場占有率が7割(2024年時点)を超えています。ハイブリッド種子は農家が毎年購入する必要があるため、企業にとっては投資回収がしやすく、結果として技術革新が進んでいます。
(3)2025年の最新動向:ゲノム編集と品質の厳格化
➀ ゲノム編集イネの承認
2025年、インド政府は国産技術によるゲノム編集イネ(特定の病害に強い品種)を承認しました。これにより、海外技術へのライセンス料支払いを抑えつつ、最先端技術を自給する路線を明確にしています。
② 品質基準の国際化
偽造種子や低品質種子の流通を防ぐため、すべての種子パッケージへのQRコード貼付を義務化。デジタル・トレーサビリティ(追跡可能性)を導入することで、農家の信頼を勝ち取ると同時に、優良な種子企業の市場を守る策を講じています。
(4) インドが示す「第3の道」
インドの戦略は、以下の2点を両立させる「ハイブリッドなアプローチ」です。
➀ インフォーマル・セクター(農民同士の種子交換)
地域の多様性と農家の経済的自立を守る。
② フォーマル・セクター(民間企業の種子ビジネス)
科学的な生産性向上と、気候変動への対応を担う。
7. アフリカ諸国:ハイブリッド種子導入と在来種の保存
アフリカ大陸の種子戦略は、爆発的な人口増加に対応するための「生産性の劇的向上」と、気候変動下での「レジリエンス(適応力)の維持」という2つの大きな課題の間で揺れ動いています。2025年現在、民間主導のハイブリッド種子普及と、コミュニティによる在来種保存の両立を目指す動きが加速しています。
(1) ハイブリッド種子の急速な普及と「種子革命」
サハラ以南のアフリカ(SSA)を中心に、収穫量を劇的に増やすためのハイブリッド種子の導入が進んでいます。
➀ 市場の成長
アフリカの種子市場は2025年に約31億ドル規模に達し、その約6割をトウモロコシや野菜などのハイブリッド種子が占めています。特に東部・南部アフリカ(ケニア、ザンビア、ジンバブエ等)では、民間企業(Seed Co等)による普及活動により、トウモロコシのハイブリッド利用率が高まっています。
② 気候スマート農業(CSA)
干ばつに強い「耐乾性トウモロコシ」などの改良品種が、国際機関(AATF等)の支援で導入されており、異常気象による飢饉を防ぐセーフティネットとしての役割を果たしています。
③ 課題(コストと依存)
ハイブリッド種子は毎年購入する必要があり、小規模農家にとっては経済的負担が重いのが現状です。ガーナなど一部の地域では、改善品種の採用率が依然として低く、伝統的な種子への依存が続いています。
(2) 在来種の保存と「コミュニティ・シードバンク」
一方で、ハイブリッド種子の普及に伴う「遺伝資源の画一化(伝統的な種の喪失)」への懸念から、在来種を守る動きも強化されています。在来種を地域で管理する「農民管理の種子システム」への投資も行われています。
➀ コミュニティ・シードバンク(CSB)
村単位で地域の在来種(ソルガム、ミレット、地域の豆類など)を保存・共有する仕組みが再評価されています。これらは、肥料がなくても育つ、特定の病害虫に強いといった「地域適応性」に優れており、気候変動に対するバックアップとして機能しています。
② アグロエコロジー(生態学的農業)
外来の種子や化学肥料に頼りすぎない持続可能な農業を推進するネットワークが、在来種の種子交換会などを通じて「種子主権(Seed Sovereignty)」を提唱しています。
(3)2025年の最新方針:デジタル化とフォーマル・インフォーマルの融合
アフリカ連合(AU)や各国政府は、これまで対立しがちだった「商業種子(フォーマル)」と「伝統種子(インフォーマル)」を統合した戦略を打ち出しています。
➀ デジタル・シード・ロードマップ
スマホアプリを活用し、農家が自分の土地に最適な種子(ハイブリッドか在来種か)を選択できる情報提供プラットフォームの整備が進んでいます。
② 認証制度の柔軟化
伝統的な種子であっても一定の品質基準を満たせば「認定種子」として公的に流通・販売できる仕組みを導入する国(エチオピア等)が増えており、在来種の経済価値を高める試みがなされています。
(4)アフリカが目指す「ハイブリッドな未来」
アフリカの戦略は、単一のモデルではなく、「商業的な増産(ハイブリッド)」と「生物多様性の維持(在来種)」をバランスよく組み合わせることにあります。これは、極端な気候変動に直面する他の発展途上地域にとっても重要なモデルケースとなっています。
8. ロシア:国家の命運を懸けた「脱・輸入依存」と食料主権の確立
ロシアは世界最大の小麦輸出国でありながら、その生産を支える種子(特にトウモロコシ、ヒマワリ、テンサイなど)の多くを欧米の種子メジャーに依存していたという、極めて歪な構造を抱えていました。2022年以降の地政学的リスクを受け、現在、世界で最も急速かつ強制的に「種子自給」を推進している国の一つです。
(1)「種子の武器化」への危機感と強制的な自給
2022年のウクライナ侵攻後の制裁により、欧米の種子メジャー(バイエル、コルテバ、シンジェンタ等)が、ロシア市場からの撤退や事業縮小を示唆しました。これを受け、ロシア政府は「種子の海外依存は国家安全保障上の致命的な欠陥」であると再定義しました。
➀ 輸入割当(クォータ)制の導入
2024年より、非友好国からの種子輸入に対して厳格な割当制限を開始。2025年にはさらにその枠を絞り込み、国内農業者に「強制的に」国産種子への切り替えを促しています。
② 目標数値の法的義務化
ロシア食料安全保障ドクトリンに基づき、2030年までに主要作物の種子自給率を75%以上に引き上げることを至上命令としています。
(2)国家主導の「育種・遺伝子センター」の再構築
ソ連崩壊後に衰退した国内の育種基盤を、国営企業や科学アカデミーを中心に急速に再整備しています。
➀ 科学技術プログラム(FSTP)
テンサイ、ジャガイモ、ヒマワリなど、特に海外依存度が高かった(一部は90%以上)作物に予算を集中投下。2025年現在、これまで皆無に等しかった国産の多収量テンサイ種子などが市場に投入され始めています。
② 知財の「国産化」
外資企業の知財に頼らず、国内の遺伝資源バンクを活用した独自の育種プログラムを強化。デジタル育種技術の導入も国策として進められています。
(3)輸出大国としての「種子主権」の確立
ロシアにとっての種子自給は、単なる国内消費のためだけでなく、世界最大の小麦輸出国の地位を維持するための「防衛策」です。
➀ サプライチェーンの組み替え
欧米に代わるパートナーとして、中国やインドとの種子技術協力や、BRICS諸国内での種子流通網の構築を模索しています。
② 「真の食料大国」への脱皮
「穀物を売って種を買う」という構造から、「種から生産までを自国で完結させる」構造への転換を、国家の威信をかけて進めています。
(4)主要作物の種子自給率75%へ
「ロシア食料安全保障ドクトリン(Food Security Doctrine of the Russian Federation)」とは、ロシアが食料を単なる産品ではなく、「国家の独立と主権を守るための戦略的武器」と位置づけ、その自給自足の目標値を法的に定めた国家基本方針です。
ロシアのドクトリンは、「種子が他国に握られている状態は、安全保障上の致命的な欠陥である」と断定しています。これは、野菜種子の9割を海外に依存している日本にとって、非常に重い警告として受け止められます。
ロシアの事例は、日本にとっても「他国に種子を握られることが、有事の際にどのようなリスクになるか」を最も鮮明に示すケーススタディとなります。
9.各国の比較から見えるもの
(1)各国の種子戦略
ここまで見てきた各国の種子戦略をまとめると、以下の特徴が浮かび上がります。
| 国・地域 | 戦略の核心 | 主な手法・キーワード | 自給へのアプローチ |
| 日 本 | 知財管理・
上流特化 |
種苗法改正、R&D集中、
国内回帰検討 |
設計図(知財)を握り、リスクを分散。生産は海外に委託しつつ、優れた「品種の設計図(知財)」と「育種技術」を国内で死守・管理する。 |
| アメリカ | 知財・
テック覇権 |
ゲノム編集、特許保護、
デジタル農業 |
世界標準を握り、輸出で支配する。強力な特許制度と民間メジャーの独占的技術(デジタル・ゲノム)で、世界の種子スタンダードを支配する。 |
| 中 国 | 独立自強・
国家防衛 |
南繁(シリコンバレー)、
GM解禁 |
100%内製化を目指す「農業チップ」。種子を「農業の半導体」と定義し、国家主導の巨大投資とバイオ技術で、海外依存を徹底的に排除する。 |
| 仏・蘭 | 基準輸出・
ブランド |
環境規制、高品質基準、
輸出ハブ |
欧州基準を「世界のパスポート」にする。EUの厳しい環境基準を逆手に取り、高品質・高付加価値な種子を「欧州ブランド」として世界に売り込む。 |
| チ リ | 増殖プラット
フォーム |
逆シーズン生産、
受託増殖、特区 |
世界の供給網に不可欠な「工場」になる。南半球の利を活かした「受託生産」に特化し、世界の種子供給を支える物流・生産のハブとなる。 |
| インド | 権利の均衡 | 自家採種権の死守、
ハイブリッド普及 |
小規模農家保護と企業投資の両立。農家の「自家採種」の権利を法律で死守しつつ、民間企業の「ハイブリッド種子」を普及させる折衷型モデル。 |
| アフリカ | レジリエンス・
適応 |
耐乾性品種、シードバンク、多様性 | 飢餓克服と伝統種の保存を併走させる。耐乾性などの改良品種で生産性を上げつつ、地域の「コミュニティ・シードバンク」で在来種の多様性を守る。 |
| ロシア | 強制的自給・
食料主権 |
輸入割当と国策投資により、短期間で「脱・欧米依存」を強行する | 強制的な自給。地政学的リスクを背景に、輸入制限と国家投資を組み合わせ、欧米依存を力づくで脱却する「背水の陣」の戦略。 |
(2)結論としての全体像
ここまで見てきたように、種子に対する認識は、「国家の存立を左右する戦略的資材」に変質してきており、次の3つの顔を同時に持つ複合的な戦略資産であると言えます。
- 生存資産: 飢餓を防ぐ「命のタネ」
- 経済資産: 特許料を生む「稼ぐタネ」
-
政治資産: 他国への影響力を持つ「統治のタネ」
各国は、戦略的資材でもある種子を守るために、さまざまな施策を行っています。今、世界の種子事情は「民間主導の技術独占」か「国家主導の完全自給」か、あるいはその隙間を縫う「地域適応型の多様性維持」かという、3つの大きな潮流が交差する「種子戦国時代」にあるといえます。
日本が直面している「野菜種子自給率1割以下」という現実は、この3つの資産すべてにおいて海外(特に特定の少数国)に生殺与奪の権を委ねているという危うい状態にあります。日本は、今後、どのような方向で「種子主権」を守っていくのでしょうか。
第4章 まとめと日本への示唆
世界各国の種子戦略を概観すると、種子自給率とは単なる「物理的な在庫数」ではなく、「遺伝資源、技術、知財制度の三位一体による統治能力」であることが浮き彫りになりました。これらを踏まえ、日本が今後進むべき方向性を考えます。
1.世界の先行事例から学ぶ3つの種子保障モデル
各国の動向は、大きく以下の3つのモデルに分類できます。
(1) 「テック・知財覇権モデル」(米国・EU)
最先端のバイオ技術と強力な特許制度を武器に、世界市場のルールそのものを支配する。
(2) 「国家主導・完全自給モデル」(中国・ロシア)
巨額の国費を投じ、研究から生産までを垂直統合。海外依存を徹底的に排除する。
(3) 「レジリエンス・多様性モデル」(インド・アフリカ)
最新のハイブリッド種子を導入しつつ、地域固有の在来種を「シードバンク」等で保護し、予測不能な事態に備える。
2.日本が直面する固有の課題とポテンシャル
日本の現状は、世界でも稀に見る「高度な開発力(R&D)」と「脆弱な生産基盤」のアンバランスにあります。
- 強み ⇒ 野菜種子などの特定分野における世界トップクラスの育種技術と、独自の遺伝資源(「おいしさ」や「機能性」)。
- 弱み ⇒ 採種地の海外依存(9割)と、国内の高齢化による育種・採種ノウハウの喪失リスク。
3.日本への具体的な示唆:次世代の種子安全保障
日本が「真の自給率」を向上させ、食料安全保障を盤石にするための4つの指針とし以下を提言します。
(1) 「設計図の自給」と知財管理の徹底
物理的な生産地が海外であっても、その種子の「親株」と「データ(ゲノム情報)」を国内で完全にコントロールし続けることが最優先事項です。改正種苗法を基盤として、日本の優良品種が海外で無断増殖されないよう、デジタル技術(DNA鑑定やブロックチェーン)を用いた監視体制を強化する必要があります。
(2) 国内採種体制の「スマート化」による回帰
コストや気候の制約で海外へ流出した採種工程を、「植物工場」や「自動授粉ロボット」などのテクノロジーによって国内へ呼び戻す「スマート国内採種」への投資が求められます。これは、労働力不足を解決しながら、有事の際の供給途絶リスクを回避する現実的な道です。
(3) 地域在来作物の「分散型シードバンク」化
日本各地で数百年にわたり守られてきた在来作物(伝統野菜)は、その土地の気候や病害虫に耐え抜いてきた「強靭な遺伝子の宝庫」です。
➀ 生きた保存
企業主導の画一的な種子に依存しすぎず、地域農家や家庭菜園レベルでの「自家採種」を支援し、地域ごとに種を繋ぐインフォーマルな供給網を再評価すべきです。農家頼みにするのではなく、地域が主導してオンファームで種継ぎをし続けることが必要です。長野県のように県条例によって野菜在来種の保存に取り組む自治体がありますが、他の自治体でも検討して欲しいものです。
② 究極のセーフティネット
有事に外部からの種子や肥料の供給が断たれた際、肥料が少なくても育ち、種が毎年採れる在来種は、食料主権を守る最後の砦となります。だからこそ、全国各地の地域が在来種の保全取り組むべきです。
この在来種を地域で守る「地域適応型の多様性維持」を実行することで、種子が持つ遺伝資源の価値、育種・栽培技術の継承なども可能となります。本当の意味での「種子主権」を握るためには、地域における在来種の保全は欠かせません。
(4) 「みどりの食料システム戦略」との連動
2050年を見据えた環境負荷低減(農薬・肥料減)を実現するためには、環境負荷が低くても収量を維持できる「高抵抗性品種」の開発が不可欠です。これを「種子の自給」とセットで推進することで、日本の農業全体の競争力を高めることができます。
4.結論
2025年以降の種子自給戦略において、日本は、採種地の国内比率の向上、高度な育種・栽培技術による新品種の開発、在来種の保護など多方面から対策することが必要です。特に世界市場での種子の競争力をあげるためには、「遺伝情報・技術・法」を押さえ、開発した種子を確実に「供給」できるようにすることです。
- 「地域(在来種)」で生物多様性と生存のバックアップを確保する
- 「技術(ゲノム・AI)」で開発スピードを握る
- 「法(知財)」で権利を守る
- 「分散(サプライチェーン)」で供給リスクを抑える
この多層的な防衛線こそが、グローバルな変動に翻弄されない日本の「食の源流」を守る手段になり得ると考えます。
また、これと相反しますが、農民の権利として、在来種を国や民間企業などの他人任せにせず、地域で守っていくことが重要になるのではないでしょうか。
【参考資料】
日本の食料自給率:農林水産省
「中国網日本語版(チャイナネット)」2025年7月4日
農林水産政策研究所 [主要国農業政策・食料需給]プロ研資料 第6号(2024.3)(ロシア)
農林水産政策研究所 [主要国農業政策・食料需給]プロ研資料 第7号(2024.5)(インド)
インド国 農業研究所優良種子開発計画 事前調査報告書
ODEPA. Boletín de hortalizas, marzo 2025 – Opia.CL – FIA(チリ)
Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS)(チリ)
Euroseeds(欧州種子協会)(EU)
American Seed Trade Association (ASTA)
野菜の種子のほとんどが海外で生産されるわけ ~タネの国内自給率を高めることはできるのか~
25年ぶりの食料・農業・農村基本法の改正と伝統野菜のタネの行方
「農」しなくて大丈夫? ~自給的農業のススメ~