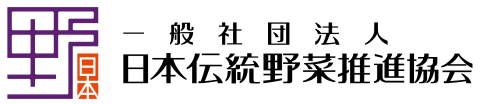日本の伝統果樹一覧 ~栗(くり)編~
目次
栗で豊かになる料理とお菓子
秋の味覚の代表格である栗。栗は、日本において縄文時代から食されていたとされる古い作物です。現在でも、日本各地には気候や風土に適応した在来栗の品種が存在します。
栄養面でも優れており、炭水化物が豊富で腹持ちが良く、木の実(ナッツ類)の中では脂質が非常に少なく、ヘルシーです。加熱しても壊れにくいデンプンに守られたビタミンCも特徴で、現代でも料理や和洋菓子に欠かせない食材として、さまざまなレシピに使われています。
焼き栗、茹で栗はもちろんのこと、和菓子では、栗きんとん、栗羊羹、栗まんじゅう、栗大福など、洋菓子では、モンブラン、マロングラッセ、マロンタルト、マロンパイ、栗のムースなどが思い浮かびます。料理では、栗ごはん、栗おこわ、栗そば、栗入り茶碗蒸し、栗の煮物(甘露煮)、栗のポタージュスープ、栗入りコロッケなど…。数えたらキリがないかもしれません。

今回は、伝統果樹シリーズ第二弾として、全国に残る在来種の栗をご紹介します。品種数が少ないので、栗の種類や歴史なども合わせて紹介していきたいと思います。どの品種も独特の食感や味わいを持ち、郷土料理などに使われてきましたが、一般市場には出回らない希少な品種もあります。日本の「栗」の魅力を知り、料理や加工品に、ますます活用していきたいものです。
世界の栗の種類
栗の起源は、約6,000万年前の白亜紀後期にさかのぼるとされます。アジア、ヨーロッパ、アメリカ、アフリカの四大陸に生育し、特に北半球の温帯地域に広く分布しており、アジア、ヨーロッパ、北アメリカで固有種が進化してきました。

世界中に分布している栗は、大きく、アメリカ栗、ヨーロッパ栗、中国栗、日本栗の4種に大別されますが、アメリカ栗は、1904年頃に中国栗に付着して侵入した栗胴枯病(Chestnut Blight)によって壊滅的な影響を受けました。この病害によって、アメリカ東部にあった推定約40億本の栗の木が数十年の間に枯死し、林業や生態系、文化などが深刻な打撃を受けました。現在、アメリカ栗の原生種は、自然環境では、ほぼ絶滅状態ですが、各地の保護団体が保全と復活に尽力しています。1)
そのため、アメリカ栗は市場に出回っておらず、現在、食べられている栗はヨーロッパ栗、中国栗、日本栗の3種です。日本は、世界的にも中国や地中海周辺のヨーロッパ地域と並んで栗の生産が盛んな地域です。
日本栗の食感の特徴
日本栗は、一般的には「和栗(わぐり)」と呼ばれて親しまれています。中国栗やヨーロッパ栗と比べると、大粒で水分の多いのが特徴です。生のままだとそれほど甘くありませんが、加熱によってでんぷんが糖化し、やさしい甘さと栗特有の香ばしい香りが引き立ちます。栗に含まれるでんぷん質が豊富かつ繊維質が細かいため、蒸したり焼いたりすると、焼き芋のような粉質感に近いホクホク感が味わえ、口の中でほどけるように崩れます。また、甘露煮や渋皮煮にすると、水分を含んでしっとりなめらかな口当たりになります。この状態でもホクホク感はある程度残り、柔らかさと栗本来の風味が両立します。
以下に世界の栗の生育地域と特徴を示します。
世界の栗の大別と特徴
| 種類 | 主な地域 | 特徴 |
| 日本栗(和栗)
Castanea crenata |
日本、韓国 | 実が大きく甘みが強い。縄文時代から利用されている。 ほくほく、繊維が細かい。 蒸し栗、焼き栗、和菓子に最適 |
| 中国栗
Castanea mollissima |
中国全土 | 病害に強く、世界の栽培栗の多くがこの種をベースにしている。 ややねっとり+甘みが強い。 甘栗むき出し(むき甘栗)などに使われる |
| ヨーロッパ栗(西洋栗)
Castanea sativa |
地中海沿岸、東欧など
米国東部 |
日本栗より小ぶりで粘りが強い。果肉が締まっていて、渋皮が剥きやすい。 しっとりなめらか+香り。 ロースト栗やマロングラッセ、洋菓子に向いている。 |
| アメリカ栗
Castanea dentata |
米国東部 | かつて森林に広く分布していたが、20世紀に病害で激減。再生努力が進行中。 |
和栗の歴史
縄文時代:貴重な主食としての栗
日本栗すなわち和栗(Castanea crenata Siebold et Zucarini)は、日本原産の果樹で、その歴史は古く、約5,500年前の縄文時代にはすでに食されていたとされます。
各地の遺跡から炭化した栗が大量に出土しており、特に、青森県の三内丸山(さんないまるやま)遺跡では、集落の周りに栗林が意図的に植林された大規模な栗林の跡が見つかっており、当時の人々が栗を重要な食料として、計画的な栽培をしていたことがわかっています。しかも、野生の栗よりも大粒の栗が出土しており、すでに栗の栽培技術を持っていたと考えられています。栄養価が高く、保存もきく栗は、当時の人々にとって貴重なエネルギー源だったのでしょう。また、食用だけでなく、薬用や木は建材にも使われた形跡もあり、日本最古級の利用植物の一つとされます。

古代・中世:税や献上品としての栗
弥生時代は、日本列島で水稲耕作が本格的に始まり、食料生産のあり方が大きく変化した時代ですが、稲作が定着し、十分な収穫量が得られるようになるまでには時間がかかり、地域によって普及の度合いにも差がありました。そのため、弥生時代から古墳時代にかけても栗は重要な食材でした。
奈良・平安時代になると、『古事記』や『日本書紀』、『万葉集』など文研や和歌など文学作品にも登場し、貴族たちの間では嗜好品としても親しまれていたことがわかります。
鎌倉・室町時代には、武士の携帯食や戦陣食として、また飢饉を救う重要な作物としての役割も担いました。
◎丹波栗の発展
平安時代には、京都の丹波地方で栗の栽培が盛んになり、「丹波栗(たんばぐり)」として、年貢や献上品として重宝されるようになりました。この時代には、すでに栽培技術が確立されていたと考えられています。
江戸時代:品種改良と流通の拡大
江戸時代になると、参勤交代の大名行列の土産物として、丹波栗が全国に広まっていきました。また、各地で栗の栽培が盛んになり、地域の特産品として定着していきました。栽培技術も発展し、江戸時代後半ともなると栗栽培に人為的要素が加えられ、大果の枝木を実生の苗木に接木するなども導入され、多様な品種改良が進みました。これにより庶民の間にも広く普及し、より身近な味覚となっていきました。
◎銀寄栗の誕生
丹波産の「銀寄(ぎんよせ)」という品種は、江戸時代の干ばつの際に、この栗を売って多大な利益を上げたことから名付けられたと伝えられています。

近代:クリタマバチの被害と品種改良
明治時代以降は、産業としての栽培が本格化し、多くの新品種が登場しました。食文化の多様化と共に、秋の味覚として親しまれてきました。
1901(明治34)年に、農林省農業試験場園芸部が、全国の栽培品種を集め、分類し、命名していった事から、現在の品種系統の統一化が始まり、年と共に品種の数は増え、1913(大正5)年には510余種が記録されていたそうです2)。
ところが、1941(昭和16)年に、栗に寄生するクリタマバチ3)が穂木または苗木とともに持ち込まれ、その被害は瞬く間に日本全国に広がってしまいました4)。戦前から1948(昭和23)年のクリタマバチ大発生までに栽培されていた品種の多くが被害に遭い、1955(昭和30)年頃には、クリタマバチ耐虫性のない多くの品種が栽培不能となり、市場から姿を消してしまいました。
そのため、1947(昭和22)年から国の園芸試験場が取り組んでいた育種にも「クリタマバチに対する抵抗性」という課題が加えられ、1959(昭和34)年には「丹沢」(クリ農林1号)、「伊吹」(クリ農林2号)、「筑波」(クリ農林3号)の3品種が登場しました。現在、栽培されている品種は基本的にクリタマバチ耐虫性品種です。
名称は生産地名が多い
日本の栗は、元々は、山栗(やまぐり)や柴栗(しばぐり)と呼ばれる野生種を品種改良したもので、農研機構の研究4)によると、遺伝的には九州、西日本、東北の3地方の野生の栗と栽培栗という4グループに分類できることを明らかにしています。栽培された栗は、各地域からの持ち込みや複数の地域での人為的な選抜が行われるなどし、複雑な栽培化過程を経ている可能性も示唆されています。
現在、栽培されている日本栗は、品種名とは別に、生産地域名を冠した名称で販売していることが多くみられます。たとえば、有名な丹波栗(たんばぐり)は、丹波地域で生産された栗の総称で、品種名ではありません。長野県の小布施(おぶせ)栗、茨城県の笠間(かさま)栗、岐阜県の恵那(えな)栗、熊本県の山江(やまえ)栗なども生産地域名です。


各生産地では、優良な栗の品種を何種類か生産しており、それが各地の気候風土と相まって、独自性のある味わいになっています。また、受粉率を高め、収穫量を増やすために「混植(こんしょく)」という栽培方法が行われてきたため、品種毎に明確に選別するのが難しいという事情もあります。そのため、販売の際は、品種名ではなく、産地名を掲げることが多くみられます。
農研機構の研究によると、日本栗の在来品種は丹波地域から全国に持ち運ばれ、栽培が広がったことを検証しています。DNA解析では、主に「丹波地域の品種」を中心に構成されるグループと「丹波地域以外の品種」で構成されるグループに分かれることを明らかにしています。5)
日本栗の代表的品種
栗は、前述の理由により、栽培地の名称が品名になっていますが、ここでは、古くから栽培されてきた在来種と代表的な品種をご紹介します。
柴栗(しばぐり)/山栗(やまぐり)
【由来】山野に自生する野生の栗で、日本栗(和栗)の原種とされています。自然環境に見られる在来種で、「ヤマグリ」とも呼ばれます。
【時期】地域や気候によって異なりますが、だいたい、8月下旬から10月下旬頃までが収穫時期です。熟して自然に木から落ちたものが食べ頃となるため、栗拾いをする場合は、地面に落ちている栗を探すのが一般的です。
【特徴】自然に繁殖できる強さがあり、イノシシやリスなどの野生動物にとっても重要な食糧源となっています。病害虫への耐性も比較的高く、日本の風土に適応しているため、栽培品種との交配にも利用されることがあります。
本州、四国、九州の広範囲にわたって自生していますが、北海道では栽培も行われています。自生している柴栗は地元住民が手に入れることが多く、一般の市場にはあまり出回りません。
実は小さいですが、甘味が強く香りも豊かで、野趣あふれる味わいが特徴です。焼き栗などにすると風味がいっそう引き立ちます。ただし、渋皮(外側の硬い皮を剥いた後に現れる茶色く薄い皮)が果肉にしっかりと密着しており、非常に剥きにくいという欠点があります。
岸根栗(がんねぐり)
【由来】山口県岩国市の岸根地区が原産地とされ、同地区を中心に栽培されている大粒の栗です。この地域で生産されるものは、特に甘みと貯蔵性の高さで知られています。歴史は古く、江戸時代から栽培されていたと伝えられており、地元では「幻の栗」と称されることもあります。
【時期】収穫時期は10月中旬から下旬頃の晩生種です。栽培には手間がかかりますが、病害虫に強く、品質の安定した実をつけるのも特徴です。収穫量が限られているため市場にあまり多く出回らず、希少価値が高い栗として扱われています。
【特徴】最大の特徴は、その実の大きさと美しさです。粒は非常に大きく、ふっくらと丸みがあり、見た目にも存在感があります。皮は比較的剥きやすく、渋皮もスムーズに取れるため、調理しやすい点でも優れています。
味わいは甘味が強く、しっとりとした食感で、加熱するとさらに風味が増します。栗ご飯や焼き栗はもちろん、和菓子や洋菓子の材料としても高く評価され、日本を代表する優良品種の一つとされています。
見た目・美味しさ・扱いやすさの三拍子がそろった高品質な栗で、贈答用や高級食材として人気があります。地元ではブランド化も進められており、山口県を代表する特産品の一つとなっています。
銀寄(ぎんよせ)
【由来】大阪府豊能郡能勢町が発祥で、江戸時代から伝わる栽培栗の品種です。「栗の王様」とも呼ばれるほどの品質の高さと収量の安定性から、古くから栗の主要品種として全国各地で栽培されています。なかでも、特に丹波栗の代表品種として知られています。
名前の由来にはいくつかの説がありますが、有力なものとしては「この栗を出荷すれば“銀(お金)を寄せる”ほど売れた」ということから「銀寄」と呼ばれるようになったと言われています。それだけ高く売れた、つまり価値ある栗と認識されていた証でもあります。
【時期】収穫時期は、9月下旬から10月中旬にかけてです。これは「筑波」の次に収穫される中生品種にあたります。樹勢が強く育てやすいこと、結実が安定していることなどから、生産者が扱いやすい品種で、商業栽培にも家庭栽培にも適した代表的な和栗のひとつです。
【特徴】実は大きめで、丸みのあるふっくらとした形状をしており、見た目に優れています。また、果皮や渋皮が比較的むきやすいため、調理しやすい点でも人気があります。
味わいについても非常に評価が高く、甘みと風味が豊かで、ホクホクとした食感を楽しめるのが特徴です。「大粒・甘い・むきやすい・調理しやすい」という四拍子そろった優良品種で、さまざまな料理や和菓子に適しており、プロの料理人にも好まれる品種です。
丹沢(たんざわ)
【由来】「丹沢」は、クリタマバチに抵抗できる品種を開発する必要に迫られた育種の流れで、1949(昭和24)年から行われた「乙宗(おとむね)」と「大正早生(たいしょうわせ)」の交雑によって誕生した品種です。1959(昭和34)年には「くり農林1号」として農林水産省に認定されました。現在では、国内生産量が「筑波(つくば)」と「銀寄(ぎんよせ)」に次いで3番目に多く栽培されています。
【時期】栗の収穫シーズンのトップバッターを飾る早生品種(8月下旬〜9月中旬頃)の代表格で、さまざまな地方で栽培されている人気の品種です。
【特徴】果実の形状は、コロンとしたおにぎり型で、やや大粒で先端が尖っているのが特徴です。他の品種と比べツヤが少なく、色は薄く、裂果(れっか:縦に入っている筋)が多いのも丹沢栗の特徴といえます。実は白色に近い黄色で、口の中に入れるとホロホロと崩れるほど粘り気が少ないです。甘みは他の品種(特に利平栗など)に比べると控えめですが、渋みが少なく、栗本来の優しい風味と香りが楽しめます。淡白な味わいで甘味や香りが少ないため、スイーツから料理まで幅広く活用できます。栗の中では、比較的皮がむきやすい品種です。
伊吹(いぶき)
【由来】「伊吹」は、1949(昭和22)年に、大阪発祥の「銀寄(ぎんよせ)」と、東京多摩地方の「豊多摩早生(とよたまわせ)」を交雑した品種です。戦後の品種改良によって「くり農林2号」として開発され、1959年(昭和34年)に登録されました。
【時期】9月上旬から中旬に収穫される早生品種です。早生品種でありながら、双子果(一つのイガに2つの実が入っている状態)や、実が割れてしまう裂果が少ないため、品質が安定している点が利点です。また、栽培適地の範囲が広く、東北から九州まで広い範囲で栽培できます。耐寒性も比較的強いため、寒冷地でも栽培しやすいとされており、岐阜県の中津川や能登地方でも栽培が行われています。
【特徴】果実は25g程度で、丸みを帯びた短三角形をしており、果頂部はやや尖っています。果肉は淡い黄色で、粉質ながら、他の品種と比べてねっとりとした食感が特徴です。甘みと香りは中程度とされています。和栗は鬼皮が剥きにくいものが多いですが、「伊吹」は比較的、鬼皮(栗を覆う茶色く硬い皮)が剥きやすいとされ、加工用にも適しています。
筑波(つくば)
【由来】「筑波」は、日本で最も広く栽培されている代表的な栗の品種です。1949(昭和24)年に「岸根(がんね)」と「芳養玉(はやたま)」を交雑して誕生した品種です。農研機構(農業・食品産業技術総合研究機構)によって開発された改良品種で、1959(昭和34)年に「くり農林3号」として登録されました。日本の気候、特に寒冷地にも適応できるように開発されており、その優れた特徴から、日本の栗の主力品種の一つとして知られています。
【時期】中生品種で、9月下旬から10月上旬頃に収穫されます。「丹沢(たんざわ)」の次に収穫される品種として、日本の秋の味覚を代表する存在となっています。
【特徴】収穫量が多いため商業栽培に適しており、日本の栗市場を支える重要な品種です。クリタマバチという害虫に対する抵抗力が高く、栽培しやすい点も大きな利点です。実は、大粒で見た目が美しく、豊かな甘みと香りが強いのが特徴です。その優れた品質から、さまざまな料理に活用しやすい品種です。
石鎚(いしづち)
【由来】石鎚は、クリタマバチの抵抗性を持つ育種の流れで、1948(昭和23)年に「岸根(がんね)」に「笠原早生(かさはらわせ)」を交雑させ、得られた実生から選抜育成された系統です。1956(昭和31)年から全国40か所の試験場において特性検定試験・地方適応試験が行われ、1968(昭和43)年に「石鎚」と命名され、「くり農林4号」として農林認定されています。「石鎚」という品種名は普及が期待される愛媛県の石鎚山に由来しています。当時はまだ種苗法の品種登録制度なかったため農林認定だけとなっています。
【時期】収穫時期は、10月上旬から下旬頃の晩生種にあたります。貯蔵性が高く、氷温貯蔵されたものが11月まで出荷されることもあります。樹勢が強く病害虫にも比較的強いことから栽培が容易で、果実の落果も少なく収量も安定しているため、生産者にとっても導入しやすい品種として近年注目が高まっています。
【特徴】果実は30g前後と大粒で、丸みのあるふっくらとした形状をしており、外観が美しく、果肉には甘味がしっかりとあり、加熱するとホクホクとした食感と栗本来の香りが引き立ちます。また、渋皮が比較的剥きやすいため調理や加工の際にも扱いやすいという実用性の高さを備えており、焼き栗や栗ご飯はもちろん、和菓子や洋菓子など多彩な料理にも適しています。
利平(りへい)
【由来】1940年(昭和15年)に、岐阜県の土田健吉氏が、日本の栗と中国の栗(天津甘栗に用いられる品種)を交雑させて生み出した品種です。品種名は、土田家の屋号「利平治(りへいじ)」に由来します。
【時期】9月中旬から10月下旬にかけて収穫される中生~晩生種です。収穫量が少なく、栽培には手間がかかるため、希少価値が高いとされています。このため、一般の市場にはあまり出回らず、「幻の栗」と呼ばれることがあります。
【特徴】利平栗の外観は、栗らしい丸々としたふっくらした形で、大粒で、食べ応えがあります。果頂部(先端)には産毛が多く見られます。皮は黒みがかった濃い茶色で、他の品種と比べると光沢があります。最大の魅力は、その濃厚な甘みと香りです。果肉は適度に粉質でホクホクとした食感があり、栗本来の美味しさを存分に楽しめます。その優れた食味から、非常に人気が高い品種です。鬼皮(外側の固い皮)は非常に固くて剥きにくいですが、渋皮は比較的剥きやすいという特徴があります。

国見(くにみ)
【由来】「国見」は、「丹沢(たんざわ)」と「石鎚(いしづち)」を交配して育成された「くり農林5号」で、1981年に品種登録されました。名前は、栗の主産地の一つである熊本県の国見岳にちなんで名付けられました。
【時期】「丹沢」と「筑波」の間に収穫される早生品種で、9月上旬から下旬頃が旬となります。お彼岸の頃に最盛期を迎えることが多いです。「国見」の最大の特徴は、病害虫に強いことです。特にクリタマバチやモモノゴマダラノメイガといった栗の大敵に対して強い抵抗性を持つため、栽培しやすい品種として知られています。
【特徴】果実は30g前後の大粒で、ほぼ円形に近い形をしています。赤みがかった茶色で光沢があります。肉質はやや粉質ですが、甘みや香りは少ないとされています。そのため、そのまま食べるよりも、甘露煮などの加工用として利用されることが多い品種です。
人丸(ひとまる)
【由来】「人丸」は、千葉県成田市の栗農家が、自身の「筑波」と「丹沢」の混植園で発見した偶発実生(偶然に自然に生えた実生)を育成した品種です。1985年に品種登録されました。
【時期】早生品種で、9月中旬から下旬にかけて収穫されます。「丹沢」の終わり頃から「筑波」の始まる少し前までが旬となります。クリタマバチに対する抵抗性は「筑波」と同程度とされています。市場では大粒の栗が好まれる傾向があるため、小粒の「人丸」の収穫量は少なく、一般市場にはあまり出回らない希少な品種とされています。「幻の栗」と呼ばれることもあります。
【特徴】「丹沢」と同程度の中粒で、現在の主要品種の中ではやや小さめです。果皮は赤みがかった褐色で、強い光沢があるのが特徴です。果肉は鮮やかな黄色で、粉質でホクホクした食感です。甘みが強く、豊かな香りが楽しめます。その上品で濃厚な味わいから、モンブランやマロンペーストなどの加工品に特に適していると評価されることがあります。ただし、渋皮は剥きにくいという特徴もあります。
現代の主要品種の誕生
昭和初期にクリタマバチの被害によって、数多くあった栗の品種は激減してしまいましたが、戦後、国の研究機関によって「丹沢」「伊吹」「筑波」「石鎚」「国見」といった、現在も栽培されている主要な品種が開発されました。これらの品種は、早生、中生、晩生と収穫時期が異なるように育成され、安定した供給が可能になりました。その後も現在の農研機構での品種改良が進められ、あらたな品種も登録されています。また、「利平(りへい)」のように、中国栗と日本栗の交雑種として生まれた品種も、甘みと風味の良さで高品質な栗として広く知られるようになりました。
近年も品種の育成研究が進められており、新たな栗の品種が生まれています。これらは、農林水産省の品種登録データから検索閲覧することができます。
日本初、栗のGI制度登録
2017年には、茨城県東茨城郡茨城町下飯沼地区で生産される「飯沼栗(いいぬまぐり)」が、栗として日本で初めて「地理的表示(GI)保護制度」に登録されました。
「飯沼栗」は、特定の品種名ではなく、この地域で独自の栽培方法と貯蔵技術を用いて生産された栗に与えられるブランド名です。長年研究を重ねてつちかった技術は門外不出で、生産農家秘伝の飯沼栗を生産しています。
飯沼栗の特徴は、「一つのイガに一つだけ」の実を育てる独自の栽培方法をとっている点にあります。一般的な栗は一つのイガの中に2~3個の実が入りますが、飯沼栗は1個だけで、これにより、養分が凝縮され、非常に大きく、ふっくらと丸い実が育ちます。その大きさは、通常の栗の2Lサイズが飯沼栗ではさらに大粒となるほどです。
次に、独自の「冷温貯蔵」により甘さを増します。収穫後に特別な貯蔵庫で低温管理することで、栗内部のでんぷん質が糖分に変わる「熟成」が行われます。そうすることで、各段に甘みが増し、スイーツのような濃厚な甘さと風味を生み出します。
また、品質管理や選果も徹底しており、形や色つやが優れた見た目にも美しい栗を出荷するために、収穫後の洗浄や、3回にわたる厳格な選別・選果が行われます。出荷時期は、冷温貯蔵を行うため、栗の最盛期である9月・10月を過ぎた、10月下旬から11月中旬にかけて出荷されます。この時期に出荷することで、他の栗が市場から減る時期に、質の高い栗を安定して供給することができます。
「飯沼栗」は、この特別な栽培方法と品質の高さが認められ、2017年に栗として日本で初めて「地理的表示(GI)保護制度」に登録されました。これらの特徴から、飯沼栗は東京の市場では「最高級の栗」として高い評価を得ており、一般的な栗の2倍以上の価格で取引されることも珍しくありません。生産量が限られているため、希少価値の高い栗として知られています。
ここまで、伝統的な山栗からGI制度に登録された栗までをみてきましたが、いかがでしたでしょうか?食べてみたい栗はありましたか?この秋、栗の味を直接味わえる焼き栗から栗ご飯や栗きんとん、和栗のモンブランまで、ぜひ、いろいろな栗を味わって楽しんでみてくださいね!
【参考資料】
1)日経サイエンス2014年9月「生まれ変わるアメリカグリ」
2)足立音衛門
3)国立環境研究所 侵入生物データベース「クリタマバチ」
4)農研機構「ニホングリの栽培化の歴史を遺伝的解析から明らかに」
5)農研機構「ニホングリ在来品種の遺伝的関係をDNA解析により検証」
農研機構「果樹茶業育成品種紹介」
中津川・恵那広域行政推進協議会「栗全書」
大阪府「くり」
【協会関連記事】
日本の伝統果樹一覧 ~香酸柑橘(こうさんかんきつ)編~
日本の伝統果樹一覧 ~柿(かき)編~
日本の伝統果樹一覧 ~葡萄(ぶどう)編~