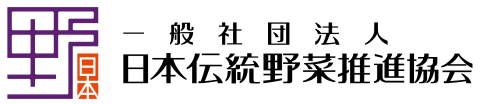夏野菜は旬真っ盛り!お盆の精進料理や夏祭りで楽しむ地域の伝統野菜を使ったオリジナリティあふれるメニュー
毎日、暑い日が続きますね。気象庁の発表によると、2025年の8~10月の平均気温は全国的に平年より高い見込みだそうです。朝から、これだけ暑いと農作業も厳しいし、農作物の出来も心配になります。とはいえ、暑くても、夏休みになれば故郷に帰る人も少なくないでしょう。この時期は、お盆を迎える地域も多く、ご先祖さまと帰郷する人を迎えるように、各地で夏祭りや盆踊りが開催され、盛り上がりをみせます。
そこで、今回は、お盆の時期に旬を迎える伝統野菜をご紹介します。帰郷の際には、ぜひ、地元の伝統野菜を味わってください。
旧暦と新暦、お盆はいつ?
お盆は、ご先祖様の霊を供養し感謝を捧げる伝統行事で、古くから人々に大切にされています。仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」が由来となっており、日本の祖先崇拝の考え方と融合して現在の形になりました。
お盆の期間は8月13日から16日までの4日間とする地域が多いですが、期間や行事の内容は地域によって異なります。
かつて、お盆は旧暦の7月15日(新暦の9月7日前後)を中心に行われていました。この時期は、夏の暑さもピークを過ぎ、農作業がひと段落する時期でもあったため、ご先祖様を迎え、供養することが落ち着いてできる時期だったと考えられます。

ところが、明治になると、国際基準に合わせるために新暦が導入され、旧暦と新暦の日にちに1ヶ月ほどのズレが生じてしましたました。これによって実際の季節感とのズレも生じてしまい、さまざまな年中行事が影響を受けました。お盆もその一つです。新暦の7月中旬は農繁期に当たるため、これを避けた地域が多かったとみられ、お盆の日が地域によって分かれることになりました。
東京都や神奈川県、静岡県の一部などでは、7月盆(新盆)として新暦の7月13日から16日にお盆を迎える地域があります。明治政府のお膝元であった東京やその周辺の都市部または一部の地方都市で、公務員や商人といった農業に直接従事しない人々が多かった地域では、旧暦7月15日をそのまま新暦に当てはめることができ、比較的スムーズに移行が進んだと言われています。
しかし、日本の大部分の地域、特に農村部では、新暦の7月はまだ農繁期であり、お盆の行事をゆっくり行う時間がありませんでした。そこで、昔からの旧暦7月15日の季節感を保ちつつ新暦に合わせるために、約1ヶ月遅らせて、新暦の8月15日にお盆を行うようになりました。これを「月遅れ盆」と呼びます。現在、全国的には、この8月のお盆が主流となっています。
また、沖縄県など、独自の文化や歴史を持つ一部の地域では、現在でも旧暦の7月15日にお盆を行っています。そのため、年によって日にちが変わり、新暦の8月下旬や9月上旬にお盆を迎えることがあります。
もともと、日本の年中行事は、豊作を祈願し、収穫を感謝するための農耕儀礼(農耕にまつわる儀式や祭り)に由来するものが多いため、農事暦と非常に密接な関係にあります。お盆も、先祖の霊を迎え、収穫期の準備や稲の生育を見守ってもらう意味合いがあるのです。
お盆に食べる伝統野菜
さて、そんなお盆には、各地で盆踊りや夏祭などのイベントが行われ、いつもとは違った地域の賑わいがあります。食事も精進料理が振舞われるなどして、普段にはない郷土料理も味わえます。そんな地域の行事と伝統野菜の結びつきをみていきたいと思います。
精霊馬(しょうりょううま)と夏の瓜(きゅうり・なす)
お盆の供物として最も広く知られているのが、ご先祖様の霊があの世とこの世を行き来するための乗り物として作られる精霊馬です。キュウリとナスが乗用動物に見立てられます。ご先祖さまを迎えに行く時は、少しでも早く家に来られるようにと、足の速い馬に見立てたキュウリが使われます。そして、あの世に戻る時には、道中ゆっくりと景色を楽しんだり、たくさんの供物を持ち帰ったりできるようにと、歩みの遅い牛に見立てナスが使われます。

これらのキュウリやナスは、単なる供物としてだけでなく、地元の恵みとして大切にされています。伝統野菜のキュウリやナスは各地に残っています。今年は、故郷のキュウリ・ナスを使ってみてはいかがでしょう?
| 青森県:糠塚きゅうり
岩手県:地うり・昔きゅうり 秋田県:小様きゅうり 山形県:勘次郎胡瓜、畔藤(くろふじ)きゅうり 福島県:会津余蒔胡瓜、小白井きゅうり 群馬県:高山きゅうり、平原きゅうり、持倉きゅうり、昔きゅうり 埼玉県:奥武蔵地這きゅうり 神奈川県:相模半白きゅうり 石川県:加賀太きゅうり 富山県:高岡太胡瓜 長野県:佐久古太きゅうり 静岡県:井川地這いきゅうり 愛知県:青大きゅうり 奈良県:黒滝白きゅうり、大和三尺きゅうり 大阪府:毛馬胡瓜 徳島県:美馬太きゅうり 宮崎県:平家きゅうり |
| 北海道:札幌早生なす
宮城県:ちょっぺなす、仙台長なす 秋田県:関口なす、仙北丸なす、新処なす、富沢なす、菊千成なす、河辺長なす 山形県:薄皮丸なす、民田なす、窪田なす、でわこなす、沖田なす、萬吉(まんきち)なす、畑なす、サファイアなす 福島県:岡部早生丸なす、会津丸なす、濡羽烏なす 栃木県:高萩なす 群馬県:白なす 埼玉県:へたむらさきなす、埼玉青なす(白なす) 千葉県:真黒1号なす、真黒2号なす、蔓細千成なす、白なす 東京都:砂村なす、山茄、寺島(てらじま)なす 神奈川県:真黒なす、橘田なす 新潟県:十全なす、梨なす(黒十全)、深雪なす、中島巾着、魚沼巾着、鉛筆なす、やきなす、久保なす、笹神なす(白なす)、柏崎緑なす、越後白なす、越の丸、一日市なす 福井県:くぼ丸なす、新保なす、立石なす、吉川なす、妙金なす 長野県:ていざなす 愛知県:愛知本長なす 大阪府:泉州水なす 和歌山県:湯浅なす 山口県:田屋なす・萩たまげなす 香川県:三豊ナス 宮崎県:佐土原なす |
お盆の行事食と伝統野菜
お盆の期間中、ご先祖様をお迎えする精霊棚(盆棚)には、様々な供物が供えられます。この中には、その時期に採れる旬の野菜や果物が含まれます。そこには、もちろん地域の伝統野菜もあります。
例えば、京都では「賀茂なす」や「万願寺とうがらし」といった京野菜がお盆のお供えに並ぶことがあります。沖縄の旧盆では、「ヘチマ(ナーベーラー)」や「フーチバー(ヨモギ)」、「ウンチェーバー(空芯菜)」などが、ご先祖様への供物や旧盆料理に使われます。これらは、厳しい夏の暑さを乗り切るための滋養強壮の意味合いも持ち合わせています。
お盆の期間は、肉や魚を使わない精進料理が基本となる地域も多く、野菜を中心とした煮物や和え物、漬物などが作られます。親戚が集まって食卓を囲むことも多く、その際の料理にも、収穫への感謝や子孫繁栄の願いを込めて、里芋やゴボウ、インゲン豆など旬の伝統野菜をふんだんに使った郷土料理が振舞われます。
ほかにも地域独特の精進料理があるので、ご紹介したいと思います。
宮城県:「おくずかけ(お葛かけ)」
宮城県南部では、おくずかけ(お葛かけ)という郷土料理があります。人参、ごぼう、里芋などの野菜と豆腐、油揚げ、豆麩をだし汁で煮込み、白石温麺(うーめん)を加えて、とろみをつけたもので、仙台のお盆の定番料理です。

山形県:「だし」
山形県の「だし」は、夏野菜を細かく刻んで和えたもので、在来種の民田ナス (みんでんなす)やキュウリが使われ、お盆の食卓にも並ぶことがあります。
長野県:精進揚げ
長野県では、精進揚げとして、お盆に天ぷらを食べる風習があります。特に野菜やキノコ類を揚げた精進揚げが一般的です。昔は油が貴重だったため、ご先祖様へのおもてなしとして特別な料理とされていました。饅頭を天ぷらにした「天ぷらまんじゅう」も、お盆のお供えとして食べられます。
京都府:アラメの煮物
京都府では、アラメという昆布の仲間の海藻と油揚げを煮て、砂糖と醤油で味付けした料理であるアラメの煮物を食べます。送り盆には、アラメを茹でた汁を門口にまく「追い出しアラメ」という風習があります。

鹿児島県:かいのこ汁
鹿児島県の「かいのこ汁」は、一晩水につけた大豆を粗挽きしてみそ汁に仕立てたもので、夏野菜のナスやイモガラ、カボチャなどに、キクラゲ、昆布などを入れて作られるお盆の精進料理です。
沖縄県:ウサチ(酢の物)
沖縄県では、大根、きゅうり、人参、ゴーヤーなどの野菜を使った甘めの酢の物・和え物であるウサチ(酢の物)を作ります。送り盆の朝食や昼食にお供えされます。
これらの精進料理には、その土地の伝統野菜や在来作物が用いられることが多く、地域の食文化を色濃く反映しています。
豊作への感謝と供養
お盆は、ご先祖様への感謝とともに、その年の豊作を願ったり、既に収穫された恵みに感謝したりする意味合いも持っています。古来、日本の農業はご先祖様や神々の力によって支えられているという信仰が強かったため、夏の収穫期に採れる野菜を供えることは、自然の恵みと祖霊への感謝の気持ちを表す行為でした。
また、この時期に、ご先祖さまと一緒に、素朴で体に優しい精進料理を食べることは、暑さでバテ気味の体を癒すことにもつながります。このように、お盆は単なる宗教行事にとどまらず、その土地の気候風土に適応し、育まれてきた伝統野菜と、それを取り巻く人々の暮らし、そして自然への感謝の心が深く結びついた大切な行事です。
夏祭りと伝統野菜
日本各地の夏祭りでは、その土地ならではの伝統野菜が、祭り料理や供物として使われることがあります。これらは単なる食材としてだけでなく、地域の文化や歴史、そして夏の旬を象徴する大切な存在です。ここでは、夏祭りと共に供される料理と伝統野菜をいくつかご紹介します。
大阪府「天神祭」
大阪三大夏祭りの一つ、大阪天満宮の天神祭では、キュウリの酢の物が欠かせないとされます。特に「鱧の皮の酢の物」は、宵宮の夕食でよく食べられます。また、タコとキュウリの酢の物も本宮のごちそうとして親しまれています。「なにわの伝統野菜」である「毛馬胡瓜(けまきゅうり)」を使うと、歯切れが良く美味しいと評判です。地域によっては「キュウリのザクザク」とも呼ばれ、キュウリを切る音や噛んだ時の音に由来すると言われています。

京都府「かぼちゃ供養」
京都市左京区にある安楽寺では、毎年7月25日に「かぼちゃ供養」が行われます。これは、200年以上前から続く伝統行事で、「鹿ケ谷かぼちゃ(ししがたにかぼちゃ)」を煮たものを食べて、「中風(ちゅうふう/ちゅうぶ)」という脳卒中などの病気にならないよう祈願します。

大分県「宇佐神宮夏祭り」
神輿(みこし)発祥の地とされる宇佐神宮の夏祭りのご馳走として、「みとり豆」を使った「みとりおこわ」という料理があります。地元では「おこわ」や「赤飯」と呼ばれています。お供え物としても、みとり豆の餡(あん)で、まんじゅうや茹で餅が作られます。「みとり豆」は、大分県宇佐市を中心とした県北部で古くから栽培されているササゲの一種です。

長野県「夏祭り」
長野県では、夏祭りや地域のイベントで、伝統野菜の「ぼたんこしょう」が使われます。「ぼたんこしょう」は、ナス科トウガラシ属のピーマン型のトウガラシです。ほど良い辛さが特徴で、「ぼたんこしょう味噌」や、天ぷら、つくねの具材などとして使われることがあります。

岐阜県「夏イベント」
「国府なす(こくふなす)」は、飛騨高山で100年以上前から作られている伝統野菜です。夏から秋にかけて旬を迎え、この時期、地域のイベントや観光施設で、焼きなすや揚げ出しそばなど、国府なすを使った特別メニューが提供されることがあります。

これらの例からもわかるように、古くから、お盆は、祖霊への感謝とともに、その年の豊作を願ったり、自然の恵みに感謝したりして、夏の収穫期に採れる野菜が供えられます。家族が集まるこの時期は、夏祭りやお盆といった行事を通して、日本の豊かな食文化に触れる良い機会です。皆さんもぜひ、伝統野菜を使った郷土料理を楽しんでみてください。
【参考資料】
農林水産省「うちの郷土料理」
【協会関連記事】
お盆の精進料理の献立は? ~時代で変わる野菜メニュー~