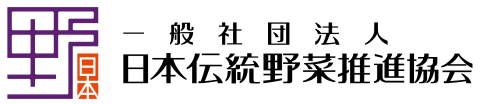あなたの食卓が未来を決める!短期利益の「死の経済」から、持続可能な食を追求する「命の経済」へ
目次
10月16日は国連が定めた「世界食料デー」です。世界的な飢餓と食料問題への意識を高め、解決に向けて行動を促すことを目的としています。そこで、今回のブログでは食料問題について取り上げてみたいと思います。
未来から問う「食料生産」のあり方
私たちは今、とても奇妙な時代に生きています。
世界中で毎日、大量の食料が廃棄されている一方で、飢餓に苦しむ人々が存在します。スーパーの棚には、一年中、安価で完璧な見た目の野菜が並びますが、その裏側では地球環境が悲鳴を上げ、未来の世代の食料基盤が蝕まれています。
こうした現代の食料システムの「歪み(ひずみ)」をどう解決すればいいのでしょうか?
ここでは、その答えをフランスの著名な思想家で経済学者のジャック・アタリ氏が提唱する二つの概念に求めてみたいと思います。
ジャック・アタリ (Jacques Attali) 氏は、フランスの著名な経済学者、思想家、作家であり、未来予測と文明論の大家として世界的に知られています。経済の方向性を「命の経済(人類の生存と生活向上に貢献する活動)」と「死の経済(短期的な利益追求や破壊)」という独自の二項対立で捉え、未来社会のあり方に警鐘を鳴らしています。
「命の経済(L’économie de la vie)」⇒ 人類の生存、健康、生活の質(QOL)向上に直接貢献し、長期的な視点を持つ活動。
「死の経済(L’économie de la mort)」⇒ 短期的な利益、競争、破壊、浪費を前提とし、人類の生存を脅かす活動。
この二項対立のレンズを通して、現在の食料生産が「命」と「死」のどちらに傾いているのかを分析し、持続可能な未来への道筋を考えてみたいと思います。
「死の経済」としての食料生産(現状への警鐘)
私たちが享受している安価で便利な食料システムの多くは、残念ながら「死の経済」の論理で動いています。
大量生産・大量廃棄の構造
グローバル企業が主導する食料生産は、効率至上主義に基づいています。大量の土地を使い、大量に生産し、大量に消費させることで、短期的な利益を最大化します。
その結果、信じがたいほどの食品ロスが発生しています。生産された食料の約3分の1が、流通過程や消費段階で捨てられているという現実があります1)2)。これは、食料そのものだけでなく、それに費やされた水、エネルギー、労働、そして環境への負荷を丸ごと破壊している行為であり、「死の経済」の最も分かりやすい例です。
環境と健康への負債
「死の経済」は、目先の利益のために、未来の資源を食い潰します。
土壌の疲弊:特定の作物を大規模に栽培する「単一栽培(モノカルチャー)」は、土壌の栄養を奪い、生態系のバランスを崩します。
化学物質依存:過剰な農薬や化学肥料の使用は、収穫量を増やす一方で土壌の生物多様性を破壊し、最終的には地下水や河川を汚染し、私たちの人体にも潜在的なリスクをもたらします。
動物福祉の無視:利益優先の劣悪な家畜の飼育環境は、動物の命を単なる「生産装置」として扱う「命」を軽視した行為です。
飢餓と格差
食料が、人々の生命を維持するための「権利」ではなく、投機や市場操作の対象となる「商品」となったとき、社会に構造的な不平等が生まれます。
食料価格の不安定化は、最も貧しい人々を飢餓の淵に追いやり、一方で豊かな国では飽食による健康問題が深刻化しています。これは、「命」を平等に享受する機会を奪う「死の経済」の残酷な側面です。

「命の経済」としての食料生産(未来への提言)
食料生産の舵を「死」から「命」へと切り替えるためには、人類の生存と生活の質(QOL)の向上を目的とした新しいシステムを構築する必要があります。
健康と予防医学としての食
食料を「病気を防ぐ薬」と捉え、生産の目的を「最大収穫量」から「最大栄養価」へと変えるというものです。
土壌の健康回復:農薬や化学肥料に頼らないオーガニックや自然農法を推進することで、土壌の健康を回復させ、栄養価の高い作物を生産します。
個別化された食料:AIやデータサイエンスを活用し、個人の健康状態や遺伝情報に基づいた、最適な食料を生産・供給するシステムは、未来の「命の経済」の柱となるかもしれません。
環境・資源との共存
地球の資源を浪費するのではなく、資源と共存する生産方法に移行します。
循環型農業:廃棄物を単なるゴミとするのではなく、肥料やエネルギーとして活用する「循環」を基軸とした農業が鍵となります。
持続可能なタンパク質:畜産が地球に与える負荷を軽減するため、培養肉や代替タンパク質(昆虫食など)の研究と実用化は、地球資源の節約に直結します。
※「命の経済」の視点だとこうなりますが、筆者としては、培養肉や昆虫食には、ちょっと抵抗があります。(-_-;)
クリーンな生産:太陽光や風力などの再生可能エネルギーを積極的に活用した植物工場やスマート農業は、エネルギー効率を劇的に改善します。
※ただし、再生可能エネルギーを活用する際には、機器で環境破壊をしないようにして欲しいです。本末転倒にならないように機器そのものの廃棄物の終着点までの配慮が必要だと思います。
知恵とテクノロジーによる地域分散
食料を遠方から運ぶのではなく、地域で生産し、地域で消費するシステムを復活させます。
フードテックの力:AIによる病害予測や精密な水・肥料の管理は、資源の最適化に役立ちます。テクノロジーは、効率化のためではなく、持続可能性を高めるために使うべきです。
地産地消の復活:都市型農業や地域ごとの小規模な農業を支援することで、サプライチェーンを短縮し、輸送コスト(エネルギー消費)を削減します。これは、地域経済を活性化し、食の安全保障を高める「命の経済」的なアプローチです。

食品ロス削減に関する法律を持つ主な国
「命の経済」にシフトするためには、生産面だけでなく、小売店や消費者の意識も変わっていく必要があります。
その中でも、食品ロスは、環境負荷や世界の飢餓問題にも関わる地球規模の課題ですが、私たち一人ひとりが、取り組むことのできる問題でもあります。世界では、国が知恵を絞り、食品ロス対策に前向きな解決策を実行しています。
ここでは、各国の「食品ロス」に対する法的な取り組みについて見ていきます。
1. フランス (France)
フランスは、世界に先行して「資源の循環と廃棄物の削減を目指した循環経済に関する法律」を公布し、アパレルの売れ残り商品の廃棄を禁止した4)国です。そして、ファストファッションと同様に、食品ロス対策においても世界的な先駆者です5)。
- 法律(2016年): 大手スーパーマーケットに対し、売れ残り、かつ消費可能な食品を廃棄することを禁止し、事前に契約した慈善団体への寄付または再利用を義務付けました。
- 罰則: 違反した場合は罰金が科せられます。
2. イタリア (Italy)
フランスと同じく2016年に食品廃棄規制法を成立させました5)。
- 法律(2016年): 食品の寄付を促進するため、企業が食品銀行や慈善団体に寄付しやすいよう手続きを簡素化し、寄付量に応じて税制上の優遇措置(インセンティブ)を提供しています6)。フランスと異なり、罰則よりも寄付促進に焦点を当てています。
3. 韓国 (South Korea)
食品廃棄物の処理方法に焦点を当てた独自の取り組みで成功を収めています。
- 法律・制度: 2005年以降、食品廃棄物の埋め立て処分を禁止しました7)。
- 「従量制」の導入: 2013年以降、ソウルなどの都市で住民が排出する食品廃棄物の量に応じて手数料を支払う「食品廃棄物従量制」を導入し、国民が自ら排出量を減らすインセンティブを生み出しています。
4. 中国 (China)
外食時の食べ残しや大食い動画の規制など、消費者行動への規制に焦点を当てています。
- 法律(2021年):反食品浪費法8)レストランが客に過剰な食べ残しがあった場合、処分費用を請求することを許可しています。
- 大量の注文を奨励・誘導した飲食店に対して罰金を科すことがあります。
- 社会的な影響を考慮し、大食い動画の配信を禁止しました。
5. スペイン (Spain)
サプライチェーン全体での食品ロス対策を義務付けています。
- 法律(2025年施行)9): 食品サプライチェーンのすべての事業者に対し、食品ロスを防止・削減するための防止計画の作成を義務付けました。また、消費可能なものの見栄えが悪い食品を割引販売することなども奨励しています。
6. 日本 (Japan)
- 法律(2001年):食品リサイクル法: 食品関連事業者に対して、食品廃棄物を肥料や飼料などに再生利用することを義務付けています。
- 法律(2019年):食品ロス削減推進法10): 国、自治体、事業者、消費者それぞれの責務を明確にし、食品ロス削減を国民運動として推進しています。罰則よりも推進と啓発に重点を置いた法律です。
食卓から未来を変えるために
食料生産を持続可能にするとは、単に環境に優しい手法を選ぶことではありません。
それは、短期的な利益を追求する「死の経済」の論理から完全に脱却し、人類の生存と繁栄を最優先する「命の経済」へと社会全体のパラダイムを転換することを意味します。
この転換は、政府や巨大企業だけが担うものではありません。
私たちは、短期的な安さと便利さを優先し続けますか? それとも、未来の健康と環境を守る選択をしますか?
今日、あなたが選ぶ一つの野菜、一つのお米が、実は「命の経済」に投票している行為だと考えてみてください。
食料生産の変革は、単なる産業の問題ではなく、人類の未来そのものを決定する「命の選択」です。
私たちは皆、食卓からこの大きな変革に参加できます。

【参考資料】
1)ジャック・アタリ著 林昌宏/坪子理美訳「命の経済 – パンデミック後、新しい世界が始まる」(2020)プレジデント社
2)農林水産省「食品ロスの現状を知る」
3)世界の食料問題
4)消費者庁「事例 フランスのファッション業界の取組」
5)参議院「フランス・イタリアの食品ロス削減法」
6)参議院「イタリアの食品寄付による廃棄物税減額制度」
7)消費者庁「韓国における食品寄附の実態及び食品廃棄物・ 食品ロス削減 …」
8)一般財団法人自治体国際化協会「中国のフードロス対策」
9)ジェトロ(日本貿易振興機構)「食品ロス防止法が施行、罰則も導入(スペイン) | ビジネス短信」
10)消費者庁「食品ロスの削減の推進に関する法律等」
【協会関連記事】
「農」しなくて大丈夫? ~自給的農業のススメ~