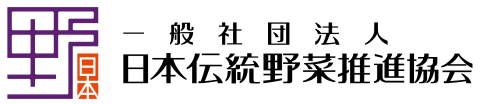日本の伝統果樹一覧 ~柿(かき)編~
目次
- 10月26日は柿の日
- バリエーション広がる柿レシピ
- 柿の発祥地は中国・長江流域
- 甘柿の誕生は鎌倉時代
- 渋味による柿の分類
- 主な柿の在来種
- 妙丹柿(みょうたんがき)
- 会津みしらず柿(あいづみしらずがき)
- 禅寺丸(ぜんじまる)
- 平核無柿(ひらたねなしがき)
- 突核無柿(とつたねなしがき)/ベビーパーシモン
- 三社柿(さんじゃがき)
- 水島柿(みずしまがき)
- 紋平柿(もんぺいがき)
- 百目柿(ひゃくめがき)
- 蜂屋柿(はちやがき)
- 堂上蜂屋柿(どうじょうはちやがき)
- 市田柿(いちだがき)
- 富有柿(ふゆうがき)
- 治郎/次郎柿(じろうがき)
- 西村早生(にしむらわせ)
- 筆柿(ふでがき)
- 蓮台寺柿(れんだいじがき)
- 鶴の子柿(つるのこがき)
- 御所(ごしょ)
- 刀根早生(とねわせ)
- 法蓮坊柿(ほうれんぼうがき)
- 花御所(はなごしょ)
- 西条柿(さいじょうがき)
- 横野柿(よこのがき)
- 愛宕柿(あたごがき)
- 葉隠柿(はがくしがき)
- 伽羅柿(きゃらがき)
10月26日は柿の日
「柿食えば鐘がなるなり法隆寺」 しみじみと日本の秋を感じさせるすてきな俳句ですね。
この有名な句は、俳人・正岡子規が1895(明治28)年10月26日に奈良旅行の際に詠んだ句です。これにちなんで全国果樹研究連合会カキ部会は、2005年に10月26日を「柿の日」に制定しました。
澄んだ空の下、色づいた葉の間から、たわわに実った柿が顔をのぞかせる景色は、古くから秋の象徴です。この時期ならではの美しい風景に思いを馳せながら、今回は、柿の品種についてご紹介したいと思います。

バリエーション広がる柿レシピ
柿は、基本は生食で、そのまま食べたり、干し柿やあんぽ柿として食べることが多いですが、その甘みや食感は料理に新しい可能性をもたらしています。
柿のレシピの定番は、正月料理にも使われる「柿なます」や、柿を豆腐や野菜と和える「柿の白和え」で、柿の甘みが良いアクセントになっています。干し柿は、渋柿を乾燥させて作る伝統的な保存食でおなじみです。
ですが、近頃は、柿レシピも広がりを見せており、まだ、熟していない硬めの柿を薄くスライスして揚げる「柿の天ぷら」や、干し柿にバターやチーズと合わせたりして、新しい味わいが広がっています。
海外では柿をフルーツとしてだけでなく、料理のアクセントとして使うレシピが多く見られます。
葉物野菜やチーズ、生ハムなどと一緒にサラダにすると、柿の甘さが引き立ちます。ドレッシングはバルサミコ酢やオリーブオイルがよく合います。柿とルッコラ、ゴルゴンゾーラチーズ、クルミを組み合わせたサラダは、甘み、苦味、塩味、香ばしさのバランスが絶妙です。バルサミコ酢やオリーブオイルをかけるだけで、おしゃれな一品になります。カリカリに焼いたパンに、クリームチーズを塗り、薄切りにした柿と生ハムを乗せるブルスケッタは、塩味と甘みの組み合わせが良く、ワインのおつまみにぴったりです。
また、肉料理の付け合わせとして、焼いた豚肉や鶏肉の上に、柿のスライスを乗せたり、柿とハーブを煮詰めたソースを添えたりします。柿の甘みが肉の旨みを引き立て、さっぱりとした後味にしてくれます。
飲み物・スイーツなどでは、柿をバナナや牛乳、ヨーグルトなどと一緒にミキサーにかけると、まろやかな甘みのスムージーになります。手軽で栄養満点な朝食になります。ショウガやシナモンを加えると、より風味豊かになります。
柿が熟して柔らかくなったら、煮詰めてジャムにしてもよいですね。パンやヨーグルトに添えるのはもちろん、肉料理のソースとしても使えます。洋菓子のタルトやパウンドケーキの具材にすれば、加熱によって甘みが増し、しっとりとした食感が楽しめます。
このほか、柿の葉にはビタミンCやタンニンが豊富に含まれていることから、お茶にして「柿の葉茶」として飲まれることもあります。
柿は、生でも加熱しても美味しい用途の広い果物です。硬さや熟し具合に合わせて、さまざまなレシピに挑戦してみるのも楽しいと思います。



柿の発祥地は中国・長江流域
柿は、古くから東アジアで栽培されてきた果物です。学名は、Diospyros kaki(ディオスピロス・カキ)。ちゃんと日本語の「kaki」がつけられており、海外のスーパーでも「KAKI」の表記で販売されいます。しかし、2018年の世界の柿の生産量は、中国が圧倒的なシェアを占めており、日本は4位でした。
柿の歴史は、大きく分けて東アジアでの起源と栽培、そして世界への広がりという二つの段階に分けられます。柿の原産地は中国の長江流域だと考えられています。約1,000年前にはすでに食用として栽培されており、その果実の美しさから詩歌にも詠まれてきました。日本へは、奈良時代に中国から伝わったとされ、平安時代にはすでに広く栽培されていたようです。
甘柿の誕生は鎌倉時代
柿の品種は日本全国に1,000種類以上あるとされており、地域固有の在来品種も多数存在します。
柿は、中国、朝鮮半島、そして日本に分布する果樹です。もともと中国や朝鮮半島にあったものは渋柿がほとんどでした。日本では、柿の品種改良が盛んに行われ、長い年月をかけて甘柿が独自に生まれ、多くの在来品種が誕生しました。鎌倉時代には日本最古の甘柿とされる「禅寺丸(ぜんじまる)」が誕生しました。
全国的に広く栽培されるようになったのは、明治時代に全国的な調査が行われ、優れた品種が各地に広まったことによります。現在の甘柿の代表品種である「富有(ふゆう)」や「次郎(じろう)」が発見されたのも明治時代で、この頃から日本全国へと広まり、多くの品種が地域を越えて栽培されるようになりました。現在でも、品種改良が行われており、新しい品種も生まれています。
渋味による柿の分類
柿の分類は、渋みを感じるかどうか、そしてその渋みがどう抜けるかによって、主に4つのタイプに分けられています。
1.完全甘柿(かんぜんあまがき)
成熟する過程で自然に渋みが抜け、種子の有無に関わらず甘くなるタイプです。渋抜きをしなくてもそのまま食べられます。
代表品種: 富有(ふゆう)、次郎(じろう)、御所(ごしょ)
2.不完全甘柿(ふかんぜんあまがき)
種子が入った部分だけ渋みが抜けて甘くなります。果肉にゴマのような黒い斑点が現れるのが特徴です。種子が少ないと渋みが残ることがあります。
代表品種: 禅寺丸(ぜんじまる)、筆柿(ふでがき)
3.完全渋柿(かんぜんしぶがき)
成熟しても渋みが抜けず、果実全体に強い渋みが残るタイプです。渋抜きをしないと食べられません。渋抜きをすると甘くなります。
代表品種: 平核無(ひらたねなし)、蜂屋(はちや)、西条(さいじょう)
4.不定形(ふていけい)
不完全渋柿とも呼ばれ、渋が抜けるかどうかが不安定なタイプです。この分類は専門的で、一般的には上記の3つに集約されることが多いです。
これらの分類は、柿の品種を選ぶ際の重要なポイントになります。たとえば、そのまま手軽に食べたいなら完全甘柿を、干し柿や渋抜きを楽しみたいなら渋柿を選ぶのが一般的です。
主な柿の在来種
ここでは、日本の柿の在来種といえる品種を紹介したいと思います。
果樹は、商品名として地域ブランドを冠することも多く、商品名=品種名ではないこともよくありますが、柿の場合も、元々の発祥地と現在の主要な生産地は、必ずしも一致していません。たとえば、よく知られている「富有柿(ふゆうがき)」は、岐阜県発祥ですが、今では福岡県でも盛んに栽培されています。また、「百目柿(ひゃくめがき)」のように、品種は同じでも、地域によって「江戸柿(えどがき)」、「富士柿(ふじがき)」など名前が変わることもあります。
生産地が変われば、その土地の気候や加工方法によって、それぞれ異なる味わいや食感が生まれるので、その違いを愉しむのも一興です。日本の伝統的な柿の品種は非常に多く、それぞれ特徴があります。ここでは、特に代表的な在来品種をご紹介していきます。
妙丹柿(みょうたんがき)
【発祥地】青森県三戸郡(さんのへぐん)南部町(なんぶちょう)
【主な生産地】青森県
【渋味の分類】不完全渋柿(渋抜きが必要)
【由来】「南部柿(なんぶがき)」とも呼ばれます。導入時期は定かではありませんが、1948(昭和23)年に発行された『果樹園芸学上巻(菊池秋雄著)』のなかに、「三戸郡の妙丹は200年前後の老木は少なくない」と記述されていることから、少なくとも250年以上前から栽培されていたと推定されます。一説には、「南部の殿様が参勤交代の帰り道、会津から枝を大根に挿して持ち帰った」とされ、持ち帰ったいくつかの枝のひとつが妙丹柿の先祖だと伝えられています。
【特徴】長宝珠形をした小型の渋柿。重さは70~80g。高さ5~6㎝。糖の含有量が多く、果肉は粘質。タネがほとんどできず、繊維質も少ない。
【料理】強い渋みがあるため、渋抜きをしてから食べます。渋抜きをすることで、濃厚な甘みと、とろけるような、なめらかな食感が生まれます。肉質がなめらかで、干し柿に適しており、竹串に刺して吊す独特の方法で、じっくりと自然乾燥させます。もともとの濃厚な味が、優しく深みがある甘味となって、さらに美味しくなります。
会津みしらず柿(あいづみしらずがき)
【発祥地】福島県二本松市小浜
【主な生産地】会津若松市門田町御山を中心とする区域
【渋味の分類】完全渋柿(渋抜きが必要)
【由来】戦国時代の天正年間に、福島県二本松市小浜を支配していた大内氏が、小浜にある西念寺の住職・夕安和尚を中国に派遣し、その際に、持ち帰ったとされます。当時は甘柿と渋柿があったとのこと。大内氏らが小浜から会津へ逃れる際に、西念寺の柿も持っていき、それが身不知柿のもととなりました。しかし、会津では甘柿は根づかず、渋柿が広がりました。漆器が盛んな会津では、渋(しぶ)を多用するため、柿は盛んに栽培されました。柿渋は、漆器のほかにも紙や傘、防水などにも使用され、やがて全国でも有数の柿の産地として知られるようになりました。
名前の由来は、美味しさから3つの説が伝えられています。一つ目は、枝が折れそうなほどにたくさんの大粒の実をつけるから身の程知らずな柿という説。二つ目は、将軍に献上したところ、「未だかかる美味しい柿を知らず(これほど美味しい柿はいまだかつて知らない)」と大いに賞賛されたという説。三つ目は、あまりにも美味しいので、我が身も考えずに食べすぎてしまう柿だという説です。
【特徴】果実は約250gと大きめで、扁平な四角い形をしています。渋抜きをすることで、とろけるような滑らかな食感と、上品で濃厚な甘みが楽しめます。
【料理】渋抜きをしてそのまま食べるのが一般的です。地元では、正月のお飾りや贈答品としても重宝される地域に根差した柿です。伝承では豊臣秀吉に献上されたという話も残っています。
【時期】10月下旬~11月下旬
JA会津よつば「みしらず柿」
會津物語「会津 身不知柿の由来」

禅寺丸(ぜんじまる)
【発祥地】神奈川県川崎市麻生区王禅寺
【主な生産地】神奈川県川崎市麻生区
【渋味の分類】不完全甘柿(種が入ると渋が抜ける)
【由来】鎌倉時代の1214(建保2)年に神奈川県川崎市麻生区王禅寺の山中で、突然変異による甘柿が発見されました。日本で最も古い甘柿であると言われています。原木は国の登録記念物に登録されています。
【特徴】サイズは、小ぶりで、丸く、重量は約100g程度です。小ぶりの割りに種が大きく、果肉部分が少ないのが特徴です。種が入ると渋が抜けて甘くなり、果肉にゴマのような黒い斑点(ゴマ)ができます。味は、強い甘みと、独特の芳醇な香りがあります。種がないと渋みが残ることがあります。
【料理】渋が抜けているものは、そのまま生で食べられます。渋が残ったものは、干し柿に加工されることもあります。その甘みと香りを生かして、和菓子や洋菓子の材料としても利用されます。
【豆知識】禅寺丸は、江戸時代から盛んに栽培され、特に東京方面に出荷されていました。一時は栽培が減少しましたが、近年は地元の特産品として再び見直され、栽培が続けられています。

平核無柿(ひらたねなしがき)
【発祥地】新潟県
【主な生産地】新潟県、山形県、青森県など
【渋味の分類】完全渋柿(渋抜きが必要)
【由来】「庄内柿 (平核無柿)」のもともとの原木が新潟市秋葉区古田(旧 新津市)で発見され、昭和 37年に「八珍柿」の原木として新潟県文化財に指定されています。推定樹齢は370年を超えていますが、今でも実をつけるそうです。
名前の由来は、その名の通り、平らな(扁平な)形で種がない(核無し)ことにあります。
【特徴】サイズ: 200g~250gの中ぶりなサイズです。他の柿には珍しい、扁平で四角い箱のような形をしています。強い渋みがあるため、渋抜きをしてから食べます。渋抜きされた果肉は、緻密でとろけるような滑らかな食感が特徴です。上品でまろやかな甘みが楽しめます。
【料理】焼酎や炭酸ガスなどを使って渋抜きをした後、そのまま食べられます。また、渋が抜けやすく、肉質が良いため、干し柿の原料としても使われます。
【豆知識】「平核無」は、その食べやすさから、全国の主要な渋柿品種となっています。栽培地域によって独自のブランド名で呼ばれることが多く、山形県の「庄内柿」や新潟県の「おけさ柿」は、この平核無柿のブランド名です。

突核無柿(とつたねなしがき)/ベビーパーシモン
【発祥地】新潟県佐渡島
【主な生産地】新潟県佐渡島、岐阜県
【渋味の分類】完全渋柿(渋抜きが必要)
【由来】佐渡市で「平核無」の枝変わりとして発見されました。果実の先端がわずかに尖っている(突起している)ことから、この名が付けられました。
【特徴】サイズは、20g〜30gと、通常の柿よりもはるかに小さいのが特徴です。平核無と同様に扁平な四角い形をしていますが先端がわずかに尖っています。強い渋みがあるため、渋抜きをしてから食べます。果汁が多く、とろけるような滑らかな食感が楽しめます。
【料理】渋抜きをしてからそのまま食べます。その小さくかわいらしい見た目から、「ベビーパーシモン」という愛称で呼ばれることもあります。アレンジとして、丸ごとシロップ漬けにしたり、デザートの飾り付けに使われたりすることもあります。
【豆知識】突核無は、もともと佐渡島で発見された柿ですが、岐阜県では近畿大学との共同研究により、「ベビーパーシモン」という名称でブランド化され、栽培が拡大しています。

三社柿(さんじゃがき)
【発祥地】富山県南砺市福光
【主な生産地】富山県南砺市福光・城端地域
【渋味の分類】完全渋柿(渋抜きが必要)
【由来】約300年以上前から栽培されている産地固有の希少品種です。三社柿は炭疽病に極めて弱いですが、生産地域は赤土の土壌だったため、むしろ栽培に適していたとされます。干柿の製法は、江戸時代の慶長(1596~1615)年間に美濃の国(岐阜県)から伝えられ、加賀3代藩主前田利常公が干柿づくりを奨励したことが、今日の干柿の基になっています。
【特徴】形は釣鐘型。サイズは大きなもので直径10cm、重さ350gにもなります。果肉はしまっています。一般的な渋柿よりも渋みが非常に強いですが、この渋みを取り除くことで干し柿にした際の濃厚な甘みにつながります。三社柿で作る富山干し柿・あんぽ柿は、2020年に農林水産省の定める地理的表示(GI)保護制度に登録されました。
【料理】400年以上の歴史の中で培われた高度な技術により、渋柿から甘みだけを引き出す干し柿が作られています。
越中とやま食の王国
農林水産省「富山干柿・あんぽ柿(とやまほしがき・あんぽがき)」
水島柿(みずしまがき)
【発祥地】富山県射水市(旧:新湊市片口)
【主な生産地】富山県を中心に、福井県や石川県などの北陸地方
【渋味の分類】不完全甘柿
【由来】富山県新湊市片口高場の前川弥三郎という人が百数十年前に改良したと言われています。
【特徴】丸みのある形で、外皮は鮮やかな橙色です。芳醇な香りが特徴。果肉は、水分が多く、食感がしっかりしています。果肉には「ゴマ」と呼ばれる黒い斑点が出ます。平均糖度は16.7度で、富有柿の14.8度よりも高い傾向がみられます。寒冷地でも渋が残りづらく、10月中旬から下旬にかけて収穫されます。収穫時期は、10月中旬~下旬が目安ですが、地域や環境によって1ヶ月程度前後します。
【料理】不完全甘柿で、受粉の具合によって渋が残ることがあります。まれに渋が残る場合でも、芯のスポンジ状の部分を取り除けば食べることができます。水島柿の葉は、茶の代わりとして加工され飲まれることもあります。
紋平柿(もんぺいがき)
【発祥地】石川県能美市
【主な生産地】石川県
【渋味の分類】完全渋柿(渋抜きが必要)
【由来】江戸時代後期(1800年頃)宝達集落(上野地区)の農家が屋根葺きの作業中に飛んできた柿の種を家の前に植えたところ、大きな渋柿ができたので渋抜きして食べたら、とても美味しかったため、この柿の木を母樹として、宝達山麓の周辺集落に広まっていきました。江戸時代に加賀藩主の前田公に献上した際、この柿を栽培した農家の名前が「紋平」であったことに由来すると言われています。
【特徴】大きさは、中〜大ぶりなサイズです。やや扁平で、四角い形をしています。強い渋みがあるため、渋抜きをしてから食べます。とろけるような滑らかな食感と、上品でまろやかな甘みが特徴です。
【料理】渋抜きをしてからそのまま食べます。渋抜き後の食感が良いため、干し柿の原料としても使われます。
【豆知識】石川県の一部地域では、柿の葉でシャリと具材を包んだ「柿の葉すし」が作られます。紋平柿もその材料として使われることがあります。柿の葉寿司で有名な奈良や和歌山では酢飯にタネを合わせて柿の葉で包むのに対して、石川では柿の葉の上に酢飯を置き、タネだけでなく桜海老、紺海苔、生姜などを添えて、葉で包むこと無く桶に重ねて食されます。起源は非常に古いようで、前田利家が加賀に入場した折には、領民は柿の葉寿司で歓待したエピソードは有名だそうです。
百目柿(ひゃくめがき)
【発祥地】明確な発祥地は特定されていませんが、山梨県をはじめとする各地で古くから栽培されてきた在来品種です。
【主な生産地】福島県、宮城県、山梨県、埼玉県、愛媛県ほか
【渋味の分類】完全渋柿(渋抜きが必要)
【由来】名称は、果実の重さが約375g(百匁)にもなることに由来すると言われています。
【特徴】サイズは、非常に大きく、500gを超えることもあります。釣鐘のような形で、先端が尖っているのが特徴です。果肉はしっかりとしており、干し柿にするともっちりとした食感になります。
【料理】干し柿に加工されることが最も多いです。山梨県の伝統的な干し柿「枯露柿(ころがき)」この品種を原料としています。焼酎などを使って渋抜きをすれば、まろやかな甘みの生食柿としても楽しめます。
【豆知識】「百目柿」は、各地で古くから栽培されており、別名がいくつもあります。山梨県では「甲州百目(こうしゅうひゃくめ)」と呼ばれています。奈良や京都など近畿地方では「江戸柿(えどがき)」の名称で呼ばれ、奈良県西吉野の特産品となっています。岐阜県美濃加茂市蜂屋町では「蜂屋柿(はちやがき)」として、古くから作られており、この地の特産となっています。またこの柿を使った干し柿が「堂上蜂屋柿(どうじょうはちやがき)」として全国的に有名です。福島県、宮城県でも「蜂屋柿」と呼ばれています。愛媛県では「富士柿(ふじがき)」と呼ばれます。富士柿は1927年愛媛県八幡浜市の弁上三郎左エ門氏が発見した蜂屋柿の変異種とされています。同地の特産として栽培され、収穫後35度の焼酎で5日間じっくりと渋を抜くアルコール脱渋法のみを使うとされています。逆さにすると富士山に似て大きいことから命名されたそうです。それぞれ品種は同じ甲州百目ですが、各地域で独自の加工法が発達し、特産品として親しまれています。

蜂屋柿(はちやがき)
【発祥地】岐阜県美濃加茂市蜂屋町
【主な生産地】岐阜県、福島県、宮城県など
【渋味の分類】完全渋柿(渋抜きが必要)
【由来】発祥地である岐阜県美濃加茂市蜂屋町の地名に由来します。品種としては百目柿です。
【特徴】サイズは非常に大きく、500gを超えるものもあります。先端が尖った釣鐘のような形をしています。果肉は、繊維が少なく、肉質がやわらかいのが特徴です。栽培が難しく、生産量が少ないため、希少な品種とされています。
【料理】干し柿の代表的な品種で、ほとんどが干し柿に加工されます。特に岐阜県では、伝統的な製法で「堂上蜂屋柿(どうじょうはちやがき)」という高級な干し柿が作られています。これは、美しい飴色と、もっちりとした食感、そしてとろけるような濃厚な甘みが特徴です。その品質の高さから、高級な贈答品として扱われます。
堂上蜂屋柿(どうじょうはちやがき)
【発祥地】岐阜県美濃加茂市蜂屋町
【主な生産地】岐阜県美濃加茂市
【渋味の分類】完全渋柿(渋抜きが必要)
【由来】鎌倉時代、朝廷に仕える貴族(堂上家)に献上されていたことから、この名がついたとされています。また、発祥地の地名「蜂屋」も名称の一部となっています。
【特徴】大きさが非常に大きく、500gを超えるものもあります。先端が尖った釣鐘のような形をしています。果肉は、繊維が少なく、肉質がやわらかいのが特徴です。蜂屋柿は栽培が難しく、生産量が少ないため、希少な品種とされています。
【料理】堂上蜂屋は、ほとんどが干し柿に加工されます。美濃加茂市では、伝統的な製法で「堂上蜂屋柿」というブランドの干し柿が作られており、美しい飴色と、モッチリとした食感、そしてとろけるような濃厚な甘みが特徴です。その品質の高さから、高級な贈答品として扱われます。
市田柿(いちだがき)
【発祥地】長野県下伊那郡高森町市田
【主な生産地】長野県下伊那郡
【渋味の分類】完全渋柿(渋抜きが必要)
【由来】発祥地である長野県下伊那郡高森町市田の地名に由来します。1921(大正10)年に市田村の篤農家たちが、在来種の渋柿(焼柿)を「市田柿」と称して大都市の市場に出荷をしたのが始まりです。地域団体商標にも登録されており、特定の地域で栽培・加工されたものだけが「市田柿」を名乗ることができます。
【特徴】大きさは、20g〜30gほどの小ぶりなサイズです。細長い釣鐘型をしています。
干し柿にすると、上品な甘さと、モッチリとした独特の食感になります。表面に白い粉(柿霜)がふくことで、美しい飴色になります。
【料理】市田柿といえば干し柿であり、ほぼすべての果実が干し柿に加工されます。ほかには、その濃厚な甘みと上品な風味から、和菓子の材料としても使われます。最近では、干し柿をバターやチーズと合わせてサンドにするレシピも人気です。

富有柿(ふゆうがき)
【発祥地】岐阜県瑞穂市(旧巣南町)
【主な生産地】岐阜県、奈良県、福岡県など
【渋味の分類】完全甘柿
【由来】富有は、江戸時代末期に岐阜県の居倉村の「居倉御所(いくらごしょ)」と呼ばれていた柿が起源になります。居倉御所(御所柿)は、小倉家によって栽培されていた柿で、その中で、味・色・形状に優れている柿に着目した居倉の福嶌才治(ふくしまさいじ)氏が、1884(明治17)年に、この接穂を得て増殖し、1892(明治25)年に、新品種としてに「富有」と命名したのが始まりです。この柿を栽培した人が「豊かで裕福になるように」との願いを込めて「富有」と名付けられたと言われています。「富有」の母木が岐阜県瑞穂市の市指定天然記念物として保存されています。
【特徴】大きさは250g〜350g程度の中ぶりなサイズです。やや扁平で、丸みを帯びた、ふっくらとした形をしています。甘柿の王様と呼ばれるほど、糖度が高く強い甘みがあります。果汁が豊富で、柔らかく、とろけるような滑らかな食感が特徴です。現在も生産量でトップクラスを誇ります。
【料理】その甘みと柔らかさを楽しむため、そのまま生で食べるのが最も一般的です。柿の自然な甘みが豆腐や野菜とよく合い、和え物にしても美味しくいただけます。また、サラダ、生ハムやチーズなどと組み合わせると、柿の甘さが引き立ち、おしゃれな前菜になります。
【豆知識】「治郎/次郎(じろう)柿」と並ぶ甘柿の代表的な品種です。次郎が硬めの食感なのに対し、富有は柔らかい食感を持つため、好みが分かれます。

治郎/次郎柿(じろうがき)
【発祥地】静岡県森町
【主な生産地】静岡県、愛知県、福岡県など
【渋味の分類】完全甘柿
【由来】江戸後期の弘化年間(1844年~1847年)頃に森町村五軒丁の「松本治郎」が太田川の川原で柿の幼木を見つけ、これを持ち帰り自宅に植えたのがはじまりと言われています。富有柿よりも早く栽培が始まったとされています。
【特徴】富有柿に比べてやや大きく、重いものだと500gを超えることもあります。形状は、四角く扁平な形をしており、果実の側面に4本の溝があるのが特徴です。糖度が高く、強い甘みがあります。果汁は比較的少なめです。緻密で硬めの果肉が特徴で、サクッとした歯ごたえが楽しめます。
【料理】その硬い食感を活かすため、そのまま生で食べるのが最も一般的です。シャキシャキとした食感が、サラダのアクセントとしても人気です。
【豆知識】「富有」と並び称される甘柿の代表的な品種です。富有柿が柔らかくジューシーなのに対し、次郎柿は硬くてサクサクとした食感を持つため、好みが分かれます。

四ツ溝柿(よつみぞがき)
【発祥地】静岡県東部(愛鷹山麓)
【主な生産地】静岡県駿東郡長泉町、富士宮市など
【渋味の分類】完全渋柿(渋抜きが必要)
【由来】静岡県静岡県駿東郡長泉町の愛鷹(あしたか)山周辺に自生していた渋柿の一種とされます。柿の実の側面に、深くはっきりとした4本の溝があることに由来します。
【特徴】大きさは、90g~140gと、小ぶりなサイズです。四角く扁平な形をしており、果実の側面に4本の深い溝があるのが特徴です。強い渋みがあるため、渋抜きをしてから食べます。果肉は緻密で、とろけるような滑らかな食感が特徴です。
【料理】焼酎や炭酸ガスなどを使って渋抜きをした後、そのまま食べられます。渋が抜けた後の食感と甘みが良いため、干し柿の原料としても使われます。
西村早生(にしむらわせ)
【発祥地】滋賀県大津市坂本
【主な生産地】福岡県、滋賀県など
【渋味の分類】不完全甘柿(種が入ると渋が抜ける)
【由来】1953年に西村弥蔵氏の柿園で偶発実生として見つかり、1960年に「西村早生」と名付けられました。富有柿と赤柿の自然交雑によって生じたとされます。「早生」は、収穫時期が他の品種より早いことを意味し、9月下旬~10月上旬に熟すとされます。
【特徴】大きさは220gほどです。やや扁平な丸みを帯びた形をしています。味と食感は、種子の有無によって異なります。種が入っている場合は、自然に渋が抜け、サクサクとした歯ごたえと甘みが楽しめます。種がない場合は、渋みが残るため、渋抜きが必要です。安定して甘柿を収穫するために、富有柿などの受粉樹として植えられることもあります。
【料理】渋が抜けているものは、そのサクサクとした食感を活かしてそのまま食べられます。

筆柿(ふでがき)
【発祥地】愛知県額田郡(ぬかたぐん)幸田町(こうたちょう)
【主な生産地】愛知県額田郡幸田町
【渋味の分類】不完全甘柿
【由来】「筆柿」の名前の由来は、筆の穂先に似た、細長い独特の形をしていることにあります。また、ほかにも、旧盆の頃に実ることから「盆柿(ぼんがき)」、その独特な形から、「珍宝柿」(ちんぽうがき)」の名で呼ばれてきました。
その歴史は古く、徳川時代より町南西部の農家の庭先で栽培されていたと言われています。もっとも古い木は、幸田町上六栗地内には樹齢300年を超える筆柿の木が複数確認されており、その中には樹齢350年と伝わるものもあります。
【特徴】「不完全甘柿」と呼ばれる珍しい種類の柿で、一本の木に甘柿と渋柿の両方が実ります。種が入ると渋が抜けて甘くなり、果肉にゴマのような黒い斑点(ゴマ)が現れます。種が少ないと渋みが残ることがあります。強い甘みと、モッチリとした食感が特徴です。形状は、ほかの柿には見られない細長い円錐形が特徴です。
【料理】渋が抜けているものはそのまま生で食べられます。渋が残ったものは、干し柿に加工されることもあります。サラダや和え物、また、その独特の形と甘みを生かして、料理の彩りとしても使われます。
幸田町「特集➀筆柿」
幸田町観光協会「幸田町筆柿ものがたり」
JAあいち三河「管内の農産物 柿」

蓮台寺柿(れんだいじがき)
【発祥地】三重県伊賀市蓮台寺地区
【主な生産地】三重県伊賀市
【渋味の分類】完全渋柿(渋抜きが必要)
【由来】発祥地である三重県伊賀市蓮台寺地区の地名に由来します。300年ほど前から、この地域で栽培されてきた在来品種です。品種保存の目的で1958(昭和33)年に伊勢市の天然記念物に指定されています。「みえの伝統果実」にも選定されています。
【特徴】大きさは中〜大ぶりなサイズです。やや扁平な四角い形をしています。強い渋みがあるため、そのままでは食べられません。干し柿に加工することで、甘みが凝縮され、モッチリとした食感が生まれます。
【料理】ほとんどが干し柿に加工されます。伊賀地方では、忍者が携帯食として利用していたという伝承も残る歴史ある干し柿として知られています。地元ホテルでは、旬の時期に、入荷状況に合わせて、柿のジュレとクリームチーズ、伊勢海老を合わせたリゾット、柿の甘みを引き出すソースなど蓮台寺柿の特性を生かした料理が提供されることがあります。柿羊羹やシフォンケーキ、柿の葉を
【豆知識】蓮台寺柿は栽培が難しく、生産量が少ないため、「幻の柿」とも呼ばれるほど希少な品種です。地元の市場を中心に9月中旬から11月にかけて出荷販売されます。
伊勢市「蓮台寺柿」
季刊誌「志摩時間」 歴史が息づく神都の蓮台寺柿詳細

鶴の子柿(つるのこがき)
【発祥地】京都府綴喜郡宇治田原の特産品
【主な生産地】京都府、埼玉県春日部市
【渋味の分類】完全渋柿(渋抜きが必要)
【由来】その形が、鶴の卵に似ていることから名付けられたと言われています。
鶴の子柿を原料にした干し柿「古老柿(ころがき)」には、宇治田原町にある禅定寺の十一面観音が少女の姿に化けて干し柿の製法を教えたという伝説があり、その「娘の柿」という意味合いで「古老柿(または孤娘柿)」と呼ばれるようになったと伝えられています。
【特徴】一般的に果実の大きさが40g〜50g程度と小ぶりで、筆柿を小さくしたような細長い形をしています。鶴の子柿は、ほとんどが干し柿にさなります。11月中旬から下旬にかけて収穫され、12月中旬頃に「古老柿」として出荷されます。
【料理】吊るさない干し柿である伝統的な「古老柿」の原料として有名で、宇治田原の独特の景観である「柿屋」で干し柿にされます。
御所(ごしょ)
【発祥地】奈良県御所市(ごせし)
【主な生産地】奈良県御所市、和歌山県、鳥取県など
【渋味の分類】完全甘柿
【由来】日本の甘柿の初期の品種の一つです。その美味しさから宮中や将軍家に献上されていたことに由来し「御所」と呼ばれたとされます。また、「御所」が天皇に畏れ多いことから「五所柿」や「やまとがき」、「ひらがき」などとも呼ばれたそうです。
果肉は糖度が17~20度と高く、粘り気のある肉質であることから「天然の羊羹」と呼ばれています。
1645(正保2)年)に、俳人の松江重頼(まつえしげより)が著した俳諧論書「毛吹草(けふきぐさ)」では、大和の名産品として「御所柿」を挙げています。
1697年(元禄10年)に、江戸時代後期の医師・本草家である人見必大(ひとみひつだい)が著した本草所「本朝食鑑(ほんちょうしょっかん)」には、御所柿のことが「その味わい絶美なり。もって上品となす」と記されています。
【特徴】形状は、小ぶりで、やや扁平な形をしています。緻密で柔らかい果肉と、強い甘み、豊かな風味が特徴です。生理落果しやすく、栽培が難しく、生産量が少ないため、市場にはあまり出回らない希少な品種です。
【料理】甘みが非常に強いため、そのまま生で食べるのが最も一般的です。
刀根早生(とねわせ)
【発祥地】奈良県天理市
【主な生産地】奈良県、和歌山県、福岡県など
【渋味の分類】完全渋柿(渋抜きが必要)
【由来】1959年に、平核無柿(ひらたねなしがき)の枝変わり(突然変異)として、奈良県の刀根淑民(とねよしたみ)氏によって発見されました。親品種である平核無よりも早く収穫できることから「早生」という名前が付けられました。
【特徴】平核無よりもやや大きく、重いものだと300gを超えることもあります。平核無と同様に、扁平で四角い形をしています。種がなく、渋抜きされた果肉は、緻密でとろけるような滑らかな食感が特徴です。
【料理】渋抜きをしてからそのまま食べます。渋抜き後の食感が良いため、あんぽ柿の原料としても使われます。
【豆知識】刀根早生は、親品種である平核無柿の優れた性質(種なし、食感の良さ)を受け継ぎつつ、早期に出荷できるという利点を持つため、市場で非常に高く評価されています。
東部地域/奈良県公式ホームページ
農林水産・食品産業技術振興協会「刀根淑民のカキ品種『刀根早生』」

法蓮坊柿(ほうれんぼうがき)
【発祥地】奈良県五條市西吉野町
【主な生産地】奈良県五條市
【渋味の分類】完全渋柿(渋抜きが必要)
【由来】奈良県の西吉野村(現:五條市)に古くから自生する在来品種で、その歴史は300年にも及ぶと言われています。
【特徴】大きさは、90g前後と小ぶりで、縦長の形をしています。ヘタ(ガク)の部分が果実に張り付かず、上に向かって咲いているように立っているのが特徴です。
渋抜きが難しいため、ほとんどが干し柿に加工されます。干し柿にすることで、濃厚な甘みが凝縮され、モッチリとした食感になります。
【料理】ほとんどが干し柿に加工され、お正月のお飾りなどにも使われます。渋皮付きの栗餡と合わせた和菓子など、地元の特産品として加工されます。また、葉は柿の葉寿司にも用いられます。
全国商工会連合会「郷愁の柿」
奈良県五條市「五条の柿だよりNo.013 冬の風物詩 吊るし柿」

花御所(はなごしょ)
【発祥地】鳥取県鳥取市国府町(旧因幡国)
【主な生産地】鳥取県
【渋味の分類】完全甘柿
【由来】江戸時代後期の1780(安永10)年頃に、奈良県から「御所柿」を持ち帰って栽培したことが発祥で、旧:郡家(こおげ)町で200年以上前から栽培されています。鳥取藩主が徳川将軍に献上したという記録も残る歴史ある品種です。1909(明治42)年に、農林省園芸試験場の恩田博士が花御所柿と命名しました。
【特徴】形状は、小ぶりで、やや扁平な形をしています。緻密な果肉と濃厚な甘みが特徴で、とろけるような口当たりです。栽培が難しく生産量が少ないため、「幻の柿」と呼ばれることもあります。
【料理】甘みが非常に強いため、そのまま生で食べるのが最も一般的です。その強い甘みと香りを生かして、タルトやジャムなどのスイーツにも利用されます。

西条柿(さいじょうがき)
【発祥地】広島県東広島市西条町寺家
【主な生産地】広島県、島根県、愛媛県など
【渋味の分類】完全渋柿(渋抜きが必要)
【由来】13世紀中頃、鎌倉の永福寺から東広島市西条町の長福寺に贈られた柿の種子を植えたことが起源と鎌倉時代の「長福寺縁起」に記されています。名前は、発祥地である広島県東広島市西条の地名に由来します。西条柿の原木がこの地にあったことから「西条柿発祥の地」として東広島市の市史跡に指定されています。近畿以西で多く栽培されています。
現在は、島根県が日本一の産地になっています。島根県には毛利氏と尼子氏の覇権争いの際に毛利方から伝わったと言われています。戦場跡には今でも樹齢500年を超える西条柿の木が存在するそうです。
【特徴】約150g〜200gの中ぶりなサイズです。縦に細長く、先端が尖った独特の形をしており、果実の側面に4本の浅い溝があるのが特徴です。渋抜きをすることで、とろけるような食感と、上品でまろやかな甘みが生まれます。
【料理】焼酎などで渋抜きをしてから生食するのが一般的です。渋が抜けた後の食感と甘みが良いため、干し柿にもよく使われる渋柿です。特に、広島県ではこの品種を使った「あんぽ柿」などが作られています。
Wikipedia「西条柿」
柿壺「西条柿(さいじょうがき)のこと」


横野柿(よこのがき)
【発祥地】山口県下関市安岡町横野
【主な生産地】愛媛県、高知県
【渋味の分類】完全渋柿(渋抜きが必要)
【由来】山口県下関市安岡町横野の竹林に自生していた柿で、江戸時代の宝永年間頃に発見されたとされます。原木は1931(昭和6)年に天然記念物として指定されていますが、後に枯れてしまったそうです。名前は発祥地の地名に由来します。明治天皇に献上したことでこの柿が全国に知られることとなりました。
【特徴】大きさは、中〜大ぶりなサイズです。やや扁平な四角い形をしています。強い渋みがあるため、渋抜きをしてから食べます。果肉は緻密で、とろけるような食感が特徴です。
【料理】焼酎などを使って渋抜きをした後、そのまま食べられます。干し柿に加工されることもあります。愛媛では、横野柿を使った「あんぽ柿」が知られています。
愛宕柿(あたごがき)
【発祥地】愛媛県周桑郡石根村(現:西条市小松町)原産
【主な生産地】愛媛県、徳島県、香川県など四国中心に栽培
【渋味の分類】完全渋柿(渋抜きが必要)
【由来】愛宕柿は、別名「まとば」または「伊予蜂屋(いよはちや)」ともいわれる。
「愛宕」の名前の由来は、石根村大頭に京都の貴船神社を勧請した祭事に、京都愛宕産の柿を供えたことから付いたとされる。原木は枯れたが枝が繁殖しており、さらにその柿から1913(大正2)年に、田野村長野(現:丹原町)の櫛部国三郎(くしべ くにさぶろう)が、良系統を選択したのが現在の愛宕柿である。
【特徴】果実は大きめで230g前後。大きなものは300~350gほどです。形は、釣鐘状で、先端が尖っているのが特徴。渋抜きをすることで、緻密でやわらかい果肉と、上品な甘さが楽しめる。
【料理】完全渋柿なので、焼酎や炭酸ガスなどを使って渋抜きをした後、そのまま食べる。脱渋した愛宕柿はポリ袋に密封された状態で店頭に並ぶことが多い。渋を抜いた愛宕はほどよい硬さで適度な甘味があり、さっぱりとした味わい。肉質がやわらかく、渋抜き後の甘みが良いため、干し柿やあんぽ柿(水分を半分くらい飛ばした水気の多い半生タイプの干し柿)の原料としても使われる。特に愛媛県では、正月のお供え物としても利用される地域に根差した品種。
【時期】収穫時期は11月下旬~12月上旬頃。ほかの品種に比べ、収穫時期が遅めで、貯蔵性も良いことから2月頃まで出回る。
愛媛県生涯学習センター「データベース『えひめの記憶 周桑の愛宕柿』」

葉隠柿(はがくしがき)
【発祥地】福岡県あるいは佐賀県の原産
【主な生産地】熊本県、佐賀県、福島県、長崎県、福岡県、宮崎県
【渋味の分類】完全渋柿(渋抜きが必要)
【由来】葉が隠れるほどたわわに実がなることが名前の由来とされています。「高瀬(たかせ)」とも呼ばれます。
【特徴】サイズは小ぶり、形は丸みを帯びた四角で高さがあります。果皮はオレンジ色から熟すにつれ赤みを帯びていきます。
【料理】完全渋柿(かんぜんしぶがき)のため、脱渋するか、主に干し柿にして食べます。
【時期】晩生種で、収穫時期は11月中旬から下旬
地方特産食材図鑑「葉隠 (はがくし)」
筑波実験植物園「カキ ‘葉隠’ :: おすすめコンテンツ ≫ 植物図鑑」
伽羅柿(きゃらがき)
【発祥地】佐賀県
【主な生産地】佐賀県
【渋味の分類】不完全甘柿
【由来】伽羅柿(きゃらがき)は、別名:元山(がんざん)とも呼ばれます。佐賀県の原産で、江戸時代には栽培されていたとされます。佐賀県原産で北九州の宅地内で栽培されていましたが、戦後の急速な都市化の流れで衰退してしまった品種です。名前の由来は、果肉のゴマが沈香の木目のように詰まっている事からといわれています。佐賀市富士町の鶴田氏宅では皇室献上用として収穫されているそうです。
【特徴】果実は果頂部がわずかに尖った扁球形で、重さは200~260gほど。果皮はやや暗い橙黄色をしており、果粉が多くみられます。果肉はゴマが多く黒褐色です。種子が4~5個入り、3個以下のものは半渋になる傾向があります。本来は甘味が強いのが特徴ですが、30年以上の古木にならないと本来の甘味が出ないとされ、樹齢が50~100年になると実に甘味が出てくるとされます。11月上旬の熟した頃に収穫します。
【料理】甘柿は生食。干し柿、干し柿なますなど
さがの歴史・文化お宝帳「皇室献上柿」
農林水産省「うちの郷土料理 佐賀県干し柿なます」
【参考資料】
農林水産省「完全甘柿 不完全甘柿 完全渋柿 不完全渋柿
農事試験場「柿の品種に関する調査」(1912)農事試驗場特別報告28号P1-46
農林水産省「カキノキ属」
農林水産省「糖度」
農林水産省「柿特」
農研機構「カキの生産量」
奈良県内のカキ古木分布と多様性
【協会関連記事】
この秋は祭に参加してみよう! ~自然や神々、人々に感謝を伝え、ねぎらい、癒す「収穫祭」の魅力~
日本の伝統果樹一覧 ~香酸柑橘(こうさんかんきつ)編~
日本の伝統果樹一覧 ~栗(くり)編~
日本の伝統果樹一覧 ~葡萄(ぶどう)編~