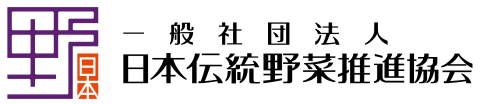農事暦って何?昔ながらの知恵から学ぶ家庭菜園のヒント
目次
今年の夏も猛烈な暑さが続いていますね。家庭菜園を始めたはいいけど、猛暑が続く昨今、「いつ、何を植えたらいいの?」と悩んだりしませんか?また、この後、どんなタイミングで次の作物の準備をしたら良いのでしょう?
そんな家庭菜園のお悩みを解決するヒントとして使えるのが「農事暦(のうじれき/のうじごよみ)」です。
現代のプロ農業では、科学的なデータや気象情報、品種改良などによって、農作業の計画が立てられており、昔の暦を必要としなかったり、むしろズレが大きくて使えなかったりするかもしれません。それでも伝統的な農事暦や二十四節気などは、日本の農業文化や季節感を理解する上で重要な役割を果たしています。
農事暦は、単なるカレンダーではありません。太陽や月の動き、季節の変化に合わせて、自然の恵みを最大限に引き出すためのヒントが詰まっています。この知恵を取り入れて、猛暑に対するオリジナルのカレンダーを作れば、家庭菜園がもっと楽しく、豊かになるはずです。
農事暦とは何か
農業で使う暦のことは、一般的に「農事暦(のうじごよみ)」あるいは「農業暦(のうぎょうごよみ)」と呼ばれます。農事暦として使われる暦には、いくつかの種類があり、それぞれが異なる視点から農作業のタイミングを教えてくれます。昔の人は、これらの暦を組み合わせて活用してきました。
一般的な暦としては、「二十四節気(にじゅうしせっき)」、「七十二候(しちじゅうにこう)」、「雑節(ざっせつ)」、「旧暦・太陰太陽暦(きゅうれき・たいいんたいようれき)」といったものがあります。
このほかには「自然暦(しぜんれき)」というものもあり、地域ごとのものも多く、「カッコーが鳴き始めたら豆を蒔け」とか「栗の花が盛りになると梅雨になる/新潟県」、「一番ザクラが咲いたら畑キビの苗代を作り、二番ザクラが咲いたら山キビの苗床をつくる/高知県」といった自然の動きを手掛かりにして、農作業を行う時期を判断するものもあります。いつか、全国の自然歴を紹介したいものです。
今回は、一般的な農事歴をご紹介し、家庭菜園での栽培に、どのように役立てるかを考えていきたいと思います。
1.二十四節気と七十二候
農事暦の基本的なものに、「二十四節気」と「七十二候」という二つの暦があります。これらは、季節の移り変わりを細かく分類しており、自然のリズムを掴むための知恵が示されています。
➀二十四節気(にじゅうしせっき)
二十四節気は、太陽の黄道上の位置に基づいて1年を24に分けたもので、約15日ごとに季節が移り変わります。「立春」「春分」「夏至」「冬至」などがこれにあたります。それぞれの節気に合わせて気候が変化するため、農作業の目安として古くから非常に重要視されてきました。太陽の動きを基準にしているため、時節にズレはありません。

②七十二候(しちじゅうにこう)
七十二候は、二十四節気をさらに5日ごとの72の期間に分けたもので、よりきめ細かな自然の変化を表します。たとえば「東風解凍(はるかぜこおりをとく)」は、春の風が氷を溶かし始める頃を指し、「梅子黄(うめのみきばむ)」は、梅の実が熟す梅雨の頃を刺し、「涼風至(すずかぜいたる)」は、立秋を過ぎ、朝晩に涼しい風が吹き始める頃をさします。
このように、自然や動植物の様子から季節の進み具合を知ることができます。これらはもともと古代中国で生まれたものですが、日本の気候に合わせて独自に調整されたものも存在します。しかし、これに表される自然や動植物の様子は、現代ではかなり大きなズレが生じているものもあるので、注意が必要です。
この二つの暦は、単なる日付ではなく、自然の変化を観察するための視点を与えてくれます。かつては、この知恵が、農家の人々にとって、無理なく自然に合わせた作業を行うための羅針盤となっていました。七十二候は、現代は、日にちをみるより、そこに表されている自然現象で季節の流れを追うのに使うと良いでしょう。

2.雑節(ざっせつ)
二十四節気とは別に、日本の風土に合わせて作られた独自の暦です。「節分(せつぶん)」、「入梅(にゅうばい)」などが雑節です。これらは、日本の気候や農業の経験から生まれた非常に実用的な暦です。
雑節の日にちは、地球の公転周期と暦のズレを調整するため、年によって変動します。たとえば、「節分」は、2月3日のことが多いですが、2025年は2月2日でした。1984年までは4年に1度の閏年の節分は2月4日でしたが、1985年から2020年までは毎年2月3日でした。 2021年から2057年までは閏年の翌年の節分は2月2日になります。
このような微調整をしながら、季節の移り変わりを刻んでいきます。
3.旧暦/太陰太陽暦(きゅうれき/たいいんたいようれき)
旧暦は、明治時代以前に使われていた太陰太陽暦です。月の満ち欠けと太陽の運行を組み合わせたもので、現在の「新暦(しんれき)」よりも季節感と一致していたため、昔の農作業の目安によく使われました。
この「太陰太陽暦」の最大の問題は、月の満ち欠け(約29.5日)を12回繰り返すと、1年が約354日となり、実際の季節(約365日)と11日ほどズレてしまうことでした。そのままでは、何年か経つと「1月なのに夏」といった事態が起こってしまいます。
そこで登場するのが、二十四節気です。二十四節気は太陽の動きを基準に作られているため、季節とズレることがありません。
旧暦は、この二十四節気を季節の目安として利用することで、季節のズレを調整していました。
具体的には、二十四節気の中にある「中気(ちゅうき)」が入らない月を「閏月(うるうづき)」とし、1年を13ヶ月にすることで、暦と季節を一致させていたのです。
そのため、2025年は、旧暦の閏6月が2回目の6月として存在します。旧暦の日付は、毎年、新暦とズレますが、伝統的な行事の多くは、明治時代以降もこの旧暦に基づいていました。
現在、伝統的な行事は、それぞれの行事や地域によって、新暦で行うか、旧暦で行うかが異なります。
たとえば、毎年6月30日に全国各地の神社で執り行われる「夏越(なごし)の祓(はらえ)」という神事は、半年間の穢れを祓う神事ですが、もともとは、旧暦6月30日(新暦8月23日)に行われていたものです。
また、「十五夜」として知られている「中秋の名月」は、今でも旧暦8月15日としており、2025年は10月6日となります。
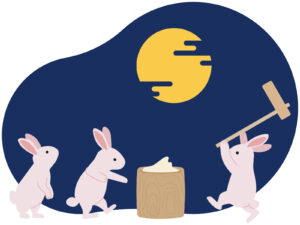
4.農耕儀礼としての年中行事
多くの日本の年中行事は、農耕儀礼(農耕にまつわる儀式や祭り)に由来しています。豊作を祈願し、収穫を感謝するための祭りが、そのままその時期の年中行事として定着しきました。年の初めに行われる行事の多くは、その年の豊作を前もって祝う「予祝(よしゅく)」の意味合いを持っています。
| 年中行事名称 | 内容・意味 |
| 小正月(こしょうがつ) | 旧暦1月15日頃。「農の正月」とも呼ばれ、餅花を飾ったり、田遊び(模擬的な田植えの儀式)を行ったりして、稲の豊作を願いました。 |
| 初午(はつうま) | 旧暦2月の最初の午の日。稲荷神社にお参りし、五穀豊穣を祈願します。 |
| お花見 | 桜の花が咲く様子を稲の豊作に見立て、宴を催すことで豊作を予祝する意味合いがあったとされています。 |
| 早苗饗(さなぶり) | 田植えを終えた後。田の神様に感謝し、田植えの労をねぎらう宴会です。 |
| 虫送り | 田植えが終わった頃(春~初夏)、稲が実り始める頃(初夏)、夏の土用や旧暦の行事の半夏生やお盆に合わせて行われます。提灯を持って地域を練り歩くなど、各地で様々な形で行われました。 |
| 雨乞い・日和乞い | 干ばつや長雨の際に、天候の回復を祈願します。 |
| お盆 | 旧暦7月15日頃。先祖の霊を迎え、収穫期の準備や稲の生育を見守ってもらう意味合いがありました。 |
| 新嘗祭(にいなめさい) | 旧暦11月。天皇がその年に収穫された新穀を神々に供え、自らも食す儀式。国民的にも収穫を感謝する重要な行事でした。各地の「秋祭り」も収穫を祝う意味合いが強いです。 |
このように、農家の人々は自然と向き合い、複数の暦を互いに補完しながら、豊かな恵みを得るための知恵として活用してきました。現代でも、これらの暦を組み合わせることで、より深く季節や自然を理解し、家庭菜園などに活かすことができます。
5.農事暦をまとめてカレンダーにしてみた
ということで、「二十四節気」と「雑節」と「年中行事」を組み合わせた農事カレンダーを作ってみました。旧暦の時期は新暦にしてあります。こうしてみると、農業は一年の四季を通して展望する必要があることがよくわかります。また、豊作を祈願したり、収穫を感謝したりする行事が多く目に留まります。人間の力ではいかんともしがたい自然を畏敬し、呼吸を合わせながら作業を進めてきたことがわかります。
分類の(年)は年中行事、(二)は二十四節気、(雑)は雑節の略です。
| 日付 | 名称 | 分類 | 簡単な内容 |
| 1月1日 | 正月 | (年) | 新年を祝い、歳神様を迎える行事。 |
| 1月5日頃 | 小寒 | (二) | 寒の入り。寒さが厳しくなり始めるころ。 |
| 1月15日 | 小正月 | (年) | 農の正月。稲の豊作を祈願する日。 |
| 1月17日~2月2日頃 | 冬土用 | (雑) | 立春(2月4日頃)の前約18日間。 土を動かす作業(土いじり、草むしり、井戸掘りなど)は避けるべきとされる。 |
| 1月20日頃 | 大寒 | (二) | 一年で最も寒さが厳しい時期。冬の作業を締めくくり、春に備える時期。 |
| 2月3日頃 | 節分 | (雑) | 冬と春を分ける日。豆まきをして邪気を払い、無病息災を願う。 |
| 2月4日頃 | 立春 | (二) | 暦の上では春の始まり。旧暦での正月の目安。 |
| 2月6日頃 | 初午 | (年) | 2月初めの午の日。稲荷神社に参拝し五穀豊穣を祈願する。 |
| 2月19日頃 | 雨水 | (二) | 雪が雨に変わり、雪解けが始まるころ。 |
| 3月5日頃 | 啓蟄 | (二) | 冬眠していた虫たちが土から出てくる頃。 |
| 3月19~21日頃 | 春の彼岸 | (雑) | 春分の日を中日とした前後3日間。祖先を供養する期間。ぼたもちを食べる。 |
| 3月20日頃 | 春の社日 | (雑) | 春分・秋分に一番近い戊(つちのえ)の日。土地の神様を祀り、五穀豊穣を祈る日。春の社日を「春社」と言って種まきをし、秋の社日を「秋社」と言って穀物を刈り取り、田の神を祀る。 |
| 3月20日頃 | 春分 | (二) | 昼と夜の長さがほぼ同じになる。太陽が真東から昇り、真西に沈む。 |
| 3月下旬~4月上旬 | お花見 | (年) | 田の神様が桜に宿ると考え、桜の開花で豊作を占い、宴を催すことで豊作を予祝する。 |
| 4月4日頃 | 清明 | (二) | 空気が澄んで清々しい頃。種まきや田植えの準備。 |
| 4月17日~5月4日頃 | 春土用 | (雑) | 立夏(5月5日頃)の直前の約18日間。 土を動かす作業(土いじり、草むしり、井戸掘りなど)は避けるべきとされる。 |
| 4月20日頃 | 穀雨 | (二) | 田畑を潤す春の雨が降る頃。種まきの好機。 |
| 5月1日頃 | 八十八夜 | (雑) | 立春から88日目。遅霜の心配がなくなる目安。茶摘みの最盛期。この日摘んだお茶は上等とされ、不老長寿の縁起物とされる。 |
| 5月5日頃 | 立夏 | (二) | 夏の始まり。この日を境に暑さが増す。 |
| 5月21日頃 | 小満 | (二) | 陽気が良くなり、草木が茂り、天地に満ち始める。 |
| 6月6日頃 | 芒種 | (二) | 稲や麦など穂の出る植物の種まきの頃。 |
| 6月11日頃 | 入梅 | (雑) | 暦の上での梅雨入り。 |
| 6月21日頃 | 夏至 | (二) | 昼の時間が一年で最も長い日。 |
| 6月下旬 | 早苗饗 | (年) | 田植えを見届けた神様を田から送り出し、豊作を祈願する。地域や集落によって時期や内容は異なる。 |
| 7月1日 | 半夏生 | (雑) | 夏至から11日目。田植えを終える目安とされる。 |
| 7月7日頃 | 小暑 | (二) | 梅雨が明け、本格的な暑さが始まるころ。 |
| 7月19日~8月6日頃 | 夏土用 | (雑) | 立秋(8月7日頃)前の約18日間。 土を動かす作業(土いじり、草むしり、井戸掘りなど)は避けるべきとされる。 土用干し(衣類や書物などを陰干しすること)を行う習慣がある。 |
| 7月23日頃 | 大暑 | (二) | 一年で最も暑さが厳しくなる頃。 |
| 8月7日頃 | 立秋 | (二) | 暦の上では秋の始まり。残暑が厳しい時期。 |
| 8月13日~15日頃 | お盆 | (年) | 先祖供養とともに、収穫に感謝と、次の作物の豊作を祈願する。 |
| 8月23日頃 | 処暑 | (二) | 暑さが和らぎ始めるころ。 |
| 9月1日頃 | 二百十日 | (雑) | 立春から210日目。台風が襲来しやすい時期とされ、農家にとって注意が必要な日。 |
| 9月8日頃 | 白露 | (二) | 大気中の水蒸気が露となって草木に朝露が宿る頃。 |
| 9月22日~24日 | 秋の彼岸 | (雑) | 秋分の日を中日とした前後3日間。祖先を供養する期間。おはぎを食べる。 |
| 9月23日頃 | 秋分 | (二) | 秋の彼岸の中日。昼と夜の長さがほぼ同じになる。暑さ寒さも彼岸までといわれる。 |
| 9月26日頃 | 秋の社日 | (雑) | 秋分の日に最も近い戊(つちのえ)の日。産土神を祀り、収穫に感謝する日収穫に感謝する日。 |
| 10月8日頃 | 寒露 | (二) | 露が冷気によって凍り始める頃。 |
| 10月20日~11月6日頃 | 秋土用 | (雑) | 立秋(10月19日)の前日から18日間。 土を動かす作業(土いじり、草むしり、井戸掘りなど)は避けるべきとされる。 |
| 10月23日頃 | 霜降 | (二) | 霜が降り始めるころ。収穫期。秋が深まり冬支度を始める時期。 |
| 11月7日頃 | 立冬 | (二) | 暦の上では冬の始まり。風が冷たくなり始める。 |
| 11月22日頃 | 小雪 | (二) | わずかな雪が降り始める頃。 |
| 11月23日 | 新嘗祭 | (年) | 勤労感謝の日。宮中や全国の神社でその年の収穫に感謝する祭りが行われる。 |
| 12月7日頃 | 大雪 | (二) | 雪が本格的に降り始める頃。 |
| 12月22日頃 | 冬至 | (二) | 昼の時間が一年で最も短い日。ゆず湯に入り、かぼちゃを食べる習慣がある。 |
農事暦は今でも役に立つのか?
では、農事暦は、この異常気象の中でも役に立つのでしょうか?
農事暦は、古くからの経験に基づいて、季節ごとの農作業の目安を示したもので、季節感にあふれています。しかし、近年の猛暑などの異常気象は、その「季節の目安」を大きく狂わせています。このことを考えると、従来の農事暦はそのままでは役に立たなくなってきていると言えるかもしれません。
特に猛暑によって、暦が役に立たなくなる理由は、具体的には、以下のものが考えられます。
作業時間の変更
猛暑日が増えたことで、熱中症のリスクが高まっています。そのため、日中の暑い時間帯を避け、早朝や夕方など、涼しい時間帯に作業を行うことが推奨されています。従来の暦では、日中の作業を前提としたスケジュールが組まれている場合が多く、そのままでは危険です。
作物の生育への影響
高温は作物の生育に悪影響を及ぼすことがあります。例えば、ホウレン草など、高温に弱い作物は、生育に適した時期がずれたり、枯れてしまったりする可能性があります。従来の暦通りに種まきや植え付けを行っても、収穫までたどり着けないケースも出てきています。
病害虫の発生時期の変化
気温の上昇は、病害虫の発生時期や種類にも影響を与えます。従来の農事暦では予測できなかった病害虫の被害が発生する可能性もあります。昨年は西日本で猛暑によりカメムシが大発生する事態に見舞われました。
このような状況を踏まえると、現代の農業では、従来の農事暦を絶対的なものとして捉えるのではなく、天候や気候変動に合わせた柔軟な対応が求められます。
今後、プロ農家は、ますます、デジタル技術を活用したリアルタイムの気象データを利用したり、生育状況を記録してデータを集積し、AIに分析させたりして、個々の農家がそれぞれの状況に合わせて作成する「オリジナルの農事カレンダー」が、より必要になってくると言えるでしょう。

家庭菜園での農事暦の活かし方
では、家庭菜園での農事暦の利用はどうでしょう?
もちろん、旧来の農事暦が持つ、季節の移り変わりや伝統的な知識には今も価値がありますが、猛暑という厳しい現実に対応するためには、更新や見直しが必要不可欠です。家庭菜園で農作物の栽培スケジュールを考える際には、伝統的な農事暦の知識をベースに、現代の気候変動に対応した工夫を組み合わせることが重要になります。従来の農事暦をそのまま鵜呑みにするのではなく、以下のような方法で柔軟に活用することをおすすめします。
1. 「適期」をずらす・見直す
農事暦に書かれている「種まき」「植え付け」の時期は、あくまで目安です。猛暑が続くと、従来の適期では高温障害や乾燥によって発芽不良になったり、苗が育たなかったりするリスクがあります。
➀暑さに強い品種を選ぶ
同じ野菜でも、猛暑に強い品種が開発されています。特に葉物野菜では、小松菜など耐暑性が改良された品種を選ぶことで、真夏でも比較的育てやすくなります。伝統野菜の品種は適応力が良いので、暑さに強かったり、採種を繰り返すことで、さらに強くなっていく可能性を持っています。
②時期をずらす
暑さが一段落する晩夏や初秋に種まきを行うなど、時期をずらして栽培計画を立てましょう。また、生育期間の短い野菜を選び、猛暑が本格化する前に収穫を終える「リレー栽培」も有効です。
③発芽を助ける工夫
暑い時期に種をまく際は、遮光ネットで地温の上昇を防いだり、夕方に水やりをしたり、涼しい場所で発芽させてから植え付けるなどの工夫が有効です。
2. 伝統的な知恵を活用する
農事暦には、単なる日付だけでなく、季節の移り変わりや天候の変化を読み解くためのヒントが詰まっています。
➀観察する目を養う
「桜の花が咲いたら種をまく」といった、植物や自然のサインを農事暦と照らし合わせることで、地域ごとの気候に合わせたより正確なタイミングを見つけられます。また、動物や昆虫、他の植物の動向や変化を観察することで、気候環境の変化をとらえることもできます。
②土用の活用
農業は作業をしようと思ったら、一年中、休みなくやることがあります。「土用」は、土をいじらない方が良いとされる時期ですが、季節ごとに休みを強制するものでもあったとも考えられます。特に夏の土用は、真夏の高温多湿な時期に無理な作業を避けるための先人の知恵とも言えます。無理せず休養する期間と捉え、のんびりした作業に当てるのも良いでしょう。
3. 猛暑対策と組み合わせる
農事暦の知識と猛暑対策を組み合わせることで、家庭菜園の成功率を上げていきましょう。
➀物理的な対策
遮光ネット: 強い日差しを遮るために、遮光ネット(寒冷紗)を張って葉焼けや地温の上昇を防ぎましょう。
敷き藁・マルチング: 株元に敷き藁やマルチングをすることで、土壌の乾燥と地温の上昇を抑制し、水やりの回数を減らすことができます。
風通し: 込み合った枝葉を剪定して風通しを良くし、蒸れを防ぎましょう。
②水やり
時間帯: 日中の暑い時間帯は避け、朝か夕方の涼しい時間帯に水やりを行います。
頻度と量: 野菜の種類や土壌の乾燥具合を見て、適度な水やりを心がけます。特にナスなど水分を好む野菜は、朝晩の水やりが有効です。
特に初心者は、苗がしおれているのを見ると、水をあげたくなると思いますが、猛暑の日中に水をやるのは厳禁。熱くなった水が蒸発し、サウナのような状態になり、苗が蒸れてしまうからです。また、葉に水がかかると、葉の表面についた水滴がレンズの役割を果たして、葉を焼いてしまう「葉焼け」の原因にもなります。夕方になってから水をやればちゃんと回復するのでガマンです。
4. 「自分だけの農事カレンダー」を作る
最も効果的な方法は、自分自身の家庭菜園の記録をつけて、「自分だけの農事カレンダー」を作ることです。
➀栽培記録をつける
栽培した野菜の種類、種まき日、植え付け日、収穫日、その日の天候や気温、行った対策(水やり、遮光など)を記録します。これは、来年の栽培にも役に立ちますが、長年、日々つけておくと経験値として蓄積された価値あるものができあがります。
②成功・失敗を分析する
なぜうまく育ったのか、なぜ失敗したのかを記録から分析することで、翌年以降の栽培に活かすことができます。同じ品種でも、播種時期をいくつかにズラしたり、いろいろな環境下で栽培を試したりしておくのも大切です。
猛暑が続くからこそ、農事暦をただの年間スケジュールとしてではなく、自然のサインを読み解くヒントとして活用し、臨機応変に対応することが、家庭菜園を楽しむための鍵となります。
ぜひ、自分の育てたい品種が元気に育つように農事暦をもとに猛暑対策を検討してみてください。
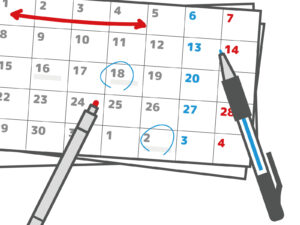
まとめ
「農事暦(のうじごよみ)」は、昔から農作業の目安として使われてきた暦ですが、猛暑が続く現代では、従来の農事暦をそのまま使うことは難しくなってきています。しかし、その知恵をヒントにすることで、家庭菜園を成功させる手助けとなります。
農事暦をただの年間スケジュールとして捉えるのではなく、ここで紹介した方法と合わせ、自然のサインを読み解くヒントとして、家庭菜園に活用してみてください。
【参考資料】
加藤孝太郎「農業に関する自然暦」(2016)農業および園芸91巻10号
京都大学防災研究所サイト「地球全体の「農事暦」を衛星データから作成」
国立天文台「こよみ用語解説」
【協会関連記事】
2024年 猛暑の夏 ~野菜の適応力について考える~