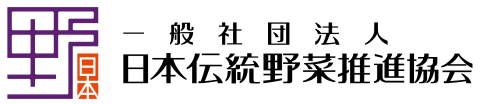なぜ、伝統野菜はその土地でしか味わえない野菜になるのか? ~在来種の適応力とその魅力~
目次
伝統野菜が紹介される時に「その土地ならでは」という言葉が、枕詞なのかと思うほどよく使われています。特定の地域で、長年育まれ、今日まで残っている伝統野菜は、その地域の気候風土に適応しているので「その土地ならでは」の野菜になっているのは当然といえます。
野菜栽培は「適地適作」が基本であり、品種、気候風土、栽培技術などの組み合わせによって成り立っています。そのため、何らかの理由でタネが他の土地に移動した場合、品種は同じでも移動先の地域によって元の野菜とは違う味わいになります。また、近年は気候変動の影響でさまざまな農作物が生育不良に陥っていますが、それも適応がおおいに関係しています。
気候や環境によって、農作物の生育や味にどのような変化が起きるのでしょうか?今回は、植物の適応の基本と、野菜の適応変化について、みていきたいと思います。
植物の基本的な環境適応
人間も含めた生物は、自然環境の中で生き抜くための環境への適応力を持っています。その強弱に差はあれど、どの生物も環境の特性に適応して持続的に生存しようとします。
植物は移動しない分、生育する場所の気候風土に合わせ、多様に進化し適応してきました。まずは、植物の基本的な適応方法を大まかに押さえておきたいと思います。
(あくまでも大まかです。詳しく知りたい方は植物生理生態学の本をご参照ください)
1. 生理的な適応
植物が育つために必要不可欠なのは、光、水、空気、温度、養分の5つです。これらを確保するために、植物はさまざまな方法で適応していきます。
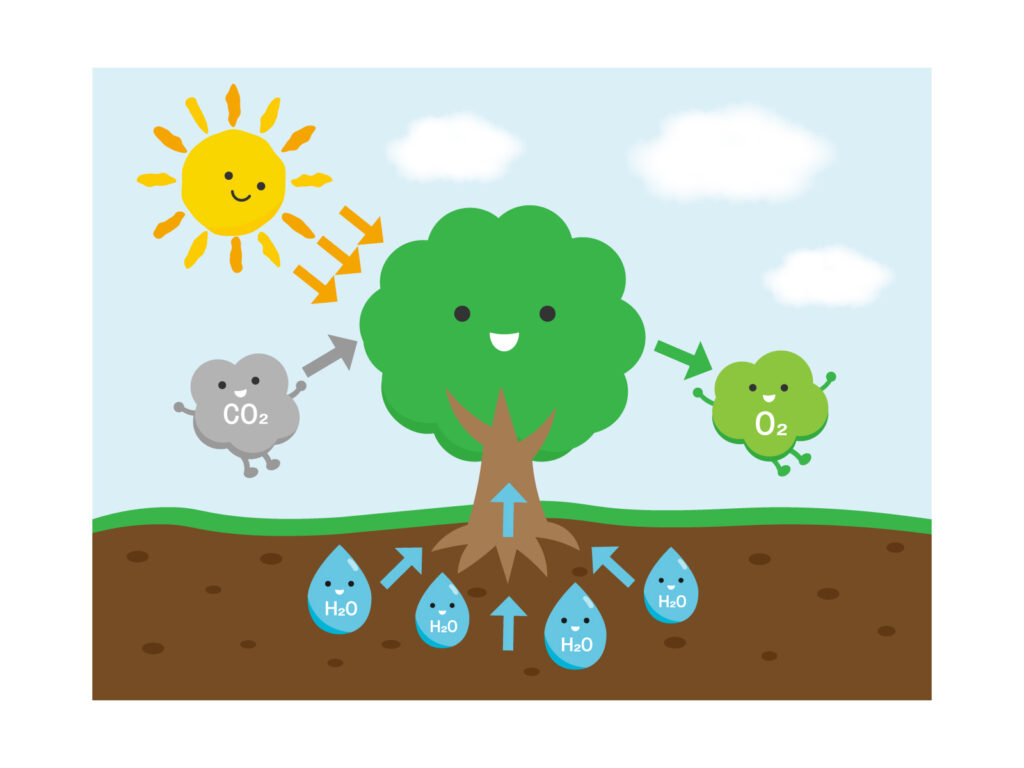
もっと光を!
植物など葉緑素を持つ生物は、光エネルギーを使って二酸化炭素と水からデンプンなどの養分(=有機物)を作ります。これを光合成(こうごうせい)といいます。植物にとって光合成のために光を取り込むことは、とても大事なことなので、できるだけ多く取り込めるようにしようとします。
高校の生物の授業でも習うと思いますが、樹木は日照時間が長いと常緑、短いと落葉になります。
常緑樹は日照時間が短くなる冬場でも、光合成で得られるエネルギー量の方が葉の維持に必要なエネルギー量より多いので葉をつけ続けます。光合成の効率が悪くなった古い葉は落葉しますが、少量の古い葉と新しく育ってきた多量の葉が常に混在しているため常緑に見えます。
落葉樹は日照時間が短い冬は光合成による栄養の生産が十分に行えません。そのため水分不足等で枯れないよう葉を落とし、できるだけ栄養や水分を使わないようにして冬を乗り切ります。

常緑針葉樹
また、日照時間が短い地域の植物は、少ない光でも光合成を効率的に行えるように、光合成の仕組みを進化させることもあります。光合成を効率的に行う細胞を密にしたり、クロロフィルの種類を増やしたりして吸収できる光の波長域を広げたりなどします。
<常緑>長い⇐光合成に適した時間⇒短い<落葉>
日照時間や気温と水分は密接に関係しているので、分けて考えるのは難しいのですが、気温に適応する仕組みも持っています。
概ね、気温が暖かい地域では広葉樹が多く、寒い地域では針葉樹が多くなります。気温が低下してくると根から水を吸い上げにくくなりますが、葉からは水分が蒸散していきます。そのため、葉の面積の小さい針葉樹の方が寒い地域には適しています。
ほかにも、寒さに強い植物は、凍結を防ぐため糖類やアミノ酸などの物質を蓄えたり、休眠したりします。
<広葉>暖かい⇐気温⇒寒い<針葉>
得意なところで頑張ります!
森林の分布は気候帯によって異なり、日本では、暖温帯では常緑広葉樹、冷温帯では落葉広葉樹、亜寒帯では針葉樹、暖温帯と冷温帯の移行部の中間温帯では落葉広葉樹が優勢となり、冷温帯や亜寒帯では針葉樹と広葉樹が混じって分布しています。
砂漠植物のように、気温の高い地域の植物は、高温に耐えるためのタンパク質を合成したり、気孔を閉じて水分蒸散を抑えたりして耐暑性を持ちます。
乾燥に強い植物は、サボテンのように少ない水分で生き延びる仕組みを持っています。湿潤に強い植物は、マングローブのように過剰な水分を排出したり、根腐れを防いだりするための仕組みを持っています。

野生のウチワサボテン
2. 形態的な適応
植物は生理的な面だけでなく形態も変化させて適応します。葉や根の形状や木の高さなどにその変化の様子を見ることができます。
あの手この手で対策します
植物は基本的に種ごとに固有の葉の形がありますが、環境に適応して形が変化することもあります。
降水量の多い地域ほど広葉樹の葉面積が大きくなり、降水量が少ない地域ほど葉面積が小さくなる傾向があります。乾燥地では葉が小さく厚くなります。たとえば、サボテンは葉の表面積を小さくしたり、多肉化させたりすることで水分の蒸散を抑えます。水分を蓄えるために茎が太くなることもあります。
多湿地では葉が大きく薄くなる傾向があります。湿潤地に生育するハスの葉は水分の蒸散を気にせず(?)、表面積を大きくしたり気孔を多くしたりすることで、光合成を効率的に行います。

ハス
寒い地域に生育している針葉樹は冬の凍結に備えて葉を頑丈な針状にしています。そうすると、光合成ができる面積は減りますが、気孔の数も減るため、水分の蒸発が少なくて済みます。また、積もった雪で葉が隠れたり枝が折れたりといったリスクを防ぎます。
また、水草やロリッパアクアティカという水陸両生植物には環境によって葉の形を自在に変える異形葉性(いけいようせい)がみられます。

水草
ほかには、同じ品種でも桑(くわ)の葉のように成長段階によって、葉を大きくしたり小さくしたり、モミジのように陽当たりを調整したり、切れ込みを入れて下の葉にも光が当たるようにしたり、風通しをよくしたりするものもあります。
み、水をくれ…
乾燥地では地中深くまで根を張り水分を求めていきます。たとえば、砂漠に生えるラクダ草は地中深く根を張ることで、地下水を効率的に吸収します。しかもラクダ草は上には伸びず横に広がり、さらに鋭いトゲを持ち、動物たちに食べられないようにガードします。それに対し、ラクダは過酷な環境に適応し、硬い植物を食べられる口腔構造を持ち、ラクダ草を食べるという適応と生き残りの戦略が展開されています。
一方、多湿地では、浅く広く根を張り養分を効率的に吸収します。水分の豊富な湿潤地の水生植物は、そうして地表の水分を効率的に吸収します。
地を這う生き方はダメですか?
寒冷地では植物の成長期間が短くなり草丈が低くなりがちです。高山植物によく見られるように、低木や匍匐性(ほふくせい)植物になることで強風や積雪から身を守ります。匍匐性(ほふくせい)とは軍隊が行う匍匐前進(ほふくぜんしん)の匍匐(ほふく)と同じで、植物の茎や枝が地面を這うように伸びる性質のことです。這い性(はいせい)、クリーピング性とも呼ばれます。

高山植物シナノキンバイ
熱帯地では熱帯雨林の樹木のように背の高い木になることで日光を効率的に浴び、他の植物との競争に勝ち抜こうとします。
3.生活環の適応
生物が誕生してから次世代の生物が誕生するまでの過程をライフサイクルまたは生活環(せいかつかん)と言います。ここでは、植物の生活環における基本的な適応の特徴を見ていきましょう。
乾燥と寒さは苦手です
植物は種子の状態でも環境に適応しようとします。乾燥地では乾燥に強い種子を形成し、雨季になってから発芽し、短い期間で成長を完了させます。寒冷地では休眠期間が長い種子を形成し、暖かい春になってから発芽することで寒さを避けます。
採種したタネを保管する場合も、低温・低湿の環境で保存することで休眠状態になり、発芽力を長く維持することができます。密閉できる食品保存用袋に乾燥剤と一緒に入れて冷蔵庫に保管すると良いでしょう。
高山植物の青春は短い!
寒冷地の植物は生育期間が短い傾向があります。たとえば、高山植物は短い夏の間で成長し繁殖を完了させます。一方、熱帯地や一年を通して温暖な地域では、常緑樹が多く、一年中成長を続けます。
4.共生
さあ、共に生きよう!
植物の適応方法には、他の植物や菌類と共生するという方法もあります。共生することで、栄養の獲得、水分やミネラルの吸収、生育場所の確保をします。
共生の種類は、大きく分けて➀相利共生、②片利共生、③寄生の3つがあります。
➀相利共生は互いに利益を得る共生関係です。②片利共生は一方の植物は利益を得ますが、もう一方の植物には利益がありませんが害も受けません。③寄生は一方の植物は利益を得ますが、もう一方の植物は害を受けます。
植物は、共生によって成長に欠かせない窒素やリン酸などの養分を効率的に獲得することができます。
➀相利共生の例
菌根菌(きんこんきん)
多くの植物の根には菌根菌という土壌微生物の一種の糸状菌の菌類が共生していて、相互に利益をもたらしています。菌根菌は植物の根の表面積を広げ、養分を効率的に吸収するのを助けます。植物は菌根菌からリン酸や水分を受け取り、菌根菌は植物から光合成産物を受け取ります。
しかし、キャベツ、ハクサイ、ブロッコリー、菜の花などのアブラナ科やホウレン草などのアカザ科の植物など、自らの根を細くするように進化して、菌根菌との共生を必ずしも必要としなくなったものもあります。
根粒菌(こんりゅうきん)
マメ科植物は根粒菌と共生します。根粒菌は大気中の窒素を植物が利用できる形に変えることができます。マメ科植物は根粒菌から窒素を受け取り、根粒菌はマメ科植物から光合成産物を受け取ります。
②片利共生の例
熱帯雨林などでは他の植物の茎や葉に着生し、日光や水分を得て成長する植物が見られます。他の植物に生育の場を借りて成長しますが、その植物に栄養を奪うことはありません。
③寄生の例
ヤドリギは他の植物に寄生し樹液を吸い取って成長します。ヤドリギは楔(くさび)のような根を他の植物の幹の中に食い込ませ水や養分を吸い取って利益を得ますが、寄生された植物は害を受けます。(サイアク…)

ヤドリギ
ここまでが、大まかな植物の適応方法です。植物の個性や適応力には驚きですね。これらの性質を踏まえた上で、植物である野菜が環境に適応するとどのような変容が起きるかをみていきたいと思います。
野菜の適応変化
植物は気候風土の影響を強く受けます。植物である野菜も気候風土に適応する過程でさまざまな変容を起こします。同じ品種の野菜であったとしても、栽培される地域の気候条件や土壌環境などによって、含まれる成分量や組成が変化することが知られています。これによって味も変化します。
具体的には、次のような変容が生じます。
1.気候への適応
気温・降水量・日照時間などの気候条件によって、野菜の生長サイクルは変わります。たとえば、寒冷地では発芽や生長が遅くなることがあり、温暖な地域では逆に成長が早くなることがあります。また、日照時間の長さが変わると光合成の効率や成長速度に影響が出ます。
寒いと甘く、暑いと苦くなる?
野菜は品種によって、そもそも耐寒性や耐暑性が異なります。
たとえば、寒冷地ではキャベツやブロッコリー等の耐寒性が強い品種が栽培されます。キャベツは寒いと葉が密に重なり寒さから身を守るようになります。熱帯や亜熱帯の地域ではトマトやナス等の暑さに強い品種が育ちやすいです。
一般には、高温下では糖分を蓄えにくくなり、味が薄くなる傾向があります。また、苦味成分が増加することもあります。反対に低温下では糖分を蓄えやすくなり、甘味が増す傾向があります。
たとえば、寒冷な地域で栽培されたホウレンソウは糖度が高く、ビタミンC含有量も多い傾向があります。アミノ酸などの旨味成分も増加するため、味わいが変わります。ただし、霜が降りるほどだと霜害や凍害を受けてしまいます。
暑いと機能性成分が増える
野菜は温度が高いほど代謝が活発になり、カロテノイドやポリフェノールなどの機能性成分の含有量が増加する傾向があります。ただし、過度な高温は生育を阻害し、成分量を減少させます。
野菜の味は収穫するタイミングによっても変化します。一般的に旬の時期に収穫された野菜が最も味が良いとされています。
しかし、ここ最近は、気候の変動によって野菜の成長周期が変わり、収穫時期がずれることもあります。寒冷になると成長が遅くなるため収穫期が遅れます。逆に平年通りに順調に生育し、温暖な気候であれば複数回の収穫が可能となるものもあります。
光合成は得意です
野菜は光合成の効率も適応させています。日照量の少ない寒冷地域では短期間で光合成を最大限に活かせるような品種が栽培され、逆に日照量の多い温暖地域では、光合成の効率が高いサトウキビやトウモロコシ等のC4(シーヨン)型植物の品種が有利になります。

サトウキビ
十分な日照を受けると、糖分やビタミンCなどを豊富に蓄え、味が濃くなる傾向があります。反対に日照不足になると、野菜は光合成を十分に行えなくなり、糖分やビタミンなどの栄養成分が減少することがあります。
たとえば、トマトは、日照時間が長いほど、リコピンやβ-カロテンなどのカロテノイド含有量が増加することが知られています。逆に日照時間が短いと生育不良になって、花が咲かなくなることがあります。
ちなみに寒さに強いネギはマイナス8度ぐらいまで耐寒性があります。また、タマネギの鱗葉(りんよう)部分、つまり私たちが普段食べている白い部分は、基本的には葉緑素を持っていません。
※植物の光合成経路には特徴があり、植物の葉の細胞で異なる光合成の二酸化炭素固定の方法でC3型とC4型に分けられます。C3型は、多くの植物が採用する基本的な光合成回路で、作物ではイネや小麦などの穀物やホウレンソウなどの野菜があり、C4型は、高温や乾燥した環境に適応した光合成経路で二酸化炭素を効率的に固定します。作物にはトウモロコシやサトウキビなどがあります。この他に、CAM型植物というものがあり、乾燥した環境に適応した光合成経路で夜間に気孔を開き二酸化炭素を取り込みます。
産毛を生やして水分を
地域によって降水量が異なるため水分の要求量や根の発達に変容が生じます。乾燥地では根を深く伸ばし水分を効率的に吸収しようとします。一方で湿地帯や降水量が多い地域では、根の発達が比較的浅くなります。
野菜の生育には適切な降水量が大切です。過剰な水分は根腐れを引き起こし、栄養分の吸収を阻害する可能性があります。また、水分が不足しても生育不良になります。また、キャベツなどは乾燥が続いた後に大雨が降ると水分を急激に吸い上げ、球が割れることもあります。結球が不十分になることもあります。
適度に乾燥した環境では、水分を保持するため養分やアミノ酸を蓄える傾向があります。これにより、味が濃くなることがあります。反対に、多湿な環境では水分を過剰に蓄え、味が薄くなることがあります。
トマトは、原産地が南米アンデス山脈の西側の高原や海岸地帯で、太陽光線が強く、乾燥し、昼夜の気温差が大きい地域です。このような乾燥地では根を深く張り、水分を効率的に吸収できるようにします。日本に渡り、多湿な気候に適応しましたが、土壌の水分が不足すると産毛のような毛(トライコーム)を生やし、それからも水分を集めようとします。この毛がある方が「甘い」と言われます。

トマトの花
数打ちゃ当たる!
乾燥が強い地域では、少ない水分でも確実に繁殖できるように種子の数を増やすことがあります。また、乾燥した環境に適した遺伝子を持つ個体が生き残りやすくなるので、その遺伝子の頻度(簡単にいうと量)が増えることがあります。
ほかには、環境の変化に対応するために新たな遺伝子が出現する突然変異が起こることがあります。長い年月をかけて気候風土に完全に適応した新たな品種が誕生することもあります。
2.土壌への適応
野菜の生育に必要不可欠な養分を供給する土壌も重要です。土壌の種類は物理的性質、化学的性質、生物的性質によって、様々な種類に分類することができます。
好みの土があるんです
野菜の種類によって適した土壌は異なります。例えば、根菜類は砂質(さしつ)土壌を好み、葉物野菜は壌質(じょうしつ)土壌を好みます。たとえば、同じ品種のキャベツでも、砂質土壌で育てるとみずみずしく、粘土質(ねんどしつ)土壌で育てると甘みが強くなる傾向があります。また、有機物を多く含む土壌で育てたキャベツは一般的に味が濃く美味しいと言われています。
また、土の酸度にも相性があります。酸度はpH値で表し、pH値7が中性、pH4~6は酸性土、pH8~9をアルカリ土と呼びます。一般的に野菜を作るにはpH6.0~6.5程度が理想的な土とされますが、野菜によって合うpH値があり、たとえば、ジャガイモはpH5~6.5、サツマイモはpH5~6の酸性土とされます。酸性度を嫌うホウレン草はpH6~7.5、アスパラガスはpH6.5~8が合っています。

羊蹄山とジャガイモ畑
土壌の複雑な条件下に適応した野菜・果物は、さまざまな栄養素やミネラル成分を含み、甘味、苦味、辛味、酸味などの味わいを生み出します。品種に合わない土地で栽培すると、生育不良、病害虫の発生、品質低下、収量減少など、様々な問題が発生します。ただし、次に説明するように、野菜が病害虫への耐性を獲得することもあります。
3.病害虫への耐性の進化
強い品種になりたい
気象条件によっては発生する病害虫も異なります。高温多湿下ではカビやウイルスが繁殖しやすいため、基本的には、それらに耐性のある品種が選ばれることが多いです。
特定の気候風土では、特定の病害虫が発生しやすいため、野菜そのものが、それらに対する抵抗性を獲得することがあります。
4. 栽培方法による変容
育ての親で変わります
野菜の適応は、遺伝的な要因だけでなく、栽培者による栽培方法や環境管理によっても影響を受けます。施肥も野菜づくりには重要な要素になります。
同じ品種を同じ環境下で育てても、有機栽培や慣行栽培など栽培方法によって野菜の成分組成が変化します。肥料の種類や施肥量や施肥のタイミングによっても野菜の成分組成が変化します。
たとえば、窒素肥料を多く施すと葉の生育が促進され、タンパク質含有量が増加する傾向があります。また、有機栽培や自然栽培では肥料が効きだすのに時間がかかりますが、野菜本来の味が引き出されやすくなります。(ニンジンやトマト本来の野菜の風味を嫌う子どももいるので美味しいと感じるかどうかはさておき…)
5.交雑
交雑によって進化することもあります。交雑とは異なる品種や系統の植物が交配して、新しい特性を持った品種が出現することです。自然交雑には風による風媒交雑、昆虫による虫媒交雑、鳥による鳥媒交雑があります。交雑にはメリットもデメリットもあります。
中でもアブラナ科の植物は交雑しやすいので、注意が必要です。京都の伝統野菜である京野菜の水菜は、葉にギザギザの切れ込みがありますが、壬生菜は丸い葉の形をしており、丸葉水菜とも呼ばれています。壬生菜は1800年代後半に蕪(かぶ)との交雑で生まれたと推定されています。水菜はサッパリとした風味ですが、壬生菜はピリッとした辛味、苦味が特徴です。
6.育種・品種改良
時には人の手も借りる
育種・品種改良とは、生物の遺伝的性質を改良して、より優れた品種をつくり出すことです。育種の方法は大きく分離育種法と交配育種法に分けられます。
「選抜育種」は「分離育種」とも言われ、遺伝的に多様な個体が混じっている在来種から優良な個体を選び出す方法で、栽培者が、病気に強いものや品質の安定しているものを選抜し、翌年の栽培用に種子を採種します。
「交配育種」は「交雑育種」とも言われ、遺伝的に異なる品種間で交配を行い、その中から優良な個体を生み出す方法です。いわゆるF1種といわれるもので、現在、日本の野菜の9割強はこのF1品種です。
他にも、近年では「遺伝子組み換え」や「ゲノム編集」といった方法も開発されています。これらの方法によって、耐暑・耐寒性、耐病害虫や薬剤耐性のある品種に改良することもあります。
まとめ
野菜は、気候や風土に適応するために様々に変容し生き延びようとします。この変容は、形態から生理生態、遺伝子に及び、最終的には突然変異などの進化につながる可能性もあります。また、人間の手による品種改良や栽培技術も野菜の変容に大きく関わります。
ここで、紹介した適応例は、ほんの上辺のほんの一部であり、農作物の奥深さは計り知れません。
日本各地に根づき、長い年月を経た伝統野菜・在来種の野菜は、その土地の気候風土にベストな状態で適応して味や栄養成分を生み出し、時に人の手を借りて選抜されるなどして「その土地ならでは」の野菜になっています。長い年月の間もタネを絶やさずに生き延びてきた品種です。過去の気候変動では、一時的に収穫物は不作になることがあっても遺伝子の多様性を持つ伝統野菜・在来種は継承され続けてきました。
今後は、気候変動によって野菜の生育適地が移動する可能性もありますが、適応力の高い在来種の遺伝的多様性を活かしつつ次世代に残していきたいものです。
【参考文献】
藤井一志『土と生命の46億年史 土と進化の謎に迫る』(2024)講談社ブルーバックス
日本植物生理学会『これでナットク! 植物の謎―植木屋さんも知らないたくましいその生き方』(2007)講談社ブルーバックス
日本植物生理学会『これでナットク! 植物の謎 Part2』(2013)講談社ブルーバックス
「植物の軸と情報」特定領域研究班 著『植物の生存戦略―「じっとしているという知恵」に学ぶ 』朝日選書 821(2007)
矢原徹一, 鷲谷いづみ著『保全生態学入門 改訂版: 遺伝子からランドスケープまで』 (2023) 文一総合出版
BSI 生物科学研究所「植物生育の基本要素」
農研機構「植物の耐凍性を向上させる新しい遺伝子を発見」(2009)
Buna「冬に植物は凍らないの? 植物が寒さを生き延びるしくみ」
森林林業学習館「日本の森林分布」
植物科学のトビラ
バイオステーション「さまざまな品種改良の方法」
【関連記事】
2024年 猛暑の夏 ~野菜の適応力について考える~
諸国を行き交う野菜の種 ~江戸時代に盛んになった種の移動~