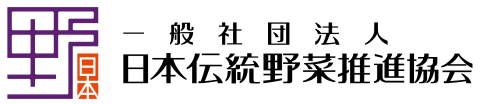目次
伝統野菜の定義
伝統野菜には、特に明確な定義はなく、主に日本各地で古くから栽培されてきた地方野菜のことを言います。
農林水産省のホームページでは、伝統野菜を「その土地で古くから作られてきたもので、 採種を繰り返していく中で、その土地の気候風土にあった野菜として確立されてきたもの」と説明しています。農林水産省(2010)野菜をめぐる新しい動き 伝統野菜の実力.AFF 2010 年 2 月号〈https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/index_1002.html〉〈最終アクセス 2021 年 2 月 15 日〉
伝統野菜の基準
近頃は、全国的に伝統野菜の復活をめざす動きが広がっており、各都道府県がそれぞれ独自に基準を設け、伝統野菜や地域野菜として選定しています。
その基準は、「江戸時代から」といったものや、「戦前から」、「30年以上前から」、「50年には栽培」、「100年以上前から」などバラつきがあり、中には「古くから」というだけのザックリとした基準の地域もあります。いずれにせよ、長い年月をかけてその土地になじみ、定着したものが伝統野菜というわけです。
それぞれの野菜がどれぐらいの時間で、その土地の気候風土に適して固定化するのかは、品目それぞれなので、このあたりの緩い基準は伝統野菜・地域野菜らしさです。
日本に自生する野菜の種類
そもそも、日本の市場に出荷されている野菜のほとんどが海外から渡来したものです。
もともと日本に自生していた野菜は、ウド、オカヒジキ、山椒(サンショウ)、自然薯(ジネンジョ)、じゅん菜(ジュンサイ)、芹(セリ)、蓼(タデ)、つる菜(ツルナ)、浜防風(ハマボウフウ)、菱(ヒシ)、蕗(フキ)、松菜(マツナ)、三つ葉(ミツバ)、茗荷(ミョウガ)、白藍(ハクラン)、ヤマゴボウ、ユリ、山葵(ワサビ)、牛蒡薊(ゴボウアザミ)、枸杞(クコ)など20種類ほどだとされています。

これらの野菜は、料理の主役として使われることは少なく、薬味のような位置づけで使われています。
渡来の野菜が日本に定着
ヨーロッパや中国、アジア諸国など海外から渡ってきた数々の野菜は、日本各地に広がり、時の流れの中、採種を繰り返すうちに、それぞれの土地の気候風土に適した野菜として形質が固定化し、地域野菜として定着していきました。
これらの野菜は、在来種、固定種と呼ばれるもので、40~50年前までは各地で当たり前に食され、地域の食文化とも密接に関係してきました。たとえば、全国的に有名な信州の野沢菜漬けの野沢菜は、長野県下高井郡野沢温泉村を中心とした地域で栽培されてきた野菜ですし、名古屋名物の守口漬は、岐阜・愛知で栽培されていたホソリ大根や美濃干大根と呼ばれていたもの(現在は、守口大根)が今でも使われています。
在来種、固定種の歴史
しかし、大部分の在来種、固定種は、歴史の流れの中で、その姿を消しつつあります。
ここでは、伝統野菜である在来種、固定種が衰退に至るまでの歴史をみていきます。
戦後の食糧事情
戦後の物資欠乏や飢餓の時代を経て、日本国民の食糧が安定的に供給されるようになったのは1950年代に入ってからでした。
戦後しばらくの間は、野菜などの生鮮食品は法的な統制下にありましたが、その統制もすぐに解かれ、各地で本格的に栽培・供給が再開されました。
その頃の野菜は、それぞれの地域では当り前であった在来種、固定種です。戦争で壊滅的になっていた品種も復活し、1950年代の後半には、戦前の水準をほぼ取り戻しました。
西洋型の食事への移行
やがて、経済の復興に伴い日本の食卓にも変化が訪れます。
米・魚・みそ汁といった和食の食事からパン・肉・牛乳の洋食に移行していったのです。
これに合わせて、野菜の種類も変化し、大根や白菜などの和食に合う野菜は衰退し、たまねぎ、キャベツ、レタス、ピーマン、トマトなど洋食に合った野菜の消費が伸びていきました。また、同じ種類の野菜の中でも、にんじん、かぼちゃ、ほうれん草などは東洋型の品種から西洋型の品種に移っていきました。
大量生産時代の到来
経済が高度成長期に入り、都市部への人口流入が加速すると、大都市への生鮮食品の安定的な供給が求められるようになってきます。
本来、旬に応じて収穫され、大きさや味には多少のバラつきが出て当り前の野菜に対しても、工業製品のように一定の量と質という均質化・規格化が求められるようになりました。
そのため、地方野菜の中から、どこでも誰でも栽培できる育てやすい品種が選ばれ、広範囲で栽培され流通されるようになりました。それ以外の在来種、固定種は徐々に栽培する農産者が減少していきました。このことが、在来種、固定種の最初の衰退要因と言えます。

雑種第一代(F1)の台頭
さらに、この頃、F1種という品種改良を行った野菜の育成が軌道に乗ってきました。
F1種が最初に作られたのは大正15年、埼玉県農事試験場で作られたナスで、野菜では、なんと世界初でした。この成功を皮切りに全国各地で固定種からF1種の作成が試みられていきます。
ちょうど高度成長期に入った頃、F1種の育成が軌道に乗ります。
F1種は、野菜の形や大きさの揃いが良く、成長も早く、同じ時期に一斉に収穫でき、これが時代のニーズにマッチしました。経済合理性の高いF1採種ができる品種は、みなF1種にとって変わっていきました。
これによって、在来種、固定種は一挙に衰退の道を辿っていくこととなります。
自家採種から種子購入へ
均質化・規格化においては、圧倒的に有利なF1種に対して、在来種、固定種は品質が均一ではありません。野菜の揃いが悪く、手間がかかり、そのうえ、その地域の気候風土に合わせた独自の栽培技術を必要とする地域野菜ならではの品種もあります。また、採種をするために、一部を収穫せずに残しておかなければならず、畑の生産効率を下げてしまいます。F1種は種子を購入するため、採種の手間が省けますし、その間の二期作や二毛作も行いやすくなります。
消費者の規格化ニーズと農業者の生産効率ニーズが合致し、瞬く間にF1種が市場を席巻。農業のスタイルは「固定種で自家採種」から「F1種で毎年種子を購入」へと変わっていったのです。
在来種、固定種の終焉
戦後の食糧不足から脱したのが1950年代後半。それから10年経つか経たないかの期間で、日本の野菜は、そのほとんどが在来種、固定種からF1種に移行しました。
時代や社会は、効率化や均質化、規格化に合う野菜を求めたのです。
1965年頃を境に在来種、固定種は、大消費地向けの市場から姿を消し、地域の農家が自家需要で栽培するにとどまり、中には消滅してしまった品種も数多くあります。
在来種、固定種は、このまま絶滅を迎えてしまうだろうと予想されました。
在来種、固定種の復活
しかし、半世紀近くの間、ひっそりと自家需要などの栽培しかされて来なかった在来種、固定種に、ここにきて再び注目が集まってきています。
1980年代半ば頃から少しづつ推進されてきた「地産地消」の流れに加え、2013年に「和食」が無形文化遺産に登録されたことが推進力となり、地域おこしの産品としても掘り起こしが活発化しています。
こうして、在来種、固定種は、新たに「伝統野菜」、「地域野菜」と呼ばれるようになり、単なる「地産地消」の農産物としてだけでなく、地域の特産品、スローフードという新しい切り口での需要が喚起されつつあります。
しかし、伝統野菜として復活したのは、かつての在来種、固定種のうちの一部だけであり、消滅してしまった品種は取り戻せません。
今後は、現存する伝統野菜の種を絶えることのないよう、保存・継承していくことが、とても重要です。
監修 高木幹夫